連日大雪が続いた花街だったが、今宵は珍しく雨が降っていた。
激しい雨粒の音と共に、大勢の使用人が一階の大広間へと忙しなく行き来する音が響き渡る。自室で準備を進める遊女たちは、その騒々しさにうんざりと顔を見合わせた。炊事場では豪勢な食事を作っている最中で、人手不足による苛立ちからか、いつにも増して激しい怒声が飛び交う。
夜見世が始まるまで残り半刻。妓楼内は本日急に行われることとなった大宴会の準備に追われ、どこもかしこも嫌に殺気立っていた。
その喧騒の端。とある会計部屋の机にて、妓夫の熊郎は一人帳簿の整理に明け暮れていた。鈍臭い彼が宴会の準備に宛がわれた試しは一度もなく、忙しい時はこうして適当な仕事を割り振られては隅に追いやられるのだ。尚、本人はそのことに全く気がついていない。
のんびりとした手つきで仕事をこなすその傍らで、美しい着物と桜の簪で着飾った一人の芸者が物憂げな表情で俯いていた。腕の中の三味線をぎゅっと抱きしめ、その拍子に揺れた弦の音色はどことなく悲しげだった。
「ねえ、どうして会いに来てくれないんだと思う?」
大切な主語が抜けているが、それが"誰"なのかは言わずとも知れている。ここ数日やけに浮き沈みが激しいと思ってはいたが、それが原因か。
仕事中ちょっかいを出しに現れるのは、決まって悩み事を打ち明けたい時だ。熊郎は内心面倒臭がりながらも可愛い妹分の為、それとなく相槌を返してやることにした。鈴蘭の話を聞いてやれるのは、忙しい姉さん遊女たちを除けば自分以外は他にいないのだ。
「そりゃあ、前回お前を買う為に大金払ったんだ。また必死こいて稼いでんだろ」
「……わたしが失礼なことしたから、怒ってるんじゃないのかな」
「寝坊のことか?あれは俺もどうかと思ったけどよ。不愉快に感じたら、贈り物なんて俺に預けないでその辺に捨てたと思うぞ」
「そっか、そうだよね。えへへ」
沈んだ気分はどこへやら、熊郎のやる気のない励ましに安心した鈴蘭はたちまち笑顔を浮かべながら、手元の三味線で弾き語りをし始めた。「仕事してんだから静かにしろ」と諫めると、鈴蘭は「ごめんね」と口を噤む。しかしその口角は依然として上がったままで、熊郎は我慢ならずついに尋ねた。
「お前、最近どうしちまったんだ?見るからにふわふわ浮き足立ってて、何だか気味悪いんだけど。まさかあの旦那に、恋でもしてるんじゃないだろうな」
その途端、鈴蘭の横顔は林檎のように赤く色めいた。色恋沙汰に疎く縁もない熊郎でも、己の何気ない発言が彼の図星を突いたことは流石に勘づく。何だ、お前いつの間に恋なんか。あの旦那は友達じゃなかったのか?
動揺する熊郎に目もくれず、鈴蘭は三味線を置き、凛とした表情で瞳を閉じていた。まるで愛する人を思い浮かべているかのように。鼓動に震える両手は、左胸の前で強く握り締めていた。まるで胸の病を訴えるかのように。
「……あの人を想うとね、心臓が凄く苦しくなる。会いたくて堪らなくなる。こんな切ない気持ちになるのは、生まれて初めてなんだ。ねえ熊郎、これって“恋”なの?」
「いや俺に聞くなよ」
「うん、恋だよね、絶対にそうだよね!」
「分かってんなら何で聞いたんだよ」
景気良く立ち上がった鈴蘭は頬を染め、今度は乙女のように軽い足取りで部屋中をうろうろと彷徨い始めた。
そう、あの日登与助に贈られた簪のおかげで、鈴蘭は完全に恋に落ちていた。こめかみに美しい桜を咲かせた己が鏡に映った瞬間、心の中で桜吹雪が嵐の如く渦巻いたのだ。それからの日々は、彼と指切りを交わしてから友人として過ごしてきた時以上に、世界を見る目が一変した。
彼に似合いそうな色の着物を纏った客には目を惹かれ、彼の雰囲気に合う曲を見つけると心躍り、大雨が降った日には客足が遠のくことに落ち込んでいるであろう彼を憂えた。何を見ても、何をしていても、無意識のまま心に浮かべてるのはいつもあの登与助の姿だ。苦しくて切なく、心地の良い感覚。誰かを心から想うことでこんなにも多幸感を味わえるなど、今までの鈴蘭には到底知り得ないことであった。
しかし熊郎にも愚痴を零した通り、登与助はここ暫くの間全く姿を見せようとしない。彼に嫌われている気はないが、あんなにも頻繁だった逢瀬がこうも不自然に途切れると、どうしても不安を感じてしまう。いつ来てもいいように、毎日あの簪を身に着けているというのに。燻った気持ちを晴らせるのなら、なけなしの言葉でも励ましでも何でも良かった。それで今回白羽の矢を立てたのが熊郎というわけだ。
一方、無意味な押し問答を強要された熊郎は初めこそ驚いたものの、意外にもその告白をすんなりと受け入れていた。あの若き青年──登与助は、今まで怖気ついていた鈴蘭を上手く煽り、見事三味線の才能を開花させた。それだけでなく、友人にもなってくれた有り難い人物だ。生業柄熊郎は大勢の男を見てきたが、遊女である鈴蘭を一人の“女の子”として対等に扱ったのは紛れもなく彼だけだ。そんな彼に惹かれるのは、一理どころか千里ある。
他人に抱いた初めての感情に戸惑いながらも、どこか嬉しそうに噛みしめている鈴蘭を目で追い、熊郎は珍しく優しい声をかけてやった。
「それならまあ、応援してやらないこともないぞ。俺もあの旦那は良い奴だと思ってるし。いつか好いてもらえたらいいな」
鈴蘭はぴたりと立ち止まる。どうしたことか、一転して顔を曇らせていた。そして怪訝な表情で伺う熊郎に対し、諦めたような笑顔を向ける。
「……どうだろう。登与助さんはわたしを友達として見てるだろうし、ちゃんと大人の女の人が好きだって言ってた。ぶきっちょで子どものわたしなんて、きっと眼中にもないと思う」
「何だよお前、あの人が好きなんだろ?独占したいんじゃないのか?」
「あはは。できっこないよ。それに、思いを成就させたいだなんて贅沢な願い、まかり通るわけがないもの。……いいんだ。わたしは登与助さんを想えるだけで、充分幸せな気持ちになれるんだから」
それは、まるで自身に言い聞かせているかのような口振りだった。あまりに口惜しいが、かけてやれる言葉が何も浮かばない。熊郎は掘り下げたことを後悔しながら、そっと視線を外した。
己の無力さに打ちのめされる感覚は、此処で何度も味わってきている。弄ばれた陰部の痛みに呻く遊女や、足抜けをした罪で折檻を受けた遊女。そういった彼女たちの手当てを一任されている熊郎は、生き地獄に苦しむ仲間に秘蔵の薬を塗り、震えるその背をただ擦ってやることしかできないのだ。
心のどこかで割り切らねば、と常日頃思いつつもついお節介ばかりを焼いてしまう熊郎の性分は、他の妓夫からは鬱陶しがられていた。本人は例の如く気づいていないが。
静かに三味線を拾い上げ、鈴蘭は出口へと歩いていく。
「お邪魔しました。もうすぐ出番だから、わたし行くね」
「ああ、そういえば今日の芸者に抜擢されたんだったな。下手こくなよ」
「分かってるよ。……聞いてくれてありがとう、熊郎!」
そう言い残し、鈴蘭は柔らかく微笑んだのち姿を消した。
ちっとも作業が進んでいない机を見渡し、倦怠感に満ちた溜息を吐きながら熊郎は天井を見上げる。
“登与助は友達として見ているだろう“。
先程の鈴蘭の言葉をふと思い出す。まるでその事実は揺るぎないものであると主張するような顔つきであったが、どうも熊郎の腑には落ちなかった。
見習いの身なら遊郭に通う余裕などありはしない、恐らく彼は仕事を増やしてでも金を稼いでいるのだろう。大層な手作りの贈り物まで用意し、何よりも一番印象強いのは門前払いに対し決して引き下がらなかったあの態度だ。あの時の剣幕は、友人と言い張るにしては些か度が行き過ぎているように思えてならない。
もしや旦那も満更でないのでは、と好き勝手に憶測を立て始めた熊郎は手元がおろそかになり、数分後に様子を見に来た遣手にこっぴどく叱られる羽目となる。
件の大宴会は滞りなく行われた。やがて主の命により、従者達はそれぞれの座敷に遊女数人を呼び立て、各々の時間を過ごしていた。突然予約を申し込んできた横暴なご一行に初めは憤っていた楼主であったが、彼らの大盤振る舞いにすっかり上機嫌な態度へと様変わりした様子だ。こんな小さな妓楼にかの有名な大豪商が訪れるなど、数年に一度あるかないかの大事件である。
決して機嫌を損ねないように、と楼主本人から再三の注意を受けたミゲルは、ごくりと生唾を飲み込んだ。畳に額が当たりそうなくらいに深く下げた頭を、いつ上げれば良いのか分からない。しどろもどろになったとはいえ、定められた口上は一言一句余すことなく述べた。
しかし目の前に座った男は、鈴蘭が座敷に着いた頃からずっと沈黙を貫いたままで、何も応えようとしないのだ。緊張のあまり湧き出た一筋の汗が、緩やかに鈴蘭の額を伝った。
「鈴蘭」
その瞬間ようやく名を呼ばれ、鈴蘭は天井まで跳ね上がる勢いで顔を上げた。初めて両者の目が合う。にこやかな微笑を浮かべた男は、愉悦を含んだ瞳でこの小さな遊女を眺めていた。どこか緊迫感の漂う座敷に、よく通る落ち着いた彼の声が響く。
「そんなに固まらずともいい。楽に寛ぎなさい」
「はっ、はい……!」
「もしや、突然呼び立てた私の無礼に腹を立てているのかな?すまないね。君の美しい音色に惹かれたものだから、どうしても二人きりで話がしたくなった」
「そ、そんな、滅相もありんせん!旦那様からの身に余るお言葉、まさに恐悦至極の思いでござりんす」
鈴蘭の上ずった声色に男はふふ、と拳で口元を押さえた。どこまでも気品を感じさせる声色や所作に、鈴蘭は顔から火が出そうなくらいの羞恥に襲われ更に汗を噴き出した。一刻も早くこの場から逃げ出したい。しかし当たり前ながらそんな無作法は誰にも許されない。何故このような大金持ちが、冴えない自分の指名をしたのだろう。
問いただす勇気もなく、すっかり委縮した様子の鈴蘭に向かって、男は尚も笑いながら手招いた。
「どれ。素晴らしい才能を持った若き芸者の顔を、もっと近くで見せておくれ」
鈴蘭は頷き、すぐさま腰を上げる。そして胡坐を掻いた男の元へと恐る恐る歩み寄った。手が届く距離まで近づいたその時、優しげだった彼の顔つきがにわかに移り変わった───その表情にどきりと心臓が跳ねる。
獣のように鋭い目つき、その瞳は鈴蘭を抱いてきた粗雑な男共と似た色味を帯びていたのだ。本能で危険を察した鈴蘭は思わず半歩退きかけたが、片腕を強引に引かれたせいで体勢を崩されてしまった。華奢な身体はあっという間に彼の腕の中へと収まり、声を出す間もなく唇が合わさった。
「ん……ッ!!???」
男の太い腕は鈴蘭の腰に回され、もう片方は頸をがしりと掴んでいる。どう足掻いても逃げられない状況だ。元より逃げていい理由も権利も与えられていないが、突然の出来事に思考が追いつかない鈴蘭は、息苦しさに身を激しく捩らせた。
男の舌は奥深くまで侵入し、好き勝手に狭い鈴蘭の口内を舐め回す。肉厚な唇が角度を変え何度もしゃぶりついてくる度に、次第に鈴蘭の背筋に甘い電撃が走るようになった。
愛撫を与えられれば、本人の意思関係なくみだらに反応してしまう──鈴蘭が落ちこぼれと称される所以はここにあった。“感じるのは遊女の恥”とされ遊女達は相応の訓練を受けるが、不器用な鈴蘭にとってそれは至難の業だったのだ。現に今も、びくびくと反らせた身体の全体重を男に預け、与えられた快楽にされるがままになっている。
「んぅっ、ん……ふ……!」
聞いていた通りの器量の悪さだ、と才谷は苦笑し、脱力した舌を絡め取り更に激しく吸いついた。より一層鼻にかかった嬌声が口の端から漏れる。あどけなさを存分に残した可愛らしいその声は、あの姉よりも幾分甲高いようだ。
飲み下せなかった唾液が、鈴蘭の顎を何度も伝う。そこでようやく才谷は口を離し、どちらのものかも分からない唾液で濡れた小ぶりな唇を、優しく親指で拭った。次いで口元の黒子を艶めかしい手つきでなぞる。荒い呼吸を繰り返しながら恍惚とした表情を浮かべてい少女に、才谷は密かに驚嘆した。
宴会の場にて三味線を披露した時の彼女は、誰よりも凛々しい顔つきであった。かと思いきや座敷に呼び立てた途端、先程まで険しかった眉は下がってしまい、まるで水揚げしたばかりの遊女のように落ち着かない素振りを繰り返しては、いとも簡単に快楽へと溺れる始末。
しかし、呆れた矢先に彼女が見せてきた色気漂う表情は、都で出会ったあの美しい花魁の姿を彷彿とさせた。押し寄せる支配欲と背徳感に唾が湧き、才谷はぺろりと舌舐めずりをしながら呟いた。
「本当に瓜二つだな。顔だけでなく、舌先の味や感触まで」
誰と比べられているのだろう、と鈴蘭は息も絶え絶えになりながら不思議そうに首を傾げる。
しかし才谷は応えることなく、鈴蘭の腰を引き寄せ耳元へと口を近づけた。欲情を孕んだ吐息がかかり、再び愛撫されると思い込んだ鈴蘭は身体を強張らせたが、囁かれた言葉に思わず目を見張る。
「──鈴蘭、私は君に身請けを申し込みたいと思っている」
「……えっ?」
素っ頓狂な声を上げ、ぴしりと固まるミゲル。対して才谷は落ち着き払った態度のまま語りかけた。
「この鳥籠の中で生涯を終えるには、君はあまりにも惜しい存在だ。想像してみたことはないか?例えるならば、そう……とある芝居小屋の舞台上、君は緋毛氈を掛けた雛壇に座す芸者の一人。次々と繰り広げられる役者達の演技に合わせ、思いのままに三味線を打ち鳴らす。大勢の客がその見事な演奏に聞き惚れ、釘づけになるだろう。最後に君を待ち受けているのは、拍手喝采の嵐だ」
予想だにしていなかった男の申し立てを認識する前に、言われるがままにその情景を思い浮べた。
今まで三味線しか取り柄のなかった自分が晴れて自由の身となり、外の世界にて思う存分音楽に浸るという物語。この数か月で楽器との付き合い方がぐんと変わった鈴蘭にとって、それは何度も何度も思い描いてきた夢物語だ。そしてその回数分、叶うわけがないと何度も諦めてきた。
「私も少々音楽を嗜む身でね。君の三味線に対する熱意を、人一倍強く感じたのだよ」
鈴蘭は無性に照れ臭くなり、そっと俯いた。今まで真摯に褒めてくれたのは、あの友人だけだ。故に、他者からこれ程までの賛辞を贈られるのはどうにも気恥ずかしくて堪らない。しかし鈴蘭の心を揺さぶる感情は、喜びよりも戸惑いの方が遥かに大きかった。評価そのものは恐れ多くなる程に有り難みを感じている反面、どうしても彼の思惑が解せないのだ。
失礼は承知の上、鈴蘭は彼の真意を探るべく震える声で問いかけた。
「旦那様。出過ぎたことをお尋ねしんすが、どうしてわっちなんかの為にそこまで?」
遊女の身請けにはかなりの大金がかかる。いくら下級遊女といえど鈴蘭は六年間勤めてきた身、数百両は必要となるだろう。大豪商の彼ならば然程痛くない出費なのかもしれないが、身請けするとなると誰もが配慮するのは、言わずもがな世間体である。一般的な遊女ならともかく落ちこぼれの下級遊女──しかもまだ幼い少女の身を貰い受けたとなると、どれだけ好奇の目に晒されることになるのか。彼ほどの男に想像がつかないわけもあるまい。
尋ねられた才谷は如何にも居心地が悪そうに視線を泳がせ「年甲斐も無いと笑われてしまうかな」と首の後ろを掻く。そののち、はにかんだ笑顔を浮かべながら、腕の中の鈴蘭をしかと見据えた。
「正直に思いの丈を伝えよう……鈴蘭、一目見た時から私は心を奪われてしまった。素晴らしい演奏だけでなく、愛くるしい君の全てに」
告白と同時に、大きな両腕が鈴蘭の身体を包み込んだ。強い力で抱きしめられた鈴蘭は、ただ唖然と、口を開けることしかできなかった。
挨拶代わりかと思っていた口づけも、思わず畏まってしまうような破格の待遇も“全て君への恋心に突き動かされたのだ“と、彼は喋々しく謳った。
「無論、先の言葉は建前ではないぞ?古くからの知り合いに座長がいる。私が口添えすれば、君は瞬く間に舞台へと上がれるだろう。もう見知らぬ男に身体を売る必要はない、借金に苦しむ生活ともおさらばだ。君は希望に満ちたこの広い世界を、自由に羽ばたけるのだよ」
「私の物になってくれるなら」と、魅力的な甘い囁きが耳をくすぐる。誰が見てもまたとない好機だ。もしこれを逃せば、この地獄から解放される日は恐らく二度と来ないだろう。
他の遊女であれば感涙に咽び、二つ返事で受け入れるであろう場面だが、当の鈴蘭は………虚空を見つめながら静かに耐えていた。身体をまさぐる彼の手つきによって生じた、身の毛もよだつような激しい嫌悪感に。
才谷は黙り込んだ鈴蘭のそんな様子に薄々勘づいていながらも、わざと同じ調子で続けた。
「……出会ったばかりの男に“信じろ”と言われても難しい話だろうな。ならまずはその身体に、私の愛を教え込むとしよう」
背中に回していた右手を持ち上げ頸へと持っていき、鎖骨に指を沿わせる。そして胸元へ手を差し込もうとした途端、石のように固まっていた鈴蘭はあらん限りの力を込め彼の胸を突き飛ばした。
同時に、拒絶を示す一声を発してしまった。
「離してっ……!!!!!!」
響き渡る叫声、刹那────暴力を働いた鈴蘭は反動で畳に尻もちをつき、受けた才谷は咄嗟に手をつき身体を支えたおかげで、体勢を大きく崩さずに済んだ。息切れを起こしながら、鈴蘭は無意識に動いた己の両手を茫然と見つめた。衝撃により、熱を持った手の平はじんじんと痛んでいる。思考よりも先に身体が動くなど、初めての経験だ。
しかし驚いたのも束の間、脳内に先程の記憶が蘇る。瞬く間に冷たい戦慄が走り、鈴蘭は四つん這いの状態で一心不乱に客の元へと這いずった。
「お、お怪我は!?」
無言で首を振るその顔には、今まで浮かべていた笑顔の欠片一つも見当たらない。それもその筈、自分を好いてくれただけでなく身請けまで申し込んでくれた客に対して、許されない無礼を働いてしまったのだ。
鈴蘭は意識が遠のきそうになりながらも、勢い良く畳に額を擦りつけた。その拍子に、桜の簪がしゃらんと音を立てる。
「どうか許しておくんなまし、旦那様……!」
下級遊女如きの安い土下座だけで済むとは到底思えないが、青ざめた鈴蘭は無我夢中で謝り続けた。
此処はとにかく小さな妓楼だ。ちっぽけな評判一つでさえ、その日の集客に大きな影響を及ぼす。もしも彼が鈴蘭の失態を言いふらせば売り上げは不振に陥るだろうし、品位を下げた罰として折檻は免れない。大昔、一度だけ足抜けを試みた際に刻まれた古傷が、ところどころじんわりと痛み出す。鈴蘭は顔を歪めながらも、呻き声を出さぬよう懸命に堪えた。
その頃、デラクルスは目の前で小刻みに震える遊女を、胡坐をかいたまま物珍しそうに眺めていた。こうも真っ向から私を拒絶するとは、見た目に反して勇気があるらしい。そのくせ、今は小鹿のようにぶるぶると怯えている。
あまりにもその姿がいじらしく面白いので、才谷は不安を煽るようにわざと大きな溜息を吐いてみせた。
「相分かった。これが君の返答というわけだな、鈴蘭」
「……だ、旦那様のお心遣いは、誠に以って、か、感謝の言葉もありんせん。けれどわっちは、わっちには」
どうしても此処から離れられない理由があるのだ。そこまで吐露する気はないので鈴蘭は言葉を詰まらせたが、興味深そうな表情をした才谷は顎を擦りながら、了承も得ず勝手に代弁した。
「“あの見習い職人がいるから”か?」
傷の痛みが、血の気と共に引いていく。身じろいだ鈴蘭を見て「図星だな」と、渋みを利かせた低い笑い声が頭上から響いた。
「君と仲の良い遊女達が教えてくれたのだよ。この数か月の内に、親しくなった若者がいると。ただ、二人はただの交友関係にあると聞かされたのだが……君がそこまで固執しているとなると、私としては理由を聞かざるを得ないな」
何かと厳しく当たってくる先輩遊女たちの顔が、鈴蘭の脳内をちらつく。しかし、不思議と彼女らを恨む気は起きない。例えあの遊女たちが教えずとも、楼主や使用人に問いただせばすぐに漏らされたであろう情報なのだから。
依然として額を堅い畳に押しつけながら、鈴蘭は掠れた声を絞り出した。
「わっちが……ただ、片想いをしているだけでありんす」
片想い。
その言葉に才谷は一瞬で思考を巡らせた。そして小さく縮こまった鈴蘭を一瞥し、如何にも気遣うような優しい声色に切り替えた。
「成る程、私を拒む理由としては頷ける」
「だ、旦那様……」
「だがな鈴蘭。君が強く恋い焦がれているのは、しがない下駄職人の見習いだ。彼らの収入が如何程のものかは、外界を知らない君でも想像に難くないだろう。今一度、彼の姿を思い出してごらん」
「……!」
鈴蘭は言われた通りに登与助の姿を想像した。彼と顔を合わせたのは、直近でも二か月前のことだ。継ぎ接ぎだらけの着物を身に纏い、あまり身なりに気を配らない質なのか髪の毛もまともに櫛を入れておらず、お世辞にも素敵な殿方とはいえない風貌。寝起きも非常に悪く“起きない時は思いきり殴っていい”との言いつけだったので、毎度の如く殴打を与えて目覚めさせていた。
そんな彼に対し、大人のくせにだらしないなといつも呆れ笑っていたが、今となっては愛おしいという気持ちが遥かに勝る。どんなにみすぼらしい格好であろうと、稼ぎが少なかろうと、彼に抱いた恋心に変わりはない。彼を貶めるのは筋違いというものだ。
才谷の物言いに少なからず憤慨した鈴蘭は、できるだけ冷静を保ちつつ顔を上げた。しかしその瞬間、自分を見下ろす男の厳しい瞳に悪寒が走る。目の前の男は、何故か今まで見せたことのない冷ややかな表情を浮かべていたのだ。先程の口調とは打って代わった非難にも似た声色が、鈴蘭の耳を刺した。
「話を聞くに、彼はとても義理堅い人間のようだ。友人の君に会う為ならどんな苦労も厭わないといった、自己犠牲的な性格だと伺える。違うか?」
「!、それは……」
「考えてもみなさい。いくら太鼓新造であろうと、積み重なれば決して安くはない額だ。裕福でないお人好しな彼は君の時間を買うにあたって、さぞや苦しい生活を強いられていることだろう。どんな若者でも、休む間もなく働けばいずれ限界というものが訪れる。そんな彼に、君は一体何をしてやれると言うんだ?恋心をひた隠し友人として振る舞い、己の欲求を満たす為、健気な振りをして彼に縋るのか?"またわたしに会いに来てね"と」
才谷の責めるような言葉を聞くにつれ、鈴蘭はようやく察知した。
草臥れた着物を新調しないのは、いつも目の下に隈があるのは、彼が仕事に根を詰めているからなのだと。口煩いらしい店主に対する愚痴を零すことはあれど、登与助は仕事に対する泣き言を一度も口にしたことがない。思えば鈴蘭も、彼と過ごしている時は弱音の一切を吐かないようにしている。全ては、相手を心配させまいといった気遣いだ。
彼が自分に声をかけたきっかけは、この生業に対する同情だったのかもしれない。「可哀想だ」と憐み慰めてくる男は今までに何人もいた。されど、友人になると申し出てくれたのは彼だけだ。軽蔑することもなく、汚れた身体を気にする素振りも見せず、彼はいつも隣で笑ってくれた。己の生活の辛さをひた隠して。
その優しさに何度も救われてきたというのに、何故肝心な部分に今まで気づくことができなかったのだろう。
鈴蘭は己の浅はかさを、そして未熟さを呪った。
彼の苦労を汲み取ろうともせず、会いに来てくれないことに自分は呑気に駄々を捏ねていた。何もかも自己満足でしかない、独り善がりな恋心。そんなものに浮かれていたことが、どれ程幼稚な行為であっただろうか。
あまりの不甲斐なさに打ちひしがれ、思わず目線を下げた。その瞬間に空気が揺れ、才谷の近づく気配を感じ取るも、鈴蘭は顔を上げることもなくひたすらに項垂れつづけた。
羞恥と後悔に顔を歪めた心優しい少女の耳元で、才谷は密かに微笑みながら極めつけの一言を放つ。
「彼を本当に想っているのなら、金で成り立つ関係を終わらせるのもまた一つの愛だ。……どのみち、彼が君を救い出せる日など永久にやってこないのだから」
丸い頬に幾筋もの涙が伝った。才谷の大きな手の平がそっと添えられ、労わるような仕草で指で涙を拭う。才谷はいつの間にやら優しげな表情に戻っていた。
「言っておくが、何も君達の仲を裂こうとは思っていないのだよ。取り返しのつかなくなる前にどうにかしてやりたいという、四十を過ぎた男の単なるお節介だ」
「……」
小さな顎を掬い、上を向かせた鈴蘭の目尻に口づけを落とす。真っ赤に泣き腫らしたそこは、かなりの熱を帯びていた。ぺろりと一舐めしただけで、塩気を含んだ涙の味が口内に広がる。もう抵抗することもなく、鈴蘭は無言でその愛撫を受け入れた。
才谷は無抵抗の人形と化した鈴蘭の身体を抱き上げ、そのまま背後に敷かれていた布団へと連れていった。そして覆い被さるようにして顔の両側に手をつき、じっと見下ろす。はらはらと大粒の涙を流しながらも、鈴蘭は視線を逸らさなかった。唇を真一文字に噛みしめる姿は、抗えない運命を懸命に受け入れようとしているように見えた。
ふいに、あの姉の姿が脳内を過ぎる。薄暗い月の光に照らされながら、一筋の涙と共に赦しを請うたあの夜の彼女。まるで本人が目の前にいるかのような錯覚に、才谷は驚いて瞬きを繰り返した。珍しい赤茶色の瞳、黒子の位置、あどけない顔立ち。この少女は紛れもなく彼女の妹なのだと再認識する。彼女が会いたい、会いたいと死ぬ程願っていた存在。
鈴蘭を手に入れることしか考えていない非情な手が、そっと帯を解いていった。
「此処に居座り、困苦窮乏に苦しみながらも友情を重んじる彼と添い遂げる妄想を続けるか。或いはわたしの物となり、彼とは良き文通仲間になるか……どちらが賢い選択かは一目瞭然だな。とは言え、急かすような真似はしたくない。鈴蘭。君に数日の猶予を与えよう」
考える暇を与えずとも返事は分かりきっているが。露わになっていく肌を撫でつけながら、才谷は胸の内で呟いた。
大人は狡猾だ。しかし返せる言葉など何もない。と鈴蘭は半ば自暴自棄になりながらも、涙でぼやける視界の中、ふと垣間見えた彼の瞳の中に違和感を覚えた。彼が見据えているのは自分である筈なのに、どこかが、何かが可笑しい。形容し難い感覚ではあるが、何百人と身体を重ねてきた鈴蘭には、確かに感じ取れた。彼は──。
目を瞬かせたその時、才谷はそっと唇を耳に寄せた。
「今宵だけは、この手を"登与助"のものだと思って構わないぞ。目を瞑り、彼の名を好きに呼ぶといい」
愛する彼の名を出された瞬間、鈴蘭の瞳から再び涙が零れ落ちた。その提案は優しさからか、それとも嘲弄 か。
いずれにせよ鈴蘭の脳内からは雑念が瞬く間に消え去り、最早登与助の姿を思い浮かべることしかできなくなった。
「……"登与助さん"」
弱々しく呟いたのと同時に、刺すような鋭い痛みが首に走った。鈴蘭は涙を飛ばしながら甲高く叫ぶ。荒々しく首元に噛みついた才谷は、縮こまった身体を叱咤するかのように太ももに爪を立てた。びくんと弓なりにのけ反った首筋を待ち構えていたかの如く、彼は角度を変え無数の鬱血痕を残していった。
激しい愛撫のせいで、涙が引っきりなしに溢れ出る。
「痛、い!嫌ぁっ……!!」
「呼びなさい」
「……!」
才谷の整った爪が、子どもの柔らかな肉に食い込む。血が滲んでしまう前に、鈴蘭は怯えながら喘ぐように繰り返した。
「……登与、助さん、登与助さん」
その様子に気を良くした才谷は下帯を捲り、縮こまっていた鈴蘭の小さな入り口を手荒く愛撫し始めた。痛みと不快感が一気に胸を支配したが、鈴蘭は目を閉じ何度も名を呼んだ。今己に触れているのは、登与助である。あの、大好きな、登与助であると必死で言い聞かせるように。
誰かを抱く時、あの人は一体どのような顔をするのだろう。男前な彼のことだ、眉根を寄せ如何にも真剣な眼差しを向けてくれるに違いない。それとも相手を怖がらせないよう、優しく微笑んでくれるかもしれない。
するとどうしたことか、次第に鈴蘭の身体は熱を増していき、痺れるような快感が全身に広がった。愛するあの人に触れられているとさえ思えば、顔が歪んでしまうほどの痛みもどうやら快楽に繋がるらしい。我ながら何と単純で、汚れた身体なのだろう。自身を嘲笑するような笑みが、自然と鈴蘭の口元に浮かんだ。
愛の伴わない行為には慣れていた筈なのに、今夜だけは心が砕けてしまいそうだ。せめてもと思い桜の簪を外そうとしたが────その手も、目敏い才谷によって阻まれ頭上に縫いつけられてしまった。
湿った花街の通りを歩く者はほとんどおらず、代わりにどの妓楼からも、下品な男の息遣いや遊女達の艶やかな声がそこかしこで響いてくる。
屋根に敷き詰められた瓦に激しく打ちつける冷たい雨粒は、どこか切なげな泣き声のようにも聞こえてならない。芯まで冷え込む冬の雨は、朝方まで降り止むことなく、どこへも行けない鳥籠の中の遊女たちの頰を、しとどに濡らした。

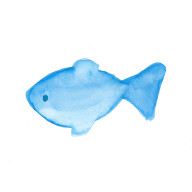

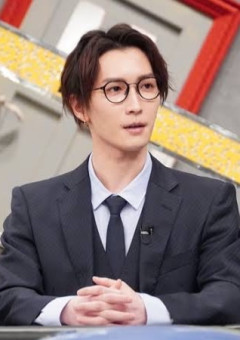















編集部コメント
主人公は鈍感で口下手ではあるものの『コミュ障』というほどではないので、キャラの作り込みに関しては一考の余地があるものの、楽曲テーマ、オーディオドラマ前提、登場人物の数などの制約が多いコンテストにおいて、条件内できちんと可愛らしくまとまっているお話でした!<br />転校生、幼馴染、親友といった王道ポジションのキャラたちがストーリーの中でそれぞれの役割を果たし、ハッピーな読後感に仕上がっています。