時は夕刻を回った頃。開け放たれた下駄屋の戸の入り口で、褪せた色の枯れ葉が木枯らしによって宙を舞う。それを見ていた店主の左衛門が、秋の訪れを感じ取りそっと溜息を吐いた。今年は特に陽が落ちるのが早い。急に冷え込んだせいで、人の通りもばったり途絶えてしまった。店は閑古鳥が鳴く始末だ。仕方がないので、そわそわと帰りたがっていた息子同然の見習い職人も、先ほど早くに上がらせてやった。
ようやく雑務を終わらせた左衛門が店先を閉めようとしたその時、馴染みのある声が耳に届く。
「よう左衛門、調子はどうだい」
「ようトラぁ。……調子も何もなあ。見ての通り今日は店仕舞いだよ」
陽気に訪ねてきたその男──小間物屋の店主の寅次郎は、笑いながら質素な風呂敷を手渡してきた。彼と左衛門は商店街ができでからかれこれ十数年の付き合いだ。妻に先立たれ身も心も老いた左衛門を心配し、時折こうして手土産を片手に他愛もない話をしに来てくれる。左衛門にとっては気の置けない兄弟のような存在だ。
「いつも悪ぃな。おお大根の煮物か、俺の大好物だ」
「気にしないでくれや。それはそうと……大丈夫なのか?」
「何だと?失礼な、俺ぁまだ歯なんて弱っとらん!その気になりゃあ畑にぶっささってる大根だって食えるぞ!」
「いや誰もあんたの心配なんてしてねえよ!あんたんとこの登与助のこった!」
人一倍怒りの沸騰がはやい左衛門の青筋立った顔が、その名を聞いた途端見る見る内に不安げな表情へと移り変わった。俯く老人を心配そうに伺いながら、寅次郎は戸を閉め、中の玄関に腰を下ろした。立ち竦んでいたままの左衛門も、手招きされ大人しく隣へと腰掛ける。互いに目線を合わせるでもなく、暫しの沈黙が続いた。外ではびゅうびゅうと北風が吹き、古びた戸を何度も音を立てて揺らす。
先に気まずい空気に耐えられなくなったのは寅次郎のほうだ。わざとらしく咳払いをした。
「あいつ、最近やたらと仕事に根を詰めてるだろ?目に隈なんぞこさえてよ。あんたその理由知ってるか?」
「……直接聞いたわけじゃねえが、目星くらいはとうについてるさ」
「やっぱりなぁ。まさかあの登与助が遊女に入れ込むたあ、思ってもみなかった」
寅次郎の呆れ口調に、左衛門はがっくりと肩を落とした。口は軽くとも根は至極真面目で人当たりも良く、この下駄屋の見習い職人は誰が見ても好青年だと思うだろう。その彼が、よもやほんの三か月前に出逢った遊女にここまで熱を上げる事態になるとは、彼と深い付き合いである左衛門にも寅次郎にも全く予想のつかない出来事であった。
「…多分、今日も行ったと思うぜぇあいつは。今月の駄賃渡したらそりゃもう嬉しそうに飛びついてきやがったんでな」
「は!?ってことはもう四度目じゃねえか!……なあ、一昨日俺んとこに来たんだが、あいつ何買っていったと思う?」
「何だ?勿体ぶるんじゃねえよ」
「髪飾りだよ、女物の!あれでもねえこれでもねえって随分と長い間選んでてよ。しかも一つじゃねえ。そんなに買ってどうすんだって聞いたら、どうやらその髪飾りの装飾使って、何か手作りするみたいでよ…」
左衛門は堪らず大きな溜息を吐いた。これは完全に浮かれている。男が遊女に手作りの贈り物を渡すなんて、まるで聞いたことがない。
金で成り立つ関係など、一人の女だけを愛し抜いた左衛門には到底理解できないものだった。見習い職人といえど彼の駄賃は決して高くない。そのお目当ての遊女とやらに会う為に、どうやら登与助は日雇いの仕事を増やして、寝る間を惜しんで小遣い稼ぎに勤しんでいるそうじゃないか。それは左衛門だけでなく、馴染み客や近所の者が不安に駆られる程の働きぶりだった。遊び人と名高い寅次郎でさえ、自分のことはとにかく後回しな登与助を見ぬ振りにはできず、こうして主人である左衛門に気を遣ってくる程だ。
目には隈、野暮ったい髪の毛、いつまでも新調しない継ぎ接ぎだらけの服。登与助が倒れてしまうのも、このままでは時間の問題だろう。
両者は顔を見やり、傍らに置いた煮物がすっかり冷めてしまうまで談論を続けた。こうと決めたら真っ直ぐ突き進む彼を説得するのは、きっと一筋縄ではいかない筈だ。
二人が悶々と頭を悩ませていた一方その頃。
噂の張本人はやっぱり予想通り、再びあの妓楼へと満を持して赴いていた。その懐には今日の為に用意した特別な贈り物。喜ぶ顔が早く見たいと浮き立つ彼がぽつんと座らされたのは、とある座敷の一部屋であった。
山水画の豪華な襖、小綺麗な鏡台に、使い込まれた茶箪笥と長火鉢。如何にも「女の自室」といった艶めかしい雰囲気である。以前まで通されていた質素な廻し部屋とは比べ物にならない。登与助は落ち着かない様子で何度も座り直した。客人の来訪により事前に焚きつけておいたであろう上品な香が、部屋の持ち主の像をそれとなく匂わせる。ここは花魁の部屋なのだと、案内した妓夫は言っていた。
僅か数十分前のことである。団体御一行による貸し切りを理由に門前払いをされた登与助は、見世番の妓夫に頼み込み、決してその場から立ち退こうとしなかった。溜まった疲れが鉛のように体に纏わりつき、睡眠不足で足はふらふらと覚束ない。会えないならばまた出直せばいいだけの話だが、疲労が頂点に達したその頭にはその判断は思い浮かびもしなかった。どうしても今日、あの子と顔を合わせて話がしたい。脳内を占めるのはただこれだけだった。
次第に、対応をしていた妓夫が困り果て、面倒事を押し付ける為に若手を呼び立てた。登与助を座敷に通した張本人は、呼ばれてきたその若い衆であった。背は登与助よりも高くずんぐりとした体躯。用心棒を呼ばれたのだと勘違いした登与助は思わず身構えたが、男は無言のまま登与助を座敷へ招き入れたのだった。
二階の一番奥の部屋前で立ち止まり、男はものぐさな風貌の割には素早い手つきで揚げ代を請求し、てきぱきと記帳に記す。散々渋られた要求をあっさり飲まれ、わけが分からないといった表情の登与助に気づき、それまで寡黙を貫いていた男はやっと口を開いた。
「此処は水仙姉さ……鈴蘭の姉貴分の部屋だ。本部屋を貸すなんてご法度だけど、姉さんに話してみたら“その客人になら貸してやってもいい“ってさ」
「そうか。その人には会えないのか?礼が言いたいな」
「風邪引いちまってるから無理。今日は大事を取って奥の座敷に籠もってんだ」
「……俺としちゃあ凄く有り難いしこう言うのもなんだが、どうして俺を特別扱いしてくれるんだ?常連なのはともかく、あんた達とは初対面の筈だろ」
尤もな問いかけに、男はぼりぼりと腹を掻きながら視線を泳がせた。どうも照れ臭そうな顔を浮かべている。
「……鈴蘭からよく聞いてるよ。友達になってくれたんだろ?あんたに会うようになってから、よく笑うんだ。たまに生意気だけど、俺たちにとって、あいつは妹みたいなもんだから。ちょっとは感謝してるっていうか、まあそんな感じだ」
「そう、なのか」
俺と会ってから、よく笑う?
鈴のように胸が高鳴り、登与助は思わず胸元を握りしめた。懐に入れていた贈り物が危うく潰れかけ、慌てて手を離す。男は一連の動作を不審そうに眺めながら襖を引いた。
「それじゃあ暫く中で待っててくだせえ。じきに来ますんで」
「でも待ってくれ!あんたやその花魁は、これがばれたら厳しく罰せられるんじゃないのか?」
「そうなったら水仙姉さんが上手くやるさ、あいつ世渡り上手いから。あと、一番端だから人は来ないだろうけど、あんまり騒がないでくれよな」
「……分かった。恩に着るよ」
「毎度どうも」
男は軽く頭を下げ、怠そうな足取りで持ち場へと戻っていった。
そして現在に至るというわけだ。妓夫の気配りと慣れない雰囲気のおかげで、可笑しくなっていた頭は大分冷えてくれた。この数週間身を粉にして働いたとはいえ、いい大人が迷惑をかけただけでなく年下に気を遣わせてしまうとは、何とも情けない話である。少し疲れているのかもしれないな、と登与助は畳の上で正座をし、ひっそりと反省した。
あの子とこうして顔を合わせるのは、確か今夜で四度目だっただろうか。あれから時の流れが急に早くなったようにも感じる。二度、三度と繰り返し会う事で、二人はすっかり打ち解けた間柄になっていた。
初めこそ大人びた立ち居振る舞いをしていたものの、一度殻を破れば鈴蘭は何にでも興味を示し、よく笑う、年相応で可愛らしい女の子だった。年の離れた妹がいたらきっとこんな感じだったのだろう。三味線の趣味が合う年下の友人と話すのは新鮮で、登与助にとって鈴蘭との時間はかけがえのないものになっていた。
音楽を語り出すとお互い話が止まらなくなり、隣の屏風から注意を受ける事もしばしばある。消灯の時間になれば布団に包まり、酒の場で仕入れたとんち話を披露するのがいつもの流れだ。お気に入りの話をしてやると、鈴蘭はいつも楽しそうにふくふくと笑いを堪える。店や店主の愚痴を零すと、鈴蘭も物珍しそうに相槌を打ってくれる。
一通り登与助が話し終えた後は、今度は鈴蘭が話す番だ。好きなものは三味線、甘い菓子(たまに客がくれる甘納豆が好物だと零していた)、桜吹雪が舞い散る季節、それと犬。
「わたしね、満開の桜を見たことがないんだ。風に乗った花びらが部屋に入ってきてくれるのを、毎年楽しみに待ってるの」
悟ったような瞳でぽつりぽつりと静かに語る姿が、脳裏に焼きついて離れない。その曇った表情を、少しでも笑顔に変えてやりたいと登与助が強く思うようになったのは、ここ最近のことだ。あの子の笑顔に会いに行くのではなく、自分があの子を笑顔にさせてやりたい。それは同情や憐みから芽生えた感情なのか、はたまた友愛の類なのか。自分でも判断はつかなかった。
ふと微かに布を引き摺る音が耳に入り、登与助はハッと顔を上げた。ぼんやり物思いに耽っている内に、待ち人が訪れたらしい。湧き上がる喜びに胸が震えた。登与助はすぐさま姿勢を崩し、未だ閉じられた襖へと視線を移す。やがてその襖は静かに引かれ、馴染みのある可愛らしい顔がひょこりと目の前に現れた。
声を掛けようとした瞬間、登与助は声を詰まらせる。
「登与助さん、来てくれたんだね……!遅くなってごめんなさい」
簪を揺らしながらいそいそと部屋に入る鈴蘭の笑顔は、いつも通り元気で目映い。急いで駆けつけたのであろう、少しだけ息が上がっている。至って普通かのように見えるが、登与助はその姿に言い知れぬ違和感を抱いた。彼女の纏う空気が、どことなく普段と違うのだ。すべらかな色白の肌には赤みが差し、形の良い唇はしとどに濡れ、潤んだ瞳はとろんと蜜のように蕩けている。いつも美しく着こなしている着物は若干乱れ、心なしか声も掠れているようだ。
登与助は正面に座る鈴蘭をまじまじと見つめた。その眼差しに、鈴蘭は不思議そうに首を傾げる。
「わたしの顔に何かついてる?」
「……鈴蘭。大丈夫か、具合でも悪いのか」
「えっ」
丸い頬に手を添えてやると、鈴蘭は驚いたように瞬きびくりと肩を震わせた。初めて触れたその頬は体温が高く、燃えるように熱かった。登与助は確信した。間違いない、この症状は。
「風邪だな。こいつは早いとこ医者に診せた方がいい」
「あ、あの、登与助さん?」
「全く、何で誰にも言わなかったんだ?いいから此処で待ってろ」
「ねえちょっと、待って。違うよ」
「駄目だ。さっきの妓夫を呼んでくるから大人しく……」
「登与助さん!わたしは大丈夫だよ!」
片膝を突き立ち上がりかけた登与助の裾を、鈴蘭は慌てて掴んだ。登与助が視線を寄越すと、その顔は酷く困惑しているようだった。浅い呼吸を繰り返し、額には薄っすらと汗が滲んでいる。どう見ても健康状態には見えない。登与助は嗜めるように声をかけた。
「お前随分と顔が赤いぞ。息だって荒いし、これが重病だったらどうすんだ」
「違うんだ。その…わたし、えっと」
「ん?」
歯切れの悪い物言いに登与助が顔を顰めると、小さい鈴蘭はもっと小さくなって、恥ずかしげに俯いた。
「……さっきまで、お客様方のお相手をしていた、から」
瞬間、がつんと脳天を撃ち抜かれたかのような感覚に見舞われる。同時に、数秒前の自分が如何に無神経であったかを思い知らされ、登与助はその場で硬直してしまった。そういえばそうだ、今日は団体の貸し切りだと見世番の男が言っていたではないか。その忙しい時間の合間を縫ってこうして会いに来てくれたというのに、それを自分は察することもせず勘違いをした挙句、恥ずかしい思いをさせた。何と鈍くて愚かなのだろう。
自身の失態に黙り込んでしまった彼を見ててっきり動揺しているのだと解釈した鈴蘭は、掴んでいた裾を離した。乱れた首元の着物を直しながら、申し訳なさそうに呟く。
「ちゃんと水浴びはしてきたんだけど、今日は、あんまり近づかない方がいいかも」
「そんなこと俺が気にするわけないだろ」
割り込む勢いで登与助の口から飛び出た言葉は、鈴蘭を尚も驚かせた。登与助は傍らに敷かれた布団をぽんぽんと叩いてみせた。折角時間を作ってくれたのだから、これ以上失態は繰り返したくない。
「……悪かった。しんどいなら、ちょっと横になれ」
「えっ、でも……」
「気にするなって、俺とお前の仲だろ鈴蘭。楽な格好になっていいから」
自分の前では、重苦しい数の着物で着飾る必要はない。身体を差し出す必要もない。優しく促すと、鈴蘭は感極まったように言葉を飲み込み、こくんと頷きながら立ち上がった。
羽織っていた着物を数枚脱いでいる間に、登与助も腰を上げ布団へと移動した。わざとらしく大の字で寝転んでやると、軽装になった鈴蘭はくすりと笑みを零し、添い寝をした。
布団に身体を預けた途端、一気に疲労が押し寄せたようで、控えめではあるがかなり長い溜息が部屋に響く。疲れた姿など今まで一度たりとも見せてこなかった鈴蘭のそんな様子に、登与助の胸はどうしようもなくざわついた。先程の口ぶりからすると、どうやら今夜も大勢の客を相手にしなければならなかったらしい。相当身体に堪えているようだ。
「……無理させられたのか?」
小声で語りかけると鈴蘭は暫し沈黙したのち、苦笑を浮かべながら「ちょっとだけね」と答えた。こんな時にまで、無理に笑わなくていいのに。
喉元まで出かかった言葉は胸にしまい、登与助は鈴蘭の頭を優しく撫でた。少しくすぐったそうに、されども幸せそうにその手の温もりを享受する鈴蘭を見ると、まるで血の繋がった妹を愛でているような錯覚に陥り、愛おしい気持ちが胸一杯に溢れる。何と安らかな時間だ。部屋を手配してくれた彼らに感謝しなくては。
「なあ、あのぽっちゃりした妓夫の彼……何て名前だ?」
「熊郎だよ。いつもからかってくるけど、本当は優しくて良い人なんだ」
「そうみたいだな」
不器用な優しさを持つ彼に、どうやら鈴蘭は相当可愛がられているようだ。後日きちんと礼をしようと考えたその時、ふと登与助は喉の渇きを覚えた。そういえば仕事を終えてから此処に訪れるまで、一滴も水を飲んでいない。確か茶箪笥があったな、と何気なく視線を巡らせると、いち早く察した鈴蘭が大慌てで身体を起こした。
「ごめんなさいっ、わたしまだお茶も出してなかった……!」
「いやいや気にするな。そうだ、たまには俺が淹れようか?」
「そんなの絶対に駄目!!!」
青ざめた顔の鈴蘭が部屋の隅へ置かれた茶箪笥へ駆け寄ろうとした瞬間、その身体は大きくぐらりと揺れた。寝転んだままの登与助に目がけて。
「うわぁっ!」
「……!」
どさっ。音を立てて、登与助の上に倒れ込む鈴蘭。咄嗟に両手を広げ抱きとめたおかげでその衝撃は緩和されたが、受けた側の登与助は突然の圧力に「ぐえっ」と蛙のような声を漏らした。急に全体重を腹の上に掛けられると、相手が子どもであっても負荷は大きい。腕の中で唖然としていた鈴蘭は、次第に状況を把握し大きな悲鳴を上げた。
「ごめんなさい!あ、足が縺れちゃって……痛っ!」
「ど、どうした鈴蘭?どこが痛むんだ?」
痛々しい声に、登与助は自分の腹の痛みなどそっちのけで鈴蘭の様子を伺った。首にしがみついた鈴蘭の表情は見えないが、身体の震えは充分に伝わる。しかし鈴蘭はきゅっと口を噤み、問いには答えなかった。どうやら"下半身"に力が入らないようだ。登与助はそれとなく察し、なるべく振動を起こさないよう細心の注意を払いながら、落ち着くまでそっと背中をさすってやる。頭に刺した簪が登与助の顔をちくちくと刺激するが、そんなことは気にならなかった。
鈴蘭はずっと痛みに耐えていたらしく、苦しそうなその呼吸はなかなか収まらない。耳元にかかる吐息が妙に艶めかしく、ほんの少しだけ心臓が高鳴ってしまった。が、すぐに不謹慎だと言い聞かせ、登与助は必死に意識を他へと集中させた。薄暗く照らされた天井を見上げ、木目の皺を意味もなく数えている内に、鈴蘭が小さく口を開いた。
「ごめんね、登与助さん。折角来てくれたのに、わたし……」
「謝るなって。無理に押しかけた俺の方が悪い」
「登与助さんは悪くないよ」
首に回された手に、ぎゅっと力が込められた。落ち着かせた筈の心臓が、何故かまたもや早鐘を打つ。
「会えて嬉しい、凄く」
掠れた声で、あまりにも切なげにそう呟くものだから、登与助は沸き起こる愛おしさのあまりその小さな身体を抱きしめた。瞬間、鈴蘭が「んっ」とくぐもった声を上げる。ものの一瞬で我に返った登与助は慌てて力を緩めた。
「悪い!まだ痛むよな」
「そ、そうじゃなくて、腰……ッ」
「腰?」
登与助は左手を背中に、右手を腰に手を添える形で鈴蘭を抱きしめている。腰が痛むのだろうか。労わるように右手で撫でてやると、鈴蘭の背筋がぴんと仰け反った。
「あッ!ちが、う、触っちゃ駄目……!」
「えっええっ?」
その反応と妙に甘ったるい声に、状況が掴めず間抜け面で固まる登与助。鈴蘭は顔を真っ赤に染め、息も絶え絶えに声を絞り出した。
「いま、その、敏感に、なってるから……っ」
ようやく合点がいく。両手を素早く宙に浮かせ、登与助は心の中で念仏を唱えながら、荒ぶる心を鎮めようと真顔で試みた。密着した身体の熱。しっとりとした柔らかな肌。聞いたことのない嬌声。自分に幼色の気は無い筈なのに、腕の中のあどけない少女が見せるその色気は、想像を絶する破壊力を秘めていた。
全身に伝わる心地の良い重みが、情事を連想させる。久しく女を抱いておらずまともに処理もしてこなかった身には、その刺激はあまりにも強すぎた。しかし鈴蘭が懇願するので、登与助はまともに身体を動かせない。逃れられない状況によってもたらされた欲情に唆され、何度も手を伸ばしては、懸命に耐えた。今にも爆発しそうな性欲は、大胆に自身の下半身へと反映されている。昂ぶりに気付かれないことを祈りながら、登与助はひたすらに下唇を噛みながら時が過ぎるのを待った。
ようやく落ち着いた鈴蘭が身体を起こし登与助の横へ転がった頃には、登与助も軽い息切れを起こしていた。そんな彼の状態など露知らず、鈴蘭は目を伏せ横向きになり、布団に顔を埋めている。心配そうに身守る登与助の視線に勘づいていながらも、埋めたその顔は羞恥の色に染まっており、静寂に包まれた部屋の中で、暫くの間押し黙っていた。
「ごめんね。気持ち悪いって思うよね、こんな、はしたないわたしのことなんて…」
やがて鈴蘭が、そっと瞳を開く。眉を下げ、悲壮感に包まれた笑顔。この物憂げな表情は何度も目にしてきた。
「……あのなあ。そんな風に思ってたら、俺は此処には来てないぞ」
「本当に?」
「本当だって。俺が嘘吐いたことあるか?」
強張っていた面持ちが僅かに綻んだのを見て、登与助は再び手を伸ばし、慈しみを込めた手つきでこめかみを撫でた。誰が友達を気持ち悪いなどと思うものか。そう語りかけるように滲んだ汗を親指で拭うと、その手にゆっくりと鈴蘭の小さな手が重ねられる。そのまま鈴蘭は、ぽつりぽつりと話し始めた。
「この前の宴会でね、一言だけど、初めて褒めてもらえたんだ」
「おっ、よかったじゃないか。流石だな鈴蘭」
「それでね、その旦那様から、とっても美味しいかりんとうを頂いたから、お礼に登与助さんにも食べてもらいたかったんだけど。ごめんね、お姉様方に盗まれちゃった」
「……俺んちの近所に、行きつけの菓子屋があるんだ。今度買ってきてやるよ。その旦那様のより何千倍も美味いやつをな」
多分ほっぺが落ちちまうぞ、と白い頬を柔らかく摘まむ。途端に楽しそうな笑い声が響き、登与助もつられて喉で笑う。
和やかな時が流れ、その心地良さに次第に鈴蘭はうっとりと微睡んだ。重そうな瞼が下がりかけている。朝から働き詰めた少女の身体に限界が訪れているのを感じ取った登与助は、空いている手で掛け布団を手繰り寄せ、ふわりとその身体に掛けてやった。すると、重ねられた方の手がぎゅっと握り締められる。今にも眠りに落ちそうな鈴蘭は、登与助の大きな手を握りながら、幸せそうに微笑んでいた。
「登与助さん」
「どうした?」
「わたし、登与助のこと、大好き」
動揺を悟られないよう、登与助も笑みを返す。
「俺もお前さんが好きだよ」
「えへへ」
「ほら、もう休め。俺が傍にいるから」
「んん、嫌だ、寝たくない……」
唇を突き出し、顰めっ面でぐずる鈴蘭は、まるで赤子のようだ。眠気のあまり呂律が回っていない様子が歯軋りするほど可愛らしくて。登与助は喉で笑いながら、捲れた布団を直してやった。
「登与助さんと三味線、弾きたいのに……」
「起きてからすりゃあいい」
「ねえ、教えてくれた曲、わたしもう弾けるんだよ。たくさん練習した、から……」
「分かった分かった」
甘えたような声は次第に小さく消えていき、代わりにすうすうと規則正しい寝息が聞こえ始める。
登与助は、初めて見るそのあどけない寝顔を、静かに見守っていた。ふと目線をずらすと、はだけた胸元が目に飛び込む。そこには鬱血した赤黒い痕が点々と残っていた。よく観察してみれば頬には畳に擦れたような火傷、細い手首には薄っすらと縄の痕が見られる。
何とも惨たらしい有様に、登与助の中でどす黒い感情がぐつぐつと煮え立った。無垢で清らかな心を持つこの子を、傷つけてもいい権利など一体この世のどこにある。憎悪と嫉妬の入り混じった感情が、怒りとなって逆巻く炎のように登与助の胸を焦がした。自分ならば、こんな手荒な扱いは絶対にしない。愛情を込め、身体の一つ一つを余すことなく大切に愛してみせる。ああ、今すぐにでもその肌に唇をつけ、味わってみたい。
────全身を駆け巡る熱い衝動に気付いた瞬間、登与助は驚いて目を見開いた。何故自分は、こんなにも熱くこの子を求めているのだろう。数刻前までは妹のような親しみを感じていた筈なのに、今はまるで違う思いを抱いている。大好きだと言われた瞬間、気持ちが舞い上がった。と同時にそんな自分が信じられなかった。
喜びを感じたのは、一瞬でもそれを"愛の告白"だと勘違いしてしまったからだ。鈴蘭は純粋な気持ちで、自分を好いてくれているというのに。これでは、この妓楼に足を運ぶ悪趣味な男共と同等ではないか。
「……ッ、どうしちまったんだ俺は」
蓄積した疲労のせいで、頭がやられているのかもしれない。下世話な感情を抱いてしまったことは綺麗さっぱり忘れよう。登与助はそっと心に蓋をした。鈴蘭は友達だ、そう何度も胸の内で言い聞かせながら。
ふいに鈴蘭の口から、むにゃむにゃと聞き取れない言葉が零れた。何とも間抜けな声色に、登与助は堪らず声を押し殺して笑ってしまった。普段は登与助が先に眠ってしまうし、朝も必ず鈴蘭のほうが先に起きるので、こうして寝顔や寝言を目の当たりにできるのは至極新鮮であった。彼女は相当疲れているようだから、恐らく朝まで目覚めないだろう。それでも登与助は構わない。鈴蘭の身が何よりも大切なのだから。
こっそりと懐に忍ばせておいた贈り物は、明日の朝一番にあの妓夫に預けることにした。反応を拝めないのは少しばかり残念だが、次に会う時の楽しみにもなる。登与助は可愛い鈴蘭の喜ぶ顔を想像しながら、瞳を閉じた。喉につかえたようなわだかまりは未だに残っているが、疲れ切った身体と頭ではもう何も考えられず、隣で気持ち良さそうに眠る少女同様、登与助も深い眠りへと落ちていった。
朝を知らせる鐘が鳴り終わったのと同時に、夢の中をふわふわと漂っていた意識が戻る。もう起きる時間か、久々に熟睡したなあ。と寝惚け眼で天井を見上げていた鈴蘭だが、ほどなくして凄まじい速度で身体を起こした。
慌てて横を見ると、布団はもぬけの殻だ。部屋の隅々を見渡しても、同衾していた筈の彼はどこにもいない。
「……!」
寝坊、の二文字が脳裏を過ぎる。瞬く間に立ち上がり、襖を開いたその時。
「おっと!びっくりした、ようやくお目覚めか」
丁度襖の向こう側に、一番親しい妓夫が立っていた。彼は眠そうに目を擦り、何とも他人事な言い草だ。鈴蘭は掴みかかる勢いで尋ねる。
「熊郎!わたしのお客様はどこ!?」
「とっくのとうにお帰りあそばされたよ。お前、馬鹿やっちまったな」
衝撃のあまり、鈴蘭は絶句しその場に立ち竦んだ。おめおめと寝過ごしただけでなく客の見送りすらもこなせなかったとは、遊女として一番してはいけない失態だ。これが遣手に知られたらお叱りだけでなく確実に減給ものだろう。だが鈴蘭にとっては罰などどうでもよく、登与助に無礼を働いてしまった事実が何よりも大きな精神的打撃となった。
言葉を失い顔面蒼白になった鈴蘭を見て、熊郎は意地悪く鼻で笑った。
「誰かにばれる前に起こしてやってくれ、って言いつけ貰ってきたんだぞ。ほんと優しい旦那で命拾いしたな、お前」
「えっ。そ、そうなんだ……返す言葉もないや」
「あとこれ、旦那から預かりもんだ。お前にやるってさ」
登与助の心遣いを噛み締める間も与えず、熊郎はとある細長い木箱を強引に鈴蘭へと手渡した。簡素な作りの箱で、別段思い当たる節などない。
不思議そうに眺める鈴蘭にそれ以上何も言及することなく、熊郎はくるりと踵を返した。ふと昨晩の出来事を思い出し、去っていく背中に向かって鈴蘭は声を張り上げた。
「熊郎!水仙姉さんに話してくれてありがとう!」
店の前で門前払いを食らっていたらしい登与助を見て、咄嗟に姉貴分へ掛け合ったのは熊郎だ。他の遊女にばれないようこっそりと鈴蘭を呼び出し、朝まで部屋にいさせてくれるよう手回ししたのも、勿論熊郎だった。
「礼なら水仙姉さんに言えよ。お前に会う為に倍の揚げ代を払った、粋な旦那にもな」
照れ隠しなのか、前を向いたままぶっきらぼうに手を振る熊郎を見送り、鈴蘭は再び手元の木箱へと視線を移した。
こんな贈り物を用意していたなんて、そのような素振りは一度も見せなかったのに。いや、もしかしたら自分が起きてから渡そうと思っていたのかもしれない。高い揚げ代を支払わせてしまったことも申し訳なくて仕方がなかった。やりきれない罪悪感に鼻の奥をつんと痛ませながら、鈴蘭は箱を開いてみた。赤茶の瞳に、煌びやかな光が映る。
そこには、一本の簪が仕舞われていた。焦げ茶色の木軸の先端を彩るのは、硝子細工で作られた薄紅色の桜。その無数の花びらから、連なった真珠が雨露のようにいくつも垂れている。まるで本物の桜の枝にも見える精巧な作りに、鈴蘭はただ感嘆の息を漏らした。
とても美しい簪だ。他の誰でもない、登与助さんが、これをわたしに贈ってくれたのだ。押し寄せる歓喜に胸の奥がじんと痺れた。鈴蘭はその場に崩れ落ちてしまいそうになるのを何とか堪え、覚束ない足取りで部屋に戻り、鏡台の前に座り込んだ。震える手で簪を手に取り、そっとこめかみに挿してみる。春にしか出会えない大好きな桜が、華々しくそこに咲いていた。甘く懐かしい花の香りが鼻孔をくすぐったような錯覚に陥り、心が大きく波打つ。同時に、登与助の笑顔が脳裏に浮かんだ。
どくんどくんと激しく高鳴り始めた鼓動は、一向に治まる気配がない。鈴蘭は暫くの間、鏡に映った自分の姿を見つめていた。
頬の横で揺れている真珠によく似た涙が、ぽろりと一粒零れ落ちるまで。

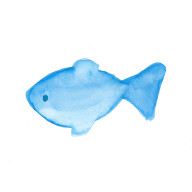














編集部コメント
主人公は鈍感で口下手ではあるものの『コミュ障』というほどではないので、キャラの作り込みに関しては一考の余地があるものの、楽曲テーマ、オーディオドラマ前提、登場人物の数などの制約が多いコンテストにおいて、条件内できちんと可愛らしくまとまっているお話でした!<br />転校生、幼馴染、親友といった王道ポジションのキャラたちがストーリーの中でそれぞれの役割を果たし、ハッピーな読後感に仕上がっています。