「なに。殺された、だと……?」
外から囁かれた内容に才谷は目を剥き、駕籠の引き戸を勢い良く開けた。が、正面に立ちはだかっていた従者に、飛び出そうとするのを慌てて手で制される。
外では先ほどから降り始めた雨が、だんだんと強まってきた頃だった。
「旦那様、お顔を出しては危険です!未だ暗殺者が近くを彷徨いておるやもしれませぬ。今夜のところは一先ず引き返しましょう」
「……うむ」
酒宴に向かう最中、俄かに街の人々が賑わい始め、何事かと従者に探らせた結果がこれだった。まさか、かの商談相手が暗殺されるとは。予想外の出来事に才谷は珍しく頭を抱えた。彼とは二度ほど顔を合わせたことがあるが温和で人当たりも良く、恨みを買う程大きく目立つような商売人でもなかった筈なのに。商談を持ち掛けられた際は、相手の功績や手口や人脈などを念入りに調査した上で承諾するようにしている。彼に関しては以前あの胡蝶に調べさせていたということもあり、才谷のほうではすっかり油断しきっていた。今宵自分がその場に居合わせていたなら、きっと巻き添えを食らっていたに違いない。
とりあえずは彼らからの報せを待とうと思い立ち、才谷が戸を閉めようとしたその時。にゃあ、と聞き馴染みのある声が耳に届いた。
「何だぁ?この薄っ汚い猫は。こら、あっちへ行け」
従者の放った言葉に、才谷はぴくりと反応する。即座に外を見やると、駕籠の前に濡れそぼった一匹の黒猫が息を切らしながら佇んでいた。見知った顔だが、才谷はその様子に思わず声を上ずらせた。
「お前……その片耳はどうした?千切れているじゃないか」
左耳が生えていたであろう箇所からは血が噴き出し、美しかった毛並みは土埃に汚れ見る影もなく、同情してしまう程に痛ましい有様だ。胡蝶の座敷の外でこの黒猫と出会うのは初めてである。野良猫同士で喧嘩でもしたのだろうか。しかしこの高慢ちきな黒猫は自分に毛程も懐いていない。助けを求めてくるなど、あり得るのだろうか?
駕籠から身を乗り出した才谷が目を凝らしてみると、どこかその傷口に引っかかりを覚えた。よくよく見れば、その傷の断面はあまりに綺麗過ぎた。左耳は千切れたのではなく、何者かに根元から切られたようだ。まるで、鋭利な刃物で刎ね落とされたかのように。
思わず差し伸べた手は、猫が踵を返したせいで呆気なく空を切った。怪我を負っているにも関わらず軽い足取りでその場から離れたと思いきや、猫は振り返りこちらをじっと見つめる。犬をこよなく愛でる才谷にとって猫の感情は読めないが、その瞳に強い意志が宿っている事には容易に勘づいた。何やらただならぬ雰囲気ではないか。同情を抱いていた胸の中で、ほんの少しの好奇心が顔を覗かせる。
「あの猫に着いて行きなさい」
怪訝な顔つきの従者達を促し、才谷は手負いの猫の背をただひたすらに追わせた。
降りしきる雨が、一行の進む先を霞がからせている。猫が道を駆ける度に鮮やかな血が地面に滴り、後から雨で滲んで歪な模様を作った。気丈に歩くその足はよく見るとふらふら揺れているようで、耳の傷以外にも痛めている箇所があるらしいと才谷は察した。膝元に乗せてやってもいいが、きっとそれは頑なに拒まれるだろう。そう判断し、敢えてこちらからは声をかけなかった。
一行は連れられるままに、夜の道を練り歩いた。満身創痍な猫がようやく歩みを止めたのは、とある一本の細い路地前だった。がらくたやくず紙がそこかしこに散らかり、人の気配など微塵も感じられない寂れた場所。怪しさに息を飲む従者達などそっちのけで、才谷は駕籠を入口に留まらせ悠々と立ち上がった。従者の内の一人が尚も用心深い面持ちで耳打ちする。
「奥に進むおつもりですか、旦那様。もしも巧妙な罠だとしたら……」
「私の刀を此処へ」
手渡された刀を腰に差し、才谷は路地の奥へと消えた猫を追う為、降りしきる雨をおし行灯片手にずかずかと進み始めた。従者達も慌てて後ろに続く。
果たしてこの先に何が待ち受けているのだろう。瀕死状態の猫に導かれる状況に対して、不謹慎ながらも、才谷は密かに心を躍らせていた。玩具を探し当てた少年のように目を輝かせて。
しかしその高揚感は瞬時に収まることとなる。雨に混じって生々しい血の匂いが彼の鼻をついたからだ。その匂いは背後の者達にも伝わり、一人が恭しく主人の前へと歩み出た。いつ何時襲われても主を守れるよう抜刀の構えをしながら、一行は道を歩き進めた。
ふいに、才谷の履物に硬い何かが当たる。立ち止まり拾ってみると、それは割れた手裏剣の欠片であった。目にした瞬間、とある可能性が脳内を過ぎった。行灯を上に掲げ目を細めてみても、まだ先の景色は見えそうにない。才谷は即座に従者を追い抜かし、背後からの声を無視して足早に進んだ。鼻孔を刺激する嫌な匂いは更に強くなっていく。
行灯の光が道の先を照らし、才谷の視界にとある光景が飛び込んできた。それは血の海に横たわる小柄な人物と、その周りをうろうろと彷徨っている黒猫。才谷は無意識の内に名を呼びながら駆け寄った。
しゃがんで傷の状態を見ると、どくどくと出血している腹部には刀が深々と刺さっていた。無理に抜いては損傷が激しくなりそうだ。才谷は自身の腰の帯を解き、ボロボロになった胡蝶の腹に巻きつけ固く固定してやった。どれほどの時間ここに放置されていたのだろう、血を失い、雨に濡れた身体はすっかり冷え切っている。迅速に処置を施す途中で仰向けになった胡蝶の顔は青白く、才谷は思わず息を呑んだ。しかし口元に手を翳してみると僅かに呼吸が伝わったので、そっと安堵した。
帯を結びながら、傍らの亡骸へと視線を移す。刀により額を奥深く刺された男は、歪んだ表情のまま死に絶えていた。危うく相討ちになるところだったらしい。胡蝶ほどの殺しの達人が、何故このような事態に。
脳内を渦巻く不審の念は、耳に届いた小さな呻き声によって掻き消された。
「う……」
「大丈夫か、胡蝶。しっかりしなさい。すぐ医者に診せるからな」
「……だ、誰か、たすけて」
「助けてやるから喋るんじゃない。傷に障るぞ」
多量出血により朦朧とした口ぶりと表情は、今にも命の灯火が消えかけていることを示唆していた。ばたばたと駆けつけた従者達に、才谷は医者を手配するよう手早く指示を投げた。胡蝶を慎重に抱き抱えようとしたその時、弱々しいその手が才谷の腕を掴む。焦点の定まっていない瞳が、おもむろに自身を見上げていた。
「あ、あの子は、どこ?ねえ、おしえて」
「あの子……もしや、黒猫のことか?」
「たすけて、あげて…僕を、守ろうとして、大怪我を……ッ」
悪夢にうなされているかのような譫言を繰り返しながら、胡蝶はひたすらに懇願した。胡蝶を守ろうとしたというその黒猫は、今は才谷の横でぐったりと横たわっている。友人の危機を報せるという大役を果たし、もう心残りはないといった面持ちで胡蝶を静かに見つめていた。
才谷は、ようやく一連の流れを読んだ。
「おねがい。たったひとりの、僕のともだちなんだ。たすけてあげて、ねえ……」
縋りついた腕に力が込められたのと同時に、青白い頬に涙の筋が伝う。顔に張りついた砂利が、その涙によってぼろぼろと落ちた。そして潤んだ瞳を宙に彷徨わせながら、胡蝶は引き攣った声で小さく呟いた。
「───もうひとりぼっちに、なりたくない」
絞り出した言葉と同時に、胡蝶は才谷の身体に全体重をかけながらそっと瞳を閉じた。
気を失った忍の濡れた睫毛を暫し見つめたのち、才谷は静かにその身体を抱き上げた。高価な着物の肩が雨に濡れようと、胡蝶の真っ赤な血に染まろうと、気に留める素振りも見せない。男の亡骸の処理と武器の回収を言いつけた従者に向かって、才谷はもう一つ命を下した。
「私の座敷に、腕利きの獣医師を呼べ」
そよそよと涼しい風が頬を撫で、朝を知らせる小鳥のさえずりが耳をくすぐる。それに伴い霞みががった視界がゆっくりと晴れ、一番先に目に飛び込んだのは見慣れない天井。
とある一室にて柔らかな布団に寝かされているのだと察知した瞬間、襲い来る鈍痛に胡蝶は顔を顰めた。思わず腹を手で押さえると、刺された部分に包帯が巻かれているらしいことが感触で伝わる。視線を下げれば、自分が薄水色の着物を纏っていることにも気づいた。胡蝶は痛みに顔を歪ませながら、疑問符を浮かべる。こんな色合いの着物は持っていない筈なのに。
その布擦れの音に、傍らで書物を読み耽っていた人物が顔を上げた。
「やあ、おはよう胡蝶」
「さっ才谷……?」
「こら安静にしていなさい。手術を施してから、君は七日も魘されていたのだよ」
「……此処は一体」
「私の屋敷だ。暫くの内は我が家で療養させることになったので、君の荷物も取り寄せておいた。心配せずとも、楼主には全て話を通しているよ」
手術、療養、荷物…。主の口から出るのはわけの分からぬ単語ばかり。胡蝶は状況が一切把握できないまま、一先ず彼が指差した部屋の奥を見てみる。
そこには胡蝶の座敷に仕舞っていた愛用の化粧箱や茶箪笥や着物の数々、それと忍の武器一式が置かれていた。ご丁寧にあの大きな屏風まで。
胡蝶は視線を戻し、才谷を穴が開く勢いで見つめた。当の本人は再び手元の書物を優雅に捲っている。
「……私を、助けてくれたの。どうやって?」
「そこの黒い毛玉が導いてくれたおかげだ」
目も合わさず、才谷は顎で指した。見ると胡蝶の傍らに置かれた座布団の上で、頭に包帯を巻いた黒猫がすやすやと寝息を立てている。ああ…よかった生きていた。君が彼を呼んでくれたのか、そんな傷ついた身体で。安堵と愛おしさがこみ上げ、胡蝶は友人の頭をそっと撫でた。毛玉呼ばわりはすこぶる気に食わないが、生憎それを諫められる程の活力はない。
その間に才谷は急須を傾け、白湯入りの湯呑を手に胡蝶の布団へと近づいた。胡蝶は大人しく彼の腕に支えられながら上体を起こし、湯呑に口をつけた。眠り続けていたせいでからからに乾いた喉に、温かな湯が心地良く染み渡る。時間をかけながらも全て飲み干した様子を見届け、主は再度布団へと寝かせながら問いかけた。
「君が相討ち寸前まで追い込まれたとは珍しいな。原因はそいつか?」
「違うよ。あの刺客は、かなりの手練れだった。この子が割って入ってくれなければ、殺されてたかもしれない……それに」
一息ついた胡蝶は横目で睨むも、すぐに視線を逸らした。
「…諸々貴方のせいにしたいところだけど、こうして迷惑をかけてるんじゃ様は無いね。こんな怪我も負ってしまったから……もう花魁は続けられないし」
あの戦いで腹部に大きな傷を負った。醜い花魁の身体など、誰も欲しがらない。傷が癒え復帰できたとしても、降格は目に見えている。収入だけでなくあの座敷まで失ってしまうのは、胡蝶にとってかなりの痛手だ。情報屋としての仕事場も消えてしまうのだから。身売りも情報屋も満足に営めない自分には、いよいよ殺しの道しか残っていない。その再開も───、一体いつになることやら。
意気消沈した胡蝶は目を瞑り項垂れた。才谷はそれをちらりと一瞥したのち、閉じた書物を脇に置き別の話題を持ちかけた。
「それにしても、驚異の幸運と回復力だ。あと少しでも刃がずれていれば、命の保証はなかったらしい。加えて出血量が多く、助かる見込みは五分五分だったとか。君の生に対する執念は凄まじいな」
「当たり前でしょ、死んでなんかいられない。鈴蘭が私の助けを待ってるんだ。それに……貴方を殺すのはこの私なんだから」
「ははは。君の生きる糧になれたのなら、重畳の至りだ」
腹に致命傷を負っていても、いつもの憎まれ口はとどまるところを知らないようだと才谷は高らかな笑い声を上げた。その忌々しい態度に、胡蝶はもううんざりといった顔で睨みを効かせる。
「そう拗ねるな。短い時とはいえ、同じ屋根の下で暮らす間柄じゃないか」
「きっ……何で私が此処で休まなきゃならないの」
「主人に向かって今なんと言いかけたんだ?まったく。その傷だと遊郭に居てはかえって怪しまれるだろう。何はともあれ、私の命を守ってくれたことに深く感謝しているんだぞ。恩はきっちり返す主義でね」
そう、と一言だけ返し、胡蝶は閉じられた障子越しに射し込む朝の光を見つめた。普段ならこの時間にはとっくのとうに起床し、身支度を整えているころだ。そろそろ朝餉の支度が始まる頃合いだろうか。この座敷は物音一つ聞こえず、酷く静かだった。傷に響かないよう一番奥の部屋を用意してくれたのだろう。
それに、彼の背後にこっそり団扇が隠されていることも胡蝶は見逃していない。意識を取り戻す直前まで感じていたそよ風は、彼によってもたらされたものだ。彼は片時も離れず、いつでも飲めるよう常に新しい急須を用意し、目が覚めるまで団扇で扇ぎ続けてくれたらしい。…そのような雑事は従者に任せればよいものを。
彼なりの不器用な恩返しを素直に受け取れず、尚も黙り続けていると、妙に神妙な面持ちをした才谷が静かに口を開いた。
「……一つ尋ねてもいいか、胡蝶。もしも妹と再会し安寧の生活を取り戻せたら、その後は何をするつもりだ。自分らを捨てた両親に報復でもするのか?」
その問いに、胡蝶は喉を引き攣らせた。お前に関係ないだろうと口を噤みかけたが、才谷が向けてくる眼差しは今まで見たことのない程に至極真面目であった。胡蝶は───思わずたじろぐ。彼の瞳は、普段とはまるで正反対である廉潔な色を強く映していたからだ。
やがてその勢いに押し負け、降参した胡蝶はゆっくりと紡ぎ始めた。生涯、誰にも語るつもりなどなかった、己の過去を。
「捨てられてなんかいない。私達の両親は殺されたんだ」
胡蝶と鈴蘭は、とある忍家業の家に生まれた姉妹だった。人里離れた地、鬱蒼と覆い茂った竹林に囲まれた家にえ、物心つく前から人を殺すための修行や鍛錬に明け暮れる日々。代々受け継がれていたその家業故に、忍としての訓練は過酷で厳しいものであった。妹の鈴蘭は何度も身体を壊し、修行を泣いて嫌がった。
「すずは、器量が悪くてさ。私よりも馬鹿で、弱くて、甘々で…どうしようもない妹だったんだ。虫さえまともに殺せないんだよ、笑っちゃうよね。でも、そんな優しいすずが私は大好きだった」
鈴蘭は弱さゆえに心優しく、感受性の豊かな子だった。畑を荒らす野良犬の子を始末しろと父親に命じられた時には、それはもう凄まじいくらいに泣き叫び、暴れて、全力で拒否した。そのあまりの剣幕に、人一倍厳しい父も怯んで「もういい」と撤回する事態だった。
そして、きっかけは定かではないが、鈴蘭は大の音楽好きであった。父の三味線や琴を引っ張り出してきてはよく、修行を抜け出し演奏し楽しんでいた。鈴蘭は人を殺すことにおいては何の役にも立たない、音楽を好んだのだ。
いつまでも幼い鈴蘭に両親はお手上げで、次第に忍への期待は全て才能ある胡蝶へと向き始めていった。
「すずとは逆で、私は優等生だったから。両親の期待には全部応えられたし、何より忍の仕事を誇りに思ってた」
姉の胡蝶は常に冷静沈着で、忍の仕事に関しては類い稀なる才能を秘めた少女だった。いち早く父に連れられ、幼いながらに任務を手伝った経験も多々ある。忍に向かない妹の教育も幾度となく任されたが、年が経つにつれ胡蝶はそれを無下に断り、逆に父に頼み込んだ。「鈴蘭に忍の仕事をさせないでくれ」と。
汚れを知らない無垢な妹に、血生臭い殺戮が蔓延るあの世界を見せたくないと考えるようになった。それに何よりも懸念していたのは。
「殺人を犯した者は、輪廻転生を逸れ地獄へと誘われる。耐え難い苦痛をその身に受けながら、永遠に罪を償うんだ。鈴蘭に、そんな重い業を背負わせたくなかった……父さん最後まで、頷いてくれなかったけどね」
いくら胡蝶が倍の働きをすると主張しても、一族の存続を何よりも優先する父の意思は固く、頑なに受け入れなかった。
そんな中、あの事件は起きた。
それはとある蒸し暑い夏の日。鈴蘭が六つになる頃だった。
どうしても行ってみたいと鈴蘭に強くせがまれ、胡蝶が両親に口添えし、その日は家族揃って隣町の神社で催された縁日へと赴いていた。初めて訪れた場所に姉妹は目を輝かせ、厳しかった両親も「たまにはこういう日があってもいいだろう」と二人のどんな我儘も快く聞き入れてくれた。
甘くて美味しい林檎飴を頬張り、父対姉妹で射的対決をした。面白可笑しいお面も買い与えてもらった姉妹は、どちらも年相応に笑っていた。珍しく両親の顔も緩んでおり、周りの誰がどう見ても、その様子は名高い忍の一家には見えなかっただろう。
物珍しさから人一倍興味を示した鈴蘭に、くるくる回るおもちゃの赤い風車を買い与えてから、一家は家路に着いた。
襲撃を受けたのは、その帰り道でのことだった。
「私たちは必死に応戦したけれど、如何せん手薄の時を狙われたから…。程無くして敵に捕らえられたよ」
現れた敵は、一族に私怨を抱いていた連中だった。多勢に無勢で押し負けた胡蝶たちは一人ずつ縄で縛り上げられ、輩は両親を好き勝手に嬲った。そして父母二人を我が家へと放り込み、幼い姉妹の目の前で火を放ったのである。
両親はとうとう、一度も命乞いをしなかった。苦しみから逃れる為に舌を噛み切るといった行為もせず、辱めと苦痛をその身に受けながら、忍としての定めを堂々と受け入れて死んでいったのだ。
ぼうぼうと燃え盛る炎の中、呻き声の一つも聞こえてこない我が家を、胡蝶は唇を噛み締めながら眺めていた。柔らかな肉がぷつりと切れ血の味が口内に広がろうとも、人肉と年季の入った木材の焦げる匂いが鼻をつこうとも、黒々と立ちのぼる煙が沁みようとも、決してそこから目を逸らさずに。その場には、地獄の業火が爆ぜる音と、おもちゃの風車が良く回る音、そして───鈴蘭の泣き叫ぶ声だけが、ただひたすらに響き渡っていた。
やがて全てが黒い炭となって無残に燃え尽きた頃、こんどは姉妹に刃を突きつけられた。しかし銭を求めていた輩の提案により、二人はそれぞれ遠い地に売り飛ばされることとなったのだ。
胡蝶が売り飛ばされたのは、広い都の花街で一番と名高い評判の遊郭。その見目の麗しさと器用さと度胸を買われ、胡蝶は早々に禿として当時の花魁の世話をさせられた。
人を殺す術しか知らない十一の少女が、ゆくゆくは名家の武将や天下の台所を回す大豪商と相手をしていかなくてはならない。まずは"教養"が必要だった。古典や漢詩に始まる文学。茶道に華道。舞踊、琴に三味線。果ては和歌などといった多岐にわたる芸事。世情の話。
一つも無礼のない完璧な作法、美しい仕草。床で男を喜ばせる在り方…それら一切を仕込まれた胡蝶は、驚く程の速度でそれを吸収し、遊郭という世界で生き抜くための腕を磨いていった。その並々ならぬ努力には誰もが目を見張り、いざ遊女として客を取るようになってからは、卓越した美貌と長けた手練手管でたちまち人気を呼んだ。指名は毎晩後を絶たず、楼主に気に入られた胡蝶は十五の齢を迎える頃に花魁の地位を与えられた。
胡蝶がようやく忍の家の生まれであることを楼主に明かし、取引を交わしたのはその時分である。情報屋、および忍としての殺しの仕事を兼任させてもらう代わりに、報酬の半分を納めるといった胡蝶の申し出は、守銭奴の楼主にとって充分過ぎる程の旨味であった。
夜の街へ繰り出し様々な情報を掻き集め、別口で依頼が入れば忍としてその手を血で汚す日々。目まぐるしい生活の中で、求めるものはただ一つ、生き別れた姉妹鈴蘭の消息だ。
「私が愛しているのは鈴蘭だけだし、鈴蘭も私だけを愛している筈。どれだけ遠く離れていても、必ずあの子を見つけてみせると誓った。贅沢な暮らしじゃなくていい。二人で慎ましく、幸せに暮らす…それだけが、私の唯一無二の夢なんだ」
語られた過去は、まだ齢十七の少女が背負うにはあまりに重く壮絶であった。
聞き終えた才谷は、暫しの間黙り込む。冷静な振りをしていたが、その胸の内では静かな怒りが炎のように巻き上がり、才谷の心をじわじわと蝕んだ。同時に、自身の嫌な思い出も蘇った。絶えず響く竹刀の音。罵声、赦しを請う声。身体をまさぐる気色悪い手の感触。果てのない、飢え。
それらの古い記憶を振り払うようにして口から漏らした言葉は、胡蝶の主としてではなく、才谷一個人としての感情によるものだった。
「復讐してやりたいと思うか。両親を殺め、お前をこんな目に合わせている者達に」
もしお前が強く望むのならば、俺が代わりに彼奴らを見つけ出し、闇の彼方に葬り去ってやろう。ところが対する胡蝶の返答は、意外にも否定の言葉であった。
「思わないわ。だって人から恨みを買う生業だもの。報復されたなら、甘んじて受け入れるのが私たちの定めだ」
「……本当にそれで良いのか?その輩のせいで、お前たちは引き離されたのだろう?お前が身体を売る羽目になったのも、多大な借金と共に生活しているのも、そんな大怪我を負わされたのも、元を辿れば全て」
「自分の業が招いたことだよ。そのくらい弁えてる」
天井を見上げながらあっけらかんと言い放つその姿は、先程語った過去など毛ほども気にしていないというようで、才谷はつい毒気を抜かれそうになった。
胡蝶は気に留めず続ける。
「命あるだけで儲けも同じ。殺されても可笑しくない状況でお情けを頂いたんだから、むしろ有り難いと思わなくっちゃ」
「いや、いいや、どうしたって分からないな。お前はこの世界において弱者ではないだろう?力があるなら振るえばいい。俺なら、自分を陥れた者には容赦なくやり返す。今までもそうやって生きてきた、それが彼奴らにとって当然の報いだからだ!」
才谷は憤慨したように吐き捨てる。そんな自分を如何にも愉快そうに横目で眺める胡蝶に気づき、才谷は思わず苛つきながら片眉を上げた。
「何を笑っている!?」
「貴方が自分を“俺"なんて言うところは、初めて見たものですから」
「……そろそろ休め。傷口が開いてしまうぞ」
「ねえ。そうやって生きてきた、ってどういうこと?貴方の過去は教えてくれないの?」
「治ったらな。いいから早く寝なさい」
苛々しつつも掛け布団を直すその手つきは丁寧で、胡蝶は含み笑いをしながら瞼を閉じた。
意外にも彼には人の血が通っているらしい。血も涙もない冷徹な人間とばかり思っていたが、少しはまともな一面もあるようだ。甲斐甲斐しい世話や、嫌っていた筈の猫を救ってくれたことや、己の過去に対する態度がそれを物語っている。
ならば余計に、こう言わずにはいられない。
「理解できなくて当然だよ。忍の私と大豪商の貴方とじゃ、何もかも違いすぎる」
結局は身分や育ってきた環境の違いだ。こんな忍の生き様など、誰にも分かってもらえないだろう。悟ったような口調の胡蝶に、才谷はほんの一瞬だけ渋ったが、ある一言だけ口にした。
「……前にも伝えたと思うがな、君と私の境遇は似ているんだよ」
「えっ?」
思わず目を開け、ぼそりと呟かれた言葉を聞き返しても、才谷は横を向き視線を合わせなかった。どうやらこれ以上言葉を交わす気はないらしい。
諦めた胡蝶が今一度布団の中に潜り込むと、傍らで眠っていた黒猫がもぞもぞと動き出し、呑気な顔をしながら起き上がった。笑顔を浮かべて撫でてやれば黒猫は嬉しそうに尻尾を立て擦り寄ろうとした───が、才谷の大きな手が黒猫を抱えたせいで、それは未遂に終わった。
「こら。病人に近づくんじゃないと、何度言ったら分かるんだ」
まるで母親のような台詞ではないか。抱え込まれた黒猫は心なしかぶすっとした表情にも見え、胡蝶は痛む腹を手で抑えながら朗らかな声を上げた。
笑い事じゃないぞ、と才谷が叱咤したとき、手中を掻い潜った猫が彼の膝上で丸まり始めた。叱られたのにも関わらず、猫は彼に身を預け、気持ち良さそうに寛いでいる。途端に石のように固まる才谷を見て、胡蝶は再び頬を緩ませた。あれ程までに嫌い合っていた二人が、いつの間にそんな仲に発展していたなんて。才谷の方は状況が掴めていないようだし、よく見るとその手には無数の引っ掻き傷が浮かんでいるようだが。
「……お前、散々言うことを聞かなかったくせに、今度は私に媚を売る気か。図々しい奴だ」
「犬派のお上りさんに教えてあげる。猫って自分に正直な生き物でね。嫌いな奴には絶対に近づかないんだよ」
怪訝な表情の彼に、胡蝶はくすくす笑いながらも、今度こそ休むべく瞼を閉じる。
ようやくしんとした静けさが訪れた頃、ふにゃあと間延びした猫の声が部屋に響いたことは、その場にいた二人の顔を見事なまでに綻ばせるには十分だった。
窓の外を吹き抜けた涼しげな風が、もうすぐやって来る夏の終わりを告げていた。

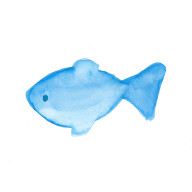
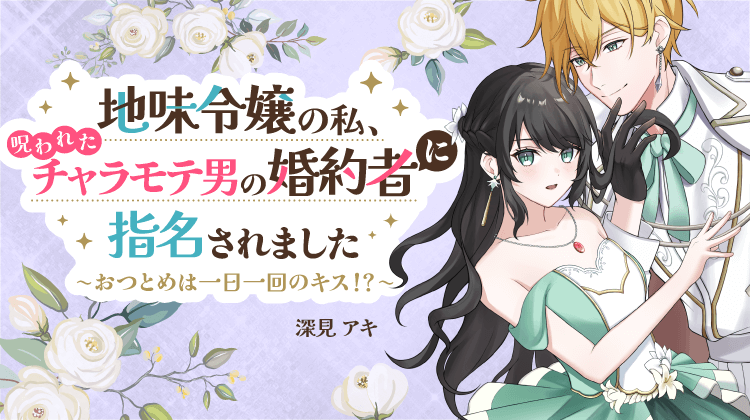










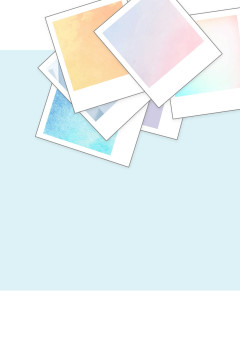


編集部コメント
引きこもりのおじさんと真面目な女子高生という組み合わせがユニーク。コンテストテーマである「タイムカプセル」が、世代の違う二人をつなぎ、物語を進めるアイテムとして存在感を発揮しています。<br />登場人物が自分の過去と向き合い、未来に向かって成長していく過程が丁寧な構成で描かれていました。