体育祭から3日が経ち、結局、1日では回復しなかった彼女は振替休日の次の日も休んでいた。
いつもは彼女が教室に一番乗りのようだが、今日は僕が最初に来た。
いや、誰でも本人が寝たら帰るだろ。
彼女が自分の席に座ろうとした所で、上靴を手にしていることに気づく。
彼女がさっと背に隠す。
そしていつものように笑った。
はぁ?
そろそろ僕も彼女のヘラヘラした態度に腹が立ってきた。
僕は近づき、彼女に背を向かせて、上靴を取り上げる。
確かに濡れていた。
そして、上靴の中には画鋲が何本かあった。
僕はそれを見て、止まってしまった。
分かってはいた。
彼女の頬にある痣、突如無くなる運動靴、そして画鋲入りの濡れた上靴。
…どれも、誰かの仕業である事は分かっていた。
けど、僕は甘く見ていたのかもしれない。
僕は上靴を黙って彼女に返すと、自分の席に戻った。
それから今日はどの授業も受ける気になれなくて、
先生にもタクミにもヒナタにも、そして彼女にも話しかけられたくなくて、
話しかけることも無かった。
休み時間もお昼も今日は一人でいた。
ホームルームが終わり、帰りの挨拶をしたのは覚えている。
が、いつの間にか僕はうつぶせの状態で寝てしまっていたらしい。
うっすら目を開ける。
教室にいるのは僕だけのようだ。
教室の明かりは付いており、扉も開けっ放しだ。
そろそろ帰ろうか、と考えた時だった。
数人の男子が階段からかなりの大声で喋っているのが耳に入る。
今は動きたくないな。
そう思い、再び目を閉じる。
でも、僕はすぐに目を開く事になる。
男子3人の声。あいつ、って多分僕だ。
は?
耳に入る言葉に、僕は苛立ちを覚え始めていた。
すると、いつも聞く人間の声真似が聞こえる。
あはははは、と大きな笑い声が教室に響く。
そうか、『頑張る』って、この事か。
男子Aが近づき、僕の顔を覗き込もうとした時だった。
僕の手が彼の胸ぐらを掴んだ。それと同時に、「うぉ、」と驚きの声が口から漏れていた。
・
・
・
口元が切れて血が滲んでいた。
消毒液が付いた綿を軽く傷に押し当てていくヒナタが、そう呟いた。
僕が派手に喧嘩していると聞いて、駆けつけてくれたようだ。
その言葉を聞いて、僕たちの間に沈黙が訪れた。
保健室には僕とヒナタ以外、誰も居ない。
僕が立ち上がる。
そして歩き始めようとした時、ヒナタが僕の裾をつかむ。
僕は黙って、椅子に戻った。
その様子を見て、裾から手を離したヒナタが口を開く。
僕の動きが止まる。
ヒナタが涙をうかべて話す。
そう言うと、僕は続けた。
僕には分かる。
彼女が好きなんじゃない。
ただ、守りたいだけなんだ。
以前、僕が守っていたというように。
僕は不器用だ。
だから、どんな風に彼女に頼んだのかは分からない。
けど、今は、今の" 僕 "なりにかけられる言葉はあるはず。
「うん、」と小さな声が聞こえたのを確認して、僕は保健室の扉を開けた。
そして走り出す。
寂しい保健室に声だけが響いた。
その声はとても、暖かいようで、悲しいものだった。








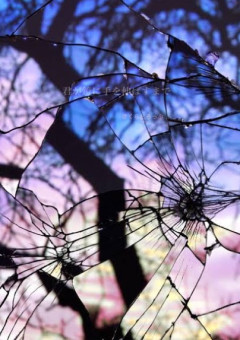




















編集部コメント
主人公は鈍感で口下手ではあるものの『コミュ障』というほどではないので、キャラの作り込みに関しては一考の余地があるものの、楽曲テーマ、オーディオドラマ前提、登場人物の数などの制約が多いコンテストにおいて、条件内できちんと可愛らしくまとまっているお話でした!<br />転校生、幼馴染、親友といった王道ポジションのキャラたちがストーリーの中でそれぞれの役割を果たし、ハッピーな読後感に仕上がっています。