「あっつい‥‥」
異常に湿気を含む薄暗い部屋の壁に掛けられている時計は、丁度七時を指していた。
じっとりと汗ばんだ肌に、首元に纏わりついた髪の毛を憂鬱気に払う。
何日降り続けば気が済むんだろうかと問いたくなる程の土砂降りの雨の音を背に、大きなお世話だって言いたくなるくらいきちんと掛けられてあった羽毛布団を勢いよく剥ぎ取った。
瞬間、隣で「んっ」と寝返りを打つあたしの―――‥‥。
「‥‥ねぇ、玲。またクーラー切ったでしょ?」
「‥‥‥んー?クーラーの風あんまり良くない」
「次、夜中にクーラー切ったら殺すから」
「‥‥‥昨日、のど痛いって、言ってたじゃん?もう平気?」
「のどは平気だけど脱水症状で死にそう」
まだ眠たいのか、玲の喋り口調はいつもよりワンテンポ遅い。馬鹿みたいな喋り方。
半分寝ながら「そっかそっか、悪化したら病院行こうね」と再び布団に包まりながら笑う彼を横目に流して洗面所へ向かう。
「‥‥はぁ」
それにしても梅雨の時期って本当嫌い。
鏡に映った自分の髪をギュッと一つにまとめて、着ていたTシャツと短パンをだらしなく脱いでシャワーを浴びる。
今ではもう、手慣れた行為。
玲と同棲を始めて、今日でちょうど一年か。
あたし達に記念日なんてものはない。
同棲一年記念日は愚か、付き合って三年になるけれど一回もそれらを祝った事はない。
まぁ最も、付き合っているのかすら怪しいあたしと玲の関係に祝うも何もない、かぁ。
グルリと目を回しながらシャワーの栓を捻った。
玲との出会いは本当に簡単なものだった。
三年前に大学を卒業して、云わば一流企業と言われる外資系の会社に入社した歓迎会での事。
あの時そこそこに酔いも回ったお偉い上司達の冷やかしがすべての原因だ。
◇◇◇
―――三年前。
『ほらほら~、松本さーん?キミ達の為の歓迎会だぞ?飲まないでどーする?』
『す、すみません佐藤常務。私、お酒あまり強くないので』
『じゃあ今日!今日強くなればいいじゃないか!な?』
こいつはアホか。
たぬきに眼鏡をかけたような佐藤"常務"は顔を真っ赤にしながらあたしの肩に腕を回す。
これ見よがしにと騒ぐ彼に、ここぞとばかり便乗して囃し立てる常務の部下たち。
まぁ、そうしないと生きていけないもんね。
笑いとも呼べない愛想笑いを続けていた、その時だった。
「‥‥佐藤常務、お疲れさまです。グラス空いてますね、お注ぎしますよ」
そう諦めていたところへ颯爽と現れたのが、玲だった。
『おぉ~!これはこれは!高野くんじゃないかー!』
『先日の案件、有難うございました』
『いやいや、優秀なキミの案件だ。受け入れるに決まってるだろう?』
常務のグラスにビールを上手く片手で注ぎながら、あたしの肩に掛かっていた手をそっと退けてくれた。
‥‥‥へぇ。
『おぉ、そうだ松本さん!キミ彼氏居ないんだって?この高野くんなんてどうだね?!』
『‥‥は?』
『じょ、常務?』
『この高野くんはな!26歳にして立派な経営コンサルタントなんだよ!将来有望!未来安定だな!な!』
『え、ちょっ、あの』
『もういい!私の相手はいいからホレ!二人で飲んできなさい!結婚式にはきちんと私の名前を出すんだぞ!』
いきなりとんでもない事を口にしたかと思えば、二人の背中を得意気な顔で押して別のテーブルへと移動させる眼鏡たぬき。
『高野くんはな、今年度の経営戦略の立案者なんだよスゴイだろう』なんて呂律の回っていない聞き取りにくい喋り方でまだあたしに"高野くんはな攻撃"をしてくる始末。
『‥‥‥』
これが知り合いの男なら迷わず手に持っている酒を頭から浴びせてやるのに。
シンッと静まったこの二人の空間を破ったのは、背の高いニッコリスマイル全開の彼だった。
『あー‥‥、突然の事で実は、僕も戸惑ってる』
『アハハ、わ、私もです』
『この年になっても彼女が居ないって、よくイジられるからもう慣れてるんだけどね』
『私も、まだまだ若いのに彼氏作らないのかってインターンの時から言われてました』
多分、ここまでは普通の会話だった。
けれどどうしても賑やかな席に男女二人っきりで居ると、眼鏡たぬきと同じ様な事を言う専務や係長がいとも簡単に『付き合ってしまいなさい』と冷やかす。
散々言いたい放題言い散らかして、再び二人になると気まずいのなんのって。
大体顔も身長も申し分ない程の彼が、今26歳にもなって結婚は愚か彼女が居ないなんて訳アリだからだろう。
『えっと、ごめ―――‥‥』
『えぇ、あたしとなんて付き合わない方が良いですよ。高野さん将来有望なんでしょ?』
正直これ以上悪目立ちするのが嫌だった。社会的地位の高さだけが取り柄の人間に指図されるのも大概だったから。
『あたし、愛だの好きだの彼氏だのって、本当そんなのもう勘弁なんで。高野さんは身の丈に合った方と真剣なお付き合いをなさってください』
惚れた腫れたはもう充分。
好きだの愛してるだの、そんなくだらない事で束縛されるのはもう懲り懲り。
―――ズキッと、あの時の傷が痛んだ。
『えっと、よくね?そうやって言われるんだけど、僕結婚する気ないんだよ』
『え?』
それは彼からの、意外な言葉だった。
『だから松本さんの気持ち、すごい分かるよ』
『‥‥‥ッ、』
―――――――――――――――――――――
―――――――――――――
玲との関係はそこから始まった。
年相応の体裁が欲しいだけの彼と、恋人が居ないというレッテルを貼られて変な付き合いを極力減らしたかったあたしがくっ付く利害が一致したまでの事。
同棲の件も、お互いの上司から「お前らもそろそろ結婚に向けて同棲しないとだめだろう」と滅したくなるくらいのお節介を焼かれたからだ。
最初は適当に流して相槌を打っていただけの話も、ある日突然佐藤常務が自分の顔の広さを豪語するかの如く不動産屋をオフィスに連れて来た時は本気で殺してやろうかと思った程。
そして、今に至る。
傍から見ればきっとあたし達は完璧なカップルだ。
彼氏は将来有望な経営コンサルタント、彼女は一流企業の総務部務め。
同期からも「羨ましい」だの「紗季を見習いたい」だの恥ずかしいくらいに褒め称えられるから安心した。
―――ガチャ。
自分でも満足のいく匂いを香らせながら風呂を出て、クルッとバスタオルを身体に巻き付けた。
「‥‥‥って、あんた何やってんの」
「んー?歯磨き」
「まぁ、あたしもそう見える。バスタオルありがと」
「ううん、あ、朝ごはん簡単に作ったから食べよー」
「‥‥すごいね。あたし十分も入ってなかったと思うんだけど」
「だって僕ずっと一人暮らしだったしさ、得意分野」
玲と居るとすべてがラクだ。
そして彼との"お付き合い"は至極簡単なルールで成り立っている。
それはあたしの会社の人間と関係を持たない事。ただそれだけ。あとは何をしようと構わない。
誰と飲みに行こうが、誰とホテルへ行こうが干渉しない。
それが暗黙のルール。
「‥‥でも、朝ごはんより紗季のその姿に欲が沸くんだけど」
「朝から盛んなのね、玲くん」
「‥‥‥まぁ、僕も一応男だし?それに―――‥‥」
歯磨きを終えたばかりの玲はタオルで口元の水分を拭いながらあたしの耳元でこっそり言う。
「昨晩の紗季が喘ぐ姿、あれ忘れらんない」っと。
「‥‥なーんてね。ほら、折角作ったのに冷めるから食べよう?」
「‥‥ッ」
パチンッと洗面所の電気を消して先に戻っていく彼の後ろ姿を睨んだ。
玲はあたしよりたかだか三歳年上なだけと言うのに、あたしが知るどの男よりも大人しく、そしてどの男よりも色気の使い方が上手い。
「‥‥‥‥」
あれだけスーツが似合う長身な黒髪経営コンサルタントのくせに、結婚する気がないなんて最初は可笑しな性癖でも持っているのかと疑った。
まぁ、そんな玲だから今一緒に居られるわけだけれど。
「‥‥じゃあ、先行くから。あとよろしくね」
「うん、あ、ねぇ。今日は仕事終わったらすぐ帰ってくる?」
「‥‥ううん、今日会社の飲み会。だから、安心して女と家使いなよ」
ウィンク交じりにそう言って玄関を出た。
同棲する前は自分の家があったから何不自由なく自由奔放に出来ていた事も、玲と一緒に生活を始めるとなればあたし達の付き合いもそれに応じて大きく変わっていった。
今まであたしが切ろうに切れなかった男達の関係も、知ってか知らずかは兎も角玲は何も言わなかった。
一緒に生活を共にするにあたって実際はどこまで口を出さないつもりでいるのか曖昧だったから、あたしは思い切って男を新居に連れ込んでみた。
けれどやっぱり何も言わない玲だから、それすらも許されるのだろうと把握した。
その点、彼も彼なりにする事はしているみたい。
なんの警戒心もない玲の携帯にはよく、一人の女からの連絡が絶えない事をあたしは何度も見ている。
それに何度も家に連れてきているって事も。
馬鹿なのかそれとも当て付けなのか知らないけれど、玲の女は家に来る度にあたしの化粧品を必ず一つ盗んでいく。
流石に腹が立つからあたしも負けじと劣らず玲のパンツを男に履かせた。
玲の事は好き。
ただ身体を重ねるだけのどこぞの男よりもはるかに玲に抱かれたい。実際に彼との相性は抜群だと思ってる。
あの癪に障らない小さな気遣いも好き。
あと‥‥あの笑顔。
ふわふわした真っ黒の髪があの甘い笑顔を引き立てている。
あたしの、肩まで伸びたブラウンベージュの髪をゆっくりと手で解しながら「可愛い」って囁く声も好き。
「おはようー紗季」
「柚木、おはよう」
大粒の雨の所為で塗れた服を拭きながらオフィスへ入ると、隣の席の柚木は何故か目を輝かせながらあたしを待っていた。
「ねぇ、紗季ってさ。あの高野さんと同棲して一年目じゃない?!どうなのよ!最近どーよ!」
「‥‥そっか。なんせ同棲の話は佐藤常務の所為で柚木達に全部筒抜けだもんね」
「そうよ!どう?もう結婚の話とかしちゃってんの?」
「まだまだよ~、向こうも今中小企業の経営を立て直すとかって大変みたいで朝もギリギリまで寝てるし。だから彼が作る朝ご飯も最近は短時間で出来るものばかり」
「キャ―――ッ!もうイケメン!それだけでもうイケメン」
柚木は両頬を抑えながら「キャーッ」っと足をバタつかせて飛び跳ねた。
「‥‥さ、朝礼の準備するよ」
「マジで羨ましいんですけど!」
「‥‥そう?」
愛っていう形に囚われないあたし達の関係。
一般的な男女のお付き合いに嵌らない今が、これまでにないくらいラクで、そしてすごくあたしらしいと思う。
『ねぇ、今日話してた男誰?何、話してたの?』
『お前俺の事好きなんだろ?
だったらいちいち詮索すんなよ面倒クセェ!』
『ねぇ、もう一緒に死のうよ。そしたらさ―――ッ』
―――ズキッ。
この傷の痛みは、まだまだ癒えない。
第三者の目からまともに見ればおかしいだの歪んでいるだのと指を指されるかもしれないけれど、あたしと玲はそれで成り立っている。
大体"普通の付き合い"って言うものがどういうモノなのかすら分からなければ、その普通を作り出す人の物差しが正しいだなんて一体誰が決めるんだろうか。
「「「さ、お疲れかんぱ――――いっ!」」」
同期達との月一の飲み会。
入社して以来一回たりとも欠かしたことのないこの会の主役は勿論、惚気話が断トツ。
女子十人で行う会は、もはや彼氏自慢の会って呼べばいいと思うくらい見栄の張り合い合戦が続く。
彼氏が結婚を見据えてくれているだ、この前の休日に彼氏と旅行へ行っただ、ブランドのバックを買ってくれただのって彼女達はさぞ幸せそうな顔をして話す。
あたしはそれを、ただただ愛想笑いで返すだけ。
「でもやっぱり紗季の彼氏は良いよねぇ~」
「‥‥え?」
「だって、もうさぁ。あんな大物物件中々ないよね~」
「‥‥‥そう?」
「この前もさ、どこか旅行行ったんでしょ?高級ホテルの!」
「あ、あぁ。うん、まぁね」
実際は国立市にある高級"ラブ"ホテルに泊まっただけだけれど。
先週の土日はお互いに予定もなく、ただの暇つぶしにあたしから誘ったまでの事。
『‥‥玲、暇』
『‥‥何、構ってほしいの?』
『そう、最近玲が不足してる』
『‥‥‥‥』
『ねぇ、聞いてる?』
『‥‥じゃあ、どこか行こうか』
『それは嫌。歩くの暑いし怠い』
‥‥‥なんて一部始終は絶対に言えない。
結局、玲はあたしの横暴的な我が儘に少し考えて馬鹿みたいに高級なラブホを取った。
「あんた‥‥いくら結構稼いでるからってコレはないでしょう」っと真面目な顔で突っ込みを入れても、「だって紗季はお金かからない子だから。これくらいは、ね?」って笑顔で言う玲。
目的なんて一つしかないこのホテルに、夜景なんて必要なければ無駄に輝く水槽も要らないのに。
そんな事を思いながら布一枚の隔たりすらないあたしと玲の距離を確かめて、彼から与えられる温もりと快楽だけをただ感じていた。
「だって高野さんマジでイケメンだし!」
「ねぇ紗季!あんたちょっと素っ気無いところあるんだから気を付けないと捨てられちゃうよ!」
「‥‥‥」
捨てられる、ねぇ。













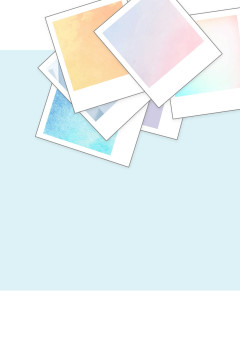


編集部コメント
引きこもりのおじさんと真面目な女子高生という組み合わせがユニーク。コンテストテーマである「タイムカプセル」が、世代の違う二人をつなぎ、物語を進めるアイテムとして存在感を発揮しています。<br />登場人物が自分の過去と向き合い、未来に向かって成長していく過程が丁寧な構成で描かれていました。