青森の田舎に戻って最初に思ったこと。
…何も変わっていない。
コンビニは24時間営業というのが都会では当たり前だが、田舎のコンビニは夜10時には閉まる。
しかも小さい頃は気づかなかったが、飲み屋が無駄に多い。飲み屋と言っても居酒屋ではなく、俗に言うスナックだ。
相変わらず閑散とした土地。
俺の知ってる友人も、もしかしたらもう殆どが引っ越してしまったかもしれない。
そんなことを考えながら、街中をぶらりと歩く。
幼い頃に遊んだ神社の鳥居は、朱が少し剥げていて、俺の居なかった年月の長さを物語っている。
俺が通っていた小学校は、どうやら廃校になったようで、ボロボロの廃墟と化していた。
風が建物に吹き込んで、まるで泣いているかのようだった。
街を歩くにつれて俺が青森に戻って真っ先に抱いた、この街は何も変わっていないという印象が間違いだったことが分かる。
神奈川での喧騒に包まれた日常から解放され、静寂に包まれた故郷に戻り何だか少し物悲しい気持ちになった。
突然後ろから声をかけられる。
落ち着いた声だが、どこか怯えたようなか細い声だった。
俺はその声の主に挨拶を返すため、後ろを振り返る。
声の主は、一言で言うなら地味。
古いテレビとかなら学級委員長、最近のならいじめられっ子のキャラでも演じていそうな出で立ち。
黒く艶やかな長い黒髪はおさげにされ、前髪は年齢的に不釣り合いな安っぽいプラスチックのダサいヘアピンで留められている。
目元には眼鏡。
まさに地味という言葉を擬人化させたような女だった。
この街には元々人が少ない上に、都会に出ていく人間はいても新しくこの土地に越してくる人間なんてほぼ皆無。そのため殆どの人は顔見知りのはずなのだが、数年の月日を経て戻ってきたせいかこの女が誰なのか、俺にはさっぱり分からなかった。
だが、それは相手も同じだったようで見慣れない顔の俺に対して少し戸惑った様子だった。
おどおどとした口調で俺に問いかける。
そんな彼女に、俺は元々この地で育ち一時期神奈川へと越した後、また此処に戻ってきたことを簡潔に伝えた。
彼女はそう言いながら嬉しそうに笑った。
地味な女だと思っていたが、笑った顔には笑窪が浮かび、明るく朗らかな印象を深めた。
そう告げると彼女はぽかんと口を開けた。
そう口に出すと同時に、頬を赤らめる。
何を焦っているのか、まくし立てるように迫ってくる彼女。
俺は過去の記憶を遡り、くーちゃんというあだ名の人物を必死に探す。
結局思い出せずにそう伝えると、彼女はとても落胆した様子で、「そうですか…」とだけ言った。
結局その後お互いの家が近いということで、俺がいない間の街の様子や廃墟なった小学校が今は心霊スポットになっているというような他愛もない話をしながら家路についた。
家に着くと、母親が引越し業者と話していた。
そして俺らを一瞥すると業者との会話を早めに切り上げて、こちらへと向かってくる。
そして、彼女に「久遠ちゃん、久しぶりねぇ」と仲睦まじい様子で声をかける。
俺がそう言うと、母親は呆れたような顔をこちらへ向ける。
俺は意味がわからずにいたが、どうやら母親の話によると俺と彼女は幼稚園、小学校とずっと同じクラスだったらしい。
母親がベラベラと話すうち、俺の記憶も徐々に呼び起こされていった。
幼い頃の話をきいて、ようやく俺は「くーちゃん」が初恋の相手の「来宮久遠(きのみやくおん)」であることを知った。






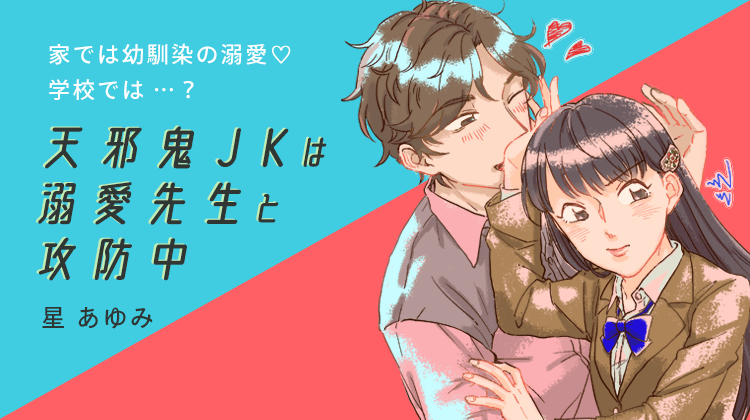













編集部コメント
主人公は鈍感で口下手ではあるものの『コミュ障』というほどではないので、キャラの作り込みに関しては一考の余地があるものの、楽曲テーマ、オーディオドラマ前提、登場人物の数などの制約が多いコンテストにおいて、条件内できちんと可愛らしくまとまっているお話でした!<br />転校生、幼馴染、親友といった王道ポジションのキャラたちがストーリーの中でそれぞれの役割を果たし、ハッピーな読後感に仕上がっています。