八月の中旬、否応なく爽太と顔を合わさなければならない日がやってきた。
登校日である。
今のご時世、登校日なんて制度がそもそも存在していることがヘンな話なのだが、小さな町の古い学校にそんなことを言っても仕方がない。
気の重いまま学校へ行って、周りにバレないようにそれとなく爽太を避けて、なんとか一日乗り切った。
ハズだったのに―――
「今夜、星でも見に行くか」
爽太は突然立ち上がってそう言った。
「ハァー?」
とても爽太から発せられたとは思えない言葉に、周りの人間が一斉に振り向く。
爽太は今隅っこの席で、三方を固めるのは、良いのか悪いのか、悠奈と彩佳と拓真だ。
帰りの挨拶を済ませ、残っている人数もまばらになった教室内に、三人の声はよく響いた。
「なに、お前? 頭でも打った?」
爽太にしてはありえないほどロマンチストみたいな発言に、「柄じゃないよ」と言いながら拓真が爆笑して爽太の顔をのぞき込む。
「俺はいたって真面目だ」
ムスッとした爽太の表情は、確かにウソをついているような感じではない。
「お前たちも来いよ」
そう言うと、爽太は悠奈と彩佳のほうをチラリと振り返った。
「えっ?」
驚いて言葉が出なかった悠奈とは裏腹に、彩佳は拓真に負けず劣らず大爆笑をかました。
「なにソレ、本気で言ってんの? たまにはいいこと言うんだねー、中峰も」
そんなことを言いながら彩佳と拓真はまだおかしそうに笑っている。さすがに悠奈もつられて吹き出した。
みんなの様子に機嫌を悪くしたのか、爽太は窓の外に目をやりながらぶつぶつ言っている。やがてカバンに視線を落としたかと思うと、吐き捨てるように言った。
「とりあえず、いいモン見せてやるから、八時に俺んちの前に来い!」
そのまま机の上のカバンを乱暴に持ち上げて、表情も見せないままスタスタと教室を出ていく。
呆気にとられた三人は、いつのまにか笑いが止まり、ポカンとしながら爽太の消えていった方向を見つめていた。
「ホントに行くんだね……」
誰にともなく言った悠奈の言葉に、彩佳と拓真はピッタリそろってうなずいた。
午後八時――
軽い荷物だけ持った悠奈は、由紀子に事情を話してから、そぉーっと扉を開けた。薄く開いて、外の様子をうかがう。
すると、隣の家の門に、スマホを触りながらもたれかかる人影が見えた。間違いなく爽太だ。
それから、自分でもよくわからないがなんとなく物音を立てないように玄関を出て、手を掛けた門が軋んだところで爽太が悠奈に気づいた。
「よお」
爽太は顔だけ上げて言う。悠奈も軽く答えて爽太の横に並んだ。
「ねえ……なんで星なんて見に行くの?」
昼間、一番気になったが爽太の強引な帰宅により結局聞けなかったことだ。
悠奈の静かな問いかけに、爽太も静かに答えた。
「嫌いじゃないからな」
いまいち答えになっていない答えを聞きながら、悠奈は「ふーん」と小さく返す。
二人がしゃべらなくなると、風の音、虫の声、近くの海の音まで、いろいろな音が耳に入ってくる。
そんな沈黙ではあるが静寂ではない時間がしばらく流れた後、爽太は思い出したように言った。
「それに、昔一回、一緒に見に行っただろ」
取って付けたような、でも本当は一番大事なその言葉を聞いて、悠奈は息が止まる思いだった。
まさか、爽太が覚えているとは思わなかった。
昼間に星と聞いて、悠奈の頭を一番最初によぎったこのはそのことだ。
でも、爽太と一緒に山に登って夏の大三角を見たのは、もう十年も前のことである。綺麗とか、そういうものに無頓着な爽太のことだ。覚えているはずがないと思っていた――
「覚えて、たんだね」
胸がいっぱいになって、思わず空を見上げる。ここからの星も綺麗だが、あの場所から見える満天の星は、古今東西のどんな言葉をかき集めても足りないくらい美しい。あの星空が、ちゃんと爽太の心にも刻まれていたことが、たまらなく嬉しかった。
「来たぞ」
爽太の声に視線を下ろすと、彩佳と拓真が向こうからやってくるところだった。なにやら言い争っているようだが、いつものことなので気にしない。勉強ではツートップの二人だが、二人そろうと子供みたいな喧嘩をするのだ。
「おーい! 彩佳ー!」
悠奈が叫んで手を振ると、彩佳はコロッと笑顔になって走って来た。後ろから「やれやれ」とでも言いたそうな顔で、拓真も走ってくる。
「仲いいなぁ、あいつら」
そんな爽太の言葉を横に聞きながら、悠奈は「そうだね」と曖昧に笑った。
星を見る場所は、十年前、爽太と一緒に行った場所だった。そこまでの道は明かりもないので、スマホのライトで照らしながら進む。
歩いている間は、バカみたいにはしゃいだ。ライトを顔の下から当てて幽霊みたいにしたり、いきなりスマホからホラーっぽい音を出して脅かしたり……
今日のみんなは、ネジが一本くらいハズれているみたいだった。
――みんな、わかっているのだ。
ここにいる全員が小学校からずっと一緒だが、一緒にいられる時間はあと少ししかない。みんな、中学を卒業したら別々の道を歩き始める。そこには希望もあるが、この小さくても居心地のいい街を出る不安、なじみの友人たちがそばにいない孤独、いろんなものが待っている。高校へ進学するためにも、まず一つ、大きな壁を越えなければならない。
だからこそ、そんな不安や孤独に押し潰されないようにするために、ありったけの力でみんな今を楽しんでいる。
こんな楽しい時間が少しでも長く続きますようにと、悠奈はそっと、心の奥で願った――
十分くらい山道を進むと、木々の中にぽっかりと開いた空間が現れた。
みんなはしゃいでその空間の中へと駆けていく。
懐中電灯がわりのスマホのライトを消すと、そこは本当に真っ暗になった。今日は新月なので、月明かりもない。そんな闇の中から顔を上げて、悠奈は息をのんだ。
真っ暗な世界から見上げたその星空は、まるで、宝石箱のようだった――
気がつけば涙が出ていた。こんな暗さじゃ表情なんて誰にも見えないので、一人静かに雫を拭う。
「あれが、デネブ、アルタイル、ベガだ」
隣に立つ爽太はとても楽しそうだった。
爽太ってこんなに星好きだったっけ?
ちょっと面白く感じながら爽太の指さす方角を見上げる。そこには、夏の夜空に輝く夏の大三角がある、はずなのだが――
「あれ? わかんないな……」
見上げた先の夜空はもちろん美しい。だが、どれが織姫で、どれが彦星なのか、見分けがつかない。
「あるだろ? ほら、あそこに」
爽太の言う方向をじっと見つめる。が、やっと見つけられたのは織姫だけで、彦星は見つけられなかった。
悠奈はうつむいて、ギュッと目をつぶった。
幼い頃、あんなにハッキリと見えた織姫と彦星が、今の悠奈には片方しか見えない。
「今年は七夕晴れたからなー。よかったよかった」
ひとつ隣の爽太は、とても楽しげだ。でも、悠奈はなにも言えなかった。
美しい星空の代わりに、暗いものが悠奈の心のなかに渦巻き始める。
たまらなくなって、悠奈は一歩あとずさった。
――織姫と彦星が二人そろって見えないのは、きっと悠奈が昔のように二人の幸せを願えないからだ。
昔は、純粋に織姫と彦星の願った。いつか、ずっと一緒にいられるようになればいいと。
でも、今の悠奈に他人の幸せなんて願えなかった。悠奈が今願っているのは、たぶん……自分の幸せだけだ。
爽太の進む道を邪魔してはいけない。困らせてはいけない。自分にそう言い聞かせても、ずっと一緒にいてほしいと願わずにはいられないのだ。
行かないで、なんて言ったら、優しい爽太はきっと、推薦を受けるのを迷ってしまう。ずっと努力してきたことなのに、たとえ推薦を受けたとしても、きっと罪悪感を抱えてこの先過ごすことになってしまう。
そんなことになってはいけないと、自分ではわかっているのに……
それでも「行かないで」と言いたかった――
いつの間にか大きくなった爽太の背中をちらりと見上げて、悠奈はまたうつむく。
――ねえ、あたし、どうしたらいい?
声に出せない問いかけに、答える声があるはずもない。
胸がつまった。息が苦しかった。でも、
ダメ……泣かないで……
そう必死に自分に言い聞かせた。
帰り道、悠奈はずっと不機嫌だった。
いや、正確には不機嫌を装っていた、だ。口をつぐみ、ずっと下を見て歩いている。そうでもしなければ、涙が溢れてきてしまいそうだった。
彩佳はなにも言わずに、悠奈の横を歩いてくれた。
「そこ、横急斜面だから気をつけろよ」
一応の忠告をくれる拓真も、普段絶対こんな態度をとらない悠奈の様子に戸惑っているようだ。
申し訳ないと思ったが、行きの道がウソみたいに沈黙が続いていた。
「悠奈」
しびれを切らしたように声を出したのは爽太だった。
「なにがあった? さっきの短い時間で、そんなに大したことがあったのか? 悪い虫に刺されたとかじゃねーよな?」
一瞬悠奈の足が止まるが、そのまま悠奈は歩調を速める。
「おい」
背後から爽太のイラついた声が聞こえるが、その声を振り払うように悠奈はどんどん歩いていく。彩佳も小走りで後を追いかけてきた。
「なんか言えよ」
不機嫌な爽太の声が後ろから近づいてくる。
「ごめん……」
言えたのはそれだけだった。
ごめんなさい。身勝手でごめんなさい。私が悪いの。全部私が悪いから、だからほっといて。今は、今だけは、私の心に踏み込まないで――
頼りない手のひらをギュッと握りしめた、そのとき、
「おい!」
爽太の手が悠奈の肩を強く掴んだ。
「離して!」
反射的に悠奈はその手を思いっきり振り払ってしまう。
ごめんなさい……と思った。
振り切った反動でよろける。
怒ってるだろうな……。ふらついた体で見上げると、予想に反して爽太はとても焦った顔をしていた。
なんだろう……?
ぼんやりしながら首を傾げると、その答えは悠奈に現実を突きつけるように突然やって来た。
「え――」
傾いた体を立て直そうとして地面をとらえたはずの足は、気づけば空を切っていた。そのまま一気に視界が揺れる。
「「悠奈!」」「早坂!」
三人の声が同時に聞こえるが、それを冷静に処理できるほど頭は正常に働いていない。
目の前が天上の星々でいっぱいになりそうになったとき、爽太の右手が伸びてきた。悠奈の手を伸ばせば届く範囲だ。
よかった、助かる――
全員が安堵する。しかし、悠奈は、その手を……
掴めなかった――
手を引っ込めた悠奈を見て、爽太の顔が恐怖に染まる。
……あたし、バカだなぁ。
みんなの叫び声を聞きながら、悠奈は急斜面を転げ落ちていった。
「悠奈! 悠奈!」
強く肩を揺すられている。この声は紛れもなく、聞き慣れたあの声だ。
「うぅぅ」
うめき声をあげて目をうっすらと開けると、そこには爽太の引き攣った顔があった。
あれ……あたし、無事だったんだ……
まだうまく働かない頭で考えてから、ぼんやりと目を開いていくと、視界がやけに狭かった。爽太の顔以外のものはあまり見えない。
「――って、うわぁ!」
冷静になってから爽太の顔の近さに驚く。気がつけば、爽太の顔を思いっきり突き飛ばしていた。
うっ――
突き飛ばしてから、初めて体の痛みに気づく。
「ってーなー」
いきなりぶたれた爽太のほうは、鼻を押さえて上を向いていた。かなり思いっきり殴ってしまったようだ。
「目覚め早々人の顔殴れるんだったらとりあえずは無事だな」
鼻を押さえたまま、爽太が恨めしそうな、でもちょっとだけ安心したような声で言った。
「ごめんごめん――イタッ」
言いつつ起き上がろうとした悠奈の体に痛みが走る。ずいぶんといろいろなところに打ち身を作ってしまったようだ。
「おい、大丈夫か?」
この状況だ、さすがに爽太も心配そうに悠奈を見やる。背中を起こそうとすると手を貸してくれた。
「大丈夫、だと思う」
体中をペタペタ触って確かめてみるが、打ち身や擦り傷以外の怪我は見当たらない。出血も特には無いようだった。
「あんな高さから落ちたんだ。なにかあったらすぐに言えよ」
そう言うと爽太は横を向いて斜面の上を見上げた。見上げた先では彩佳と拓真が手を振っているのがわかる。
そこまでの距離は十メートルくらいだろうか。かなりの高さから転がり落ちたようだが、幸い悠奈が通ったらしい場所には岩も木もなかった。障害物に阻まれることなく、平たんになったところで自然にとまったようだ。これが、怪我の少なかった要因だろう。
「おーい! 大丈夫かー?」
「ゆぅーなぁー! 無事ー?」
斜面の上から彩佳と拓真の声がする。
「大丈夫だー! 俺たちはとりあえずこっちの歩けそうな場所通って帰るから、お前たちはそっちの道で帰っててくれー!」
「心配かけてごめんねー!」
爽太と悠奈が叫び返すと、「「よかったー」」と言う声が二人そろって聞こえた。
「じゃあ、気を付けて帰れよー」
「中峰、悠奈のことよろしくねー!」
そう言い残すと、二人はもといた道を下っていった。
二人の声が聞こえなくなると、なんだか気まずい沈黙が流れた。
「あ、あの……ありがとね」
爽太の顔は見られなかったが、悠奈なりの感謝を精一杯込めて言ったつもりだった。
状況からして、爽太は悠奈を助けるためにこの急斜面を下ってきてくれたのだろう。爽太の服もかなり汚れている。血相を変えて追いかけてきてくれたのは容易に想像がついた。すべては、悠奈のせいだったのに……
申し訳なさが募って、悠奈は自分の手を握りしめた。
「爽太――、ごめん」
「そんなことより!」
悠奈の言葉を遮って爽太がいきなり大声をあげた。その声は、怒っているのか、悠奈が聞いたことのないくらい震えていた。
「なんで……」
震える声のまま爽太は話し続ける。
「なんで……あのとき俺の手を掴まなかったんだ?」
爽太の大きな手が悠奈の腕を掴む。その手は、言葉よりも震えていた。震えながら、でも痛いくらいに力を込めて、決して悠奈の腕を離そうとはしない。それはまるで、怒っているというより、怯えているようだった。
「怖かった……届くはずのお前の手に届かなくて、そのままお前は闇の中に落ちていった。こんなに怖いと思ったこと、今までねーよ……」
うつむいて震える爽太は、それでも悠奈の腕だけは力いっぱい掴んでいる。
胸が、痛かった。
でも、あのとき手を引っ込めた本当の理由は、どうしても爽太に知られたくなかった。
「なんであんなことしたんだ……」
震える爽太に、悠奈はのんきなフリをして答える。
「わざとじゃないよ。ほら、あたしどんくさいから、届く距離なのにつかみ損ねちゃっただけ」
「そんなはずねーよ!」
爽太は勢いよく顔をあげ、悠奈に視線を合わせた。
「あのとき、俺の手は確かにお前に届いた。お前が手を伸ばさなくても、頑張れば届いたくらいだ。なのに、お前は自分の左手を思いっきり引いた。だから俺の右手はなにも掴めなかった。掴めたはずのお前の腕を、俺の右手は――――――――右、手?」
爽太の目が泳いだ。
「だからそれは……、あたしがどんくさいからで……」
ダメ、お願い、気づかないで。
全部あたしのせいだから、だから爽太はなんにも知らなくていいの……
顔ではヘラヘラ笑いながら、悠奈は必死に心の中で叫んだ。
だが、悠奈の思いとは裏腹に、爽太の顔からはサーッと血の気が引いていく。
「お前まさか、俺の腕のこと心配して……」
「そんなことないって言ってるでしょ!」
――言ってしまった。こんなに強く否定したら、これはもう認めたのと同じだ。
ダメなのに、絶対爽太に気づかれちゃダメなのに。
大事なウソひとつつけない自分の頭の悪さを、悠奈は全力で呪った。
「そうか、右手だったから……」
悠奈はもうなにも言えなかった。爽太の考えていることは、すべて真実だから。
――そう、あのとき、悠奈は爽太が右腕を伸ばしたから手を引っ込めたのだ。爽太の右腕……右投げのピッチャーである爽太の、命の次に大事と言ってもいい右腕。
人の体が物理法則に従って落ちていくときの落下エネルギーはすさまじい。ドラマやマンガで見るような、間一髪落下しそうな仲間を助ける、みたいな技は、現実では助けた側の腕にも必ずダメージが残るのだ。そんなダメージをピッチャーである爽太の右腕に残す訳にはいかなかった。
我ながらバカなことだとは思うが、あの落ちる瞬間、悠奈はそんなことを本能的に思ったのだ。自分の身に及ぶ危険よりも先に。
「やめてくれよ……そんなこと……」
そうやって爽太は言うが、悠奈はあの判断を後悔していない。悠奈のせいで、爽太の未来を潰してしまいたくはないから。
「もう、絶対するな……こんなこと……」
震える爽太の声に、素直に「うん」とは言えなかった。
たぶん、この先何度だって、きっと私は同じ選択をする。
「あたしは、あたしを守ったんだよ。自分の望まない未来にしないために。わがままでしょ。だから、爽太のせいじゃないの」
「お前が無事じゃなきゃ意味ねーだろ!」
爽太は叫んだ。悠奈の目を真っ直ぐ見つめたまま。
そのあまりの迫力に、悠奈は一瞬体をこわばらせた。
「自分のせいで俺の野球生命断ちたくないとか思ってんならほんっとに怒るぞ。俺だってなあ、俺のせいでお前を危険な目に遭わせたりなんかしたくねーんだよ。お前が死ぬくらいだったら、俺の腕なんて何本でもくれてやる。もしお前がそれで辛い思いするってんなら、死ぬ気でなんとかして責任なんて感じないようにさせてやるからな」
怒鳴るように言ったその声が、悠奈にはとても痛かった。優しすぎて、真っ直ぐ受け取るのが痛かった。
気づいたときにはもう、涙があふれて止まらなかった。
「ごめん、あたし……」
こんなに怒った爽太を見たのは初めてだった。
こんなに怯えた爽太を見たのも初めてだった。
ごめんなさい。あたしをこんなにも思ってくれる人が、ずっと近くにいてくれたのに――あたしはたぶん、その優しさに気づかないふりしてたんだ……
私は昔からずっと、強がっていた。爽太は、ただずっと一緒に育ってきただけ。だから特別な感情なんてない。そう、自分に言い聞かせてきた。でもそれは、私が臆病だったから。傷つきたくなかったから。だから私は、爽太になんて興味がないようなフリをしてた。
だけど、爽太がいなくなるかもしれないと聞いてから、だんだんそうしていられなくなった。言葉に出さないし、自分では絶対認めないけど、爽太の何気ない優しさに触れるたび、胸を刺す痛みは増していく。痛めば痛むほど、自分の中の爽太の大きさを思い知った。そして今、蓋が完全に開ききった。ずっと、長年抑え込み続けていた気持ちの蓋が。一度開けば、もう閉まってはくれない。
――ああ、そうなんだね……好きになるって、こういうことなんだね。
素直に認めると、それは、思いの濁流となって溢れ出しそうだった。
でも、それはできない。
爽太のことを大切に思えば思うほど、その思いを爽太に伝えることはできないのだ。
あたしにとって一番は爽太だから、幸せな道を歩いてほしいと願うから、爽太があたしにしてくれるように、爽太の幸せを一番に考えるの……
これが、私の最後の強がり――
思いをせき止めた代わりに、涙を止めることはできなかった。……これでいい。きっと、涙がすべてを洗い流してくれるから。
大粒の涙を流す悠奈を、爽太はそっと包んでくれた。
「……怒っちまったけど、お前の思いには感謝してる」
耳元でささやかれた優しい声に、悠奈は精一杯うなずいた。
「ねえ」
爽太の背中で悠奈は言った。
立ち上がろうとしたときに捻挫に気づいたので、今は爽太が負ぶってくれている。
返事はないが、聞いているのはわかっているのでそのまま続ける。
「梨花ちゃんのことは、あたしに任せてくれていいからね」
すると爽太は、それまで律動的に刻み続けていた歩みを止めた。
「知ってたのか……」
「当たり前でしょ」
さっきひとしきり泣いたせいか、今は落ち着いて爽太と話すことができた。
正直今でも、「本当はどうしたいの?」と、自分を甘やかす心の声がする。それには、「ずっと爽太と一緒にいたい」という自分の弱さが出る。
でも、それよりも爽太が大切だった。
爽太のことを思えば思うほど、悠奈は爽太と離れる決意を固めるのだ。
歩みを止めていた爽太が、また歩き始める。
「まさか、迷ってんじゃないでしょうね?」
茶化すように悠奈が言うと、爽太は不機嫌そうに、
「まだ決めてないだけだ」
と言った。
「せっかくの名門からの推薦だよ? 蹴ったりなんかしたら承知しないからね!」
今は爽太の顔が見えないから存分に言いたいことが言える。
さっきまで大泣きしてたのは誰だよ――とはさすがに爽太も言わなかった。
かわりに、薄く笑ってから、小さく言った。
「ありがとな……」
たぶん、この言葉は悠奈に聞かせたかった訳じゃない。だから悠奈は、返事をするかわりに、少しだけ爽太につかまる腕に力を込めた。



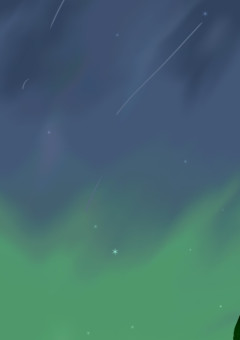















編集部コメント
主人公は鈍感で口下手ではあるものの『コミュ障』というほどではないので、キャラの作り込みに関しては一考の余地があるものの、楽曲テーマ、オーディオドラマ前提、登場人物の数などの制約が多いコンテストにおいて、条件内できちんと可愛らしくまとまっているお話でした!<br />転校生、幼馴染、親友といった王道ポジションのキャラたちがストーリーの中でそれぞれの役割を果たし、ハッピーな読後感に仕上がっています。