「…おい、マキ?」
はっと我に帰る。
声の元を辿ると、幼馴染みのリクが訝しげにこちらを見ていた。
「ごっごめん。ちょっとぼーっとしてた」
「あっそ」
たいして興味もなさそうにリクは言うと、視線を前に戻した。
いつもの帰り道、私は暗くなった辺りを見回しながら、リクと共に家路にへと着いていた。
いくら七月と言え、辺りが暗くなるとやはり肌寒い。
私は空を見つめながら、さっきの“夢”のことを思い出していた。
楽しそうに弾んでいる声と、詰まらなそうな声。
そんな2つの声が聞こえたけど、周りを見回しても誰も居なくて。
私はただ、そんな2つの声をぼーっと聞いていて。
でも、2つの声は途中で途切れてしまった。
あの後、二人はどんな話をしたのだろう。
そして、何故私はそんな“夢”をリクと帰ってるときに見たんだろう。
「…そもそも、歩きながら夢見るって…寝てないのに」
「あ?なんだ?」
ボソッと言ったつもりが、リクの耳には届いていたようだ。
なんでもない、と誤魔化すように歩を進める。
そこはちょうど私とリクが別れる道で。
好都合と思いながらリクの方を見る。
「ん、じゃあまた明日ね!」
「おー」
バイバイ、と手を振りながら去っていくリクの背中を見送り、私も家へと向かった。
木枯らしが吹くようになってきたある日のこと。
いつもの帰り道をリクと歩いていると、そーいえば、とリクが話をふってきた。
「なに?」
「いや、お前って好きな奴とか、居んの?」
「はい!?」
予想の斜め上を行く質問に、思わずリクを叩く。
「ってーな!なんだよ!」
「ああああんたね!なんでいきなりそんな話をっ!」
「いや、別にクラスの奴がそんな感じの話してたからよー」
ずる、と転びそうになった。
リクのことだから深い意味は無いだろう…とは思っていたけどさ……
少し火照った頬を冷ますように手で包む。
……私は、リクが好きだ。
それはいつからか、なんて考えてもわからない。
たぶん、物心付いたときから好きだったんだと思う。
リクと一緒におやつを食べて、リクと一緒に遊んで、リクと一緒にお昼寝をする。
そんな日常が小さい頃の“アタリマエ”だった。
まあ、今となってはそんなアタリマエさえ無くなったのだけれど。
毎日一緒に帰ってはいるが、たぶんこれもリクにとっては深い意味の無いこと。
所詮、アタリマエの延長だ。
本当はリクに告白して、あわよくば恋人同士になれたら良いな、と思ったことが無いわけではない。
でも、その私の行動のせいでこのアタリマエの延長さえも無くなってしまったら。
私はどうしたら良いのか分からなくなってしまうだろう。
だから、私は告白するつもりもない。
リクへの想いは生涯私だけの秘密に・・・ーー
「俺さ、お前のこと、好きなんだけど」
前言撤回。
「はいいいい!?」
突然の爆弾発言に、私はただ叫ぶことしかできなかった。
「いや、だから、俺お前のこと」
「あああ分かった分かった!それは分かったから!」
はあはあと叫びすぎて乱れていた呼吸を整える。
「…分かったよ、じゃあ、試しで良いから付き合ってくんね?」
「…え?」
一瞬頭がフリーズした後、意味を理解した頭はまるでそれを伝えるように、一気に体を熱くしていく。
「ああああんた自分がなにいってるか分かってんの?!」
「分かってるっつーのそんぐらい。だからさ、そのお試し期間中に俺のこと好きになったら、そんまま付き合えばいい話じゃん?」
再び硬直した私の姿を『その話に同意した』と見なしたのか、リクは自分のポケットに手を突っ込み、すたすたと先へ行ってしまった。
ちらりと見えたリクの耳がほんのり朱に染まっているのが見えた私は、『私も好きだ』って言葉が出てこなかった自分自身を嘆いた。
その日は、珍しく雪が降っていた。
いつものようにリクと帰っていた私は、少しだけ商店街の方を回りたい、と伝えた。
「はあ?なんで商店街なんだよ?」
「友達の誕生日が近いから、プレゼント買いたくて…」
だめ?と言うと、ったく、とぶつぶつ文句を言いながらも付いてきてくれた。
初めはぎこちなかったこの関係も、今ではすっかり慣れてしまっている。
本音を言うと“お試しの恋人関係”では無くて、“ホンモノの恋人関係”になりたいのだけれど。
でも、今の関係が続くならそれもそれでいいかな、なんて思っている自分もいて。
そんな矛盾を抱えながら、私は今日も他愛の無い話題提示をするのであった。

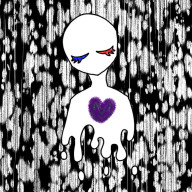





















編集部コメント
主人公は鈍感で口下手ではあるものの『コミュ障』というほどではないので、キャラの作り込みに関しては一考の余地があるものの、楽曲テーマ、オーディオドラマ前提、登場人物の数などの制約が多いコンテストにおいて、条件内できちんと可愛らしくまとまっているお話でした!<br />転校生、幼馴染、親友といった王道ポジションのキャラたちがストーリーの中でそれぞれの役割を果たし、ハッピーな読後感に仕上がっています。