「……っ!」
ビクッとして我に帰った。
辺りには雪がしんしんと積もっていて、いつも通りの帰り道もすっかり銀世界になっている。
…何故だろう。
何度もこの景色を見た気がする。
はあはあと息をする度、私の目の前の空気には白い息が現れる。
「…おい、マキ?どうした?」
私の不可思議な行動を怪訝に思ったのか、リクが声をかけてきた。
「ううん、大丈夫。ただ…」
「ただ?」
「……なんか、とても悪い夢を見た気がして」
「ぶはっ、お前、寝てたのかよ!」
「ちょっ違うし!」
「まあ、珍しく真剣な顔してたしな!雪でもふんじゃねぇ?あ、もう降ってるか!」
お腹を抱えて笑うリクに肘鉄をお見舞いする。
ぷるぷると無言で震えるリクを横目に、私は話題を変える。
「今日さ、商店街の方寄ってもいい?」
「……なんで」
「友達の誕生日が近いから、プレゼント買いたくてさ」
「……えー」
「それとも、も1回これ喰らいたい?」
ニッコリと笑いながらさっきリクを殴った肘を指差す。
何か言おうとしていたリクも、それを見て『…好きなだけどうぞ』と了承した。
…このやり取りも一体何回目になるんだろう。
商店街を回っている間、私たちは他愛の無い話を続ける。
「リクって友達の誕生日とか気にするタイプなの?」
「……俺が、そういう風なタイプに見えるか?」
「あー…なんとなく分かるわ」
「…でね?そのときゆいちゃんがさ、リクのこと『カッコいい』って言ってたんだよ!やばくない?」
「…ふーん」
「ちょっと、聞いてる?」
「あー聞いてる聞いてる」
「もーちゃんと聞いてよね!」
「はいはい」
「…でも、ゆいちゃんも物好きだよね。こんな野性児のことカッコいいって言うなんて」
「んだと?喧嘩売ってんのか?」
「そういうところが野性児なんだって」
少し歩いていると、私の行きつけの雑貨屋さんに着いた。
店内には新発売の商品も並んでいて、私は端から端まで眺めていた。
はっとして1つのカラーペンをとると、リクの方へ向かう。
「ねえねえ見て!これ可愛くない?」
リクはちらりと私の手元を見ると、頭を掻きながら、
「あー…別にどれでもいいんじゃね?」
と言った。
私はリクの返答に頬を膨らましながら、他のコーナーもみて回ることにした。
「あ、これもいいかも!いや、でもこっちかなぁ」
私がぶつぶつと一人言を言いながら商品を選んでいたら、飽きたのかリクはイライラした口調で、
「別になんでもいいから、さっさと決めろよ」
と言ってきた。
その一言が、私の逆鱗に触れた。
「ちょっと、何よその言い方!そんなこと言うなら先に帰っててください!」
ストレスが溜まっていたのも原因の一つかも知れない。
だが、今の私はそんなこと原因の解明なんか後回しだった。
とにかく、目の前の男の発言が気に入らなかったのだ。
「もう知らない!」
そう言い捨てると、私は商品を置いて店の外へ飛び出した。
「っちょ、おい待てよ!」
リクも慌てて外へ飛び出す。
必死に走るが、所詮は女子と男子。
後から追いかけてきたリクは、すぐに私に追い付いてきた。
「おい、ちょっと待てよ!」
「付いてこないでよ!」
嘘だ。
本当は付いてきて欲しいから外へ飛び出したのに。
リクが追いかけてくれたことが嬉しいのに。
「お前一人にしたら危ねーだろ!」
「うっさい!ほっといてよ!」
違う。
リクがらしくもないことを言ってくれて嬉しいのに。
本当は放っておいて欲しくもないのに。
そんな私の本心は、風と共に掻き消されていく。
伝わることのない想いに耐えかねた私は、商店街の裏道を使ってリクを撒いた。
大通り前の路地の立て掛けてある看板裏に隠れると、私は乱れた息を整えた。
段々治まっていく呼吸に、今度は涙が溢れだした。
「ったく、なんなのよあいつ………!」
もういやだ。
自分の言いたいことすら伝えられない自分に腹が立つ。
さっきだって、リクに腹が立ったのも事実。
「でも、今のは私も悪かったかも……」
“悪かったかも”じゃない。
私が“悪かった”んだ。
リクの返答にあそこまでキツイ発言をしなければ、こんな風にはならなかったはず。
「…リクに、謝らなきゃ……」
そう思った時だった。
「っ…やっと見つけた…!」
突如聞こえた第三者の声に、私はすぐさま振り向く。
そこには、汗だくになって呼吸を整えるリクの姿があった。
「!ねえ、さっきは」
『さっきはごめん』
そう言うつもりだった。
激しいブレーキ音と共に辺りが暗闇に包まれる。
身体中が痛くて仕方が無い。
そっと目を開けると気がついた。
私がリクに抱き抱えられていることに。
顔が熱くなって、なんとか腕から脱出しようと試みる。
しかし抱き抱えている力が強く、中々出られない。
恥ずかしさに耐えられなくなった私は、『~っもう!』っと言いながら思いっきりリクの頬を叩いた。
ひんやり、とリクの“低い”体温が手に伝わる。
返答はない。
何か嫌な予感がする。
私はなんとか無事そうだったスマホを手繰り寄せ、リクをライトで照らす。
リクは、傷だらけだった。
サァッと血の気が引いていく。
「リク!?リク!しっかりして!リク!」
何度呼び掛けても、返答が来ることは無かった。
「…なんで、リク………」
ポロポロと涙がこぼれていく。
「……なんで毎回、私を助けてくれるの……?」

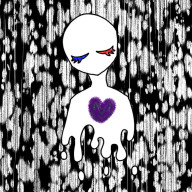

















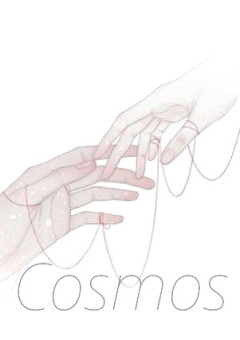
編集部コメント
引きこもりのおじさんと真面目な女子高生という組み合わせがユニーク。コンテストテーマである「タイムカプセル」が、世代の違う二人をつなぎ、物語を進めるアイテムとして存在感を発揮しています。<br />登場人物が自分の過去と向き合い、未来に向かって成長していく過程が丁寧な構成で描かれていました。