前の話
一覧へ
「シャバの空気、気持ちいい」
新緑が揺蕩う頃、男は刑務所を出ると、脳の中での記憶を呼び起こすように言葉を発した。
「きーらーきーらーひかる・・・」
尖ったデザインのギターをもつ指が激しく動いて、煌々と焚かれた照明。夢が目標になる手前で負けた。
「お疲れ様です」
ステージ裏の控室に戻ってきたコウは、マネージャーにわざと聞き取りにくいように言葉を吐く。人に顔を見せたくないのか、フードを被り下を向いている。控室と、ステージ上での素振りの違いがテレビや、週刊誌に「ギャップ」として映ることはこれまで一度もない。冷静で落ち着いてる様子をメディア側が密着したがる「本性」として、彼は決して表に見せない。見せるための本性もないのだ。
そうすると当然、このギャップを観客が知ることはなく、周囲の関係者たちはこのギャップで女もイチコロなのにと落胆するのであった。しかし仕事柄、その「周囲の関係者」に含まれる女たちは、みなコウにすがった。彼は確かなる優しさを奥底に持っていた。その優しさは非常袋のようで、どうしても必要な時にだけその優しさを使われた。
地下のライブハウスの控室のソファで、コウは夢の中に潜る。ライブが終わった後の女の騒ぎごえコウの夢を邪魔する。
「今日何人入ったの?」
「60です」
「この箱、いくつ入るんだっけ」
「車椅子客含めて95です」
コウは夢から覚めた一寸にも満たない時間で、二言喋る。そしてまた睡眠へと陥るが、この場所で寝れないとわかると身支度を始めた。
「お疲れ」
地下のライブハウスの階段をゆっくりと登り、地上に出る。
「シャバの空気」
黒いジャージのフードを被り、数軒の飲み屋の前を通りネオンが光る夜の街に出る。
「バー・ドッグス」
70年代物のお酒が棚に陳列し、メニューもジャズ音楽の名前で作られたカクテルが並ぶ。
「『little girl blue』で」
コウは、バーテンダーにゆっくりとした口調で頼む。酒と薬に溺れてこの世を去った歌手ジャニスジョプリンの名曲をもとにして作られたカクテル。
「今日もお仕事だったんですか」
バーテンダーは、世間に顔が知られているコウの仕事をいかにも知りませんという顔をして聞く。一人の女性店員がレコード盤を入れ替える。
「ありがとうございます」
コウは、いつの間にか店のBGMが「little girl blue」に変わっていることに気づくと小さな会釈をする。
目の前に運ばれる緑色のカクテル。グラスの淵に飾られたライム。コウはグラスを口につけ、静かに喉を鳴らす。遠くの数十個並ぶテキーラのボトルを眺めながら、今日のステージを脳内で再生していた。コウは全てをはっきりと覚えている。そんな脳内再生が盛んな時。
コウの左側で風が揺れ動く感触がした。直接は触れていなくとも、空中で感じる空気の揺れ動き。大昔にアインシュタインがひらめいた、時空の原理で無重力が一瞬歪むような、そんな空気の違和である。あらゆることも感じとるコウには、それが特に敏感に感じられた。
それも、カオリには余計に。
「お疲れ様」
コウの横に座るカオリが言った。途端に椅子のベロアの布が軋む。
「何飲む?」
カオリはメニューを眺めながら、上から3番目に書いてあった「」をさした。
コウはその瞬間ポケットに手を突っ込み、手を動かすと何かを掴んだまま、カオリの手を握った。数秒間握られた手はどこか分厚い。カオリは手を離すと、自分のポケットに手を入れる。
「足りてる?」
「困るほどではないわ」
「ふーん」とコウは鼻と顎を鳴らす。全て薬物の話だった。カオリはメニューを指す場所で、欲しい薬物の量を伝える。カオリはかつて歌手をめざしていた。しかし現実と夢との乖離、親友の役者を失くしたことを機に重い精神病を患った。歌手をやめた後も心に残った強いストレスから、彼女はクスリの力に頼らざるを得なかった。
酒とタバコに蝕まれた男女は酒を飲むことで、別の人間として生きることを娯楽とする。酒を飲むことが娯楽ではない。酒を飲んで別の誰かに憑依することが娯楽なのだ。
「今日お家誰かいる?」
「いる」
驚いたようにコウは一瞬グラスを持つ手を止める。
「猫が」
カオリは口を抑えて小さくふふっと笑う。コウは下唇を噛みながら舌打ちをし、カオリの手を握る。
「美味しい紅茶の淹れ方教えてもらったの」
コウはフンッと小さく鼻で微笑を浮かべ、フードを前頭部が隠れるように被って、カオリを引き連れて店を出た。カオリのアパートの一室のドアを開けた途端に、そこは社会ではなくなった。流れるように事なきことを終える。コウはベランダでキャメルのタバコを咥えながら、街灯をステージの照明のように見立てる。煙の揺れが、自分の疲れと魂の抜け具合を可視化しているようで妙に背中が痒くなる。後ろからカオリが意識半分の声でコウの名前を呼ぶ。コウはそれを聞き流す。まるで観客が自分を呼ぶ時みたいに。 するとぴたりと、タバコを吸い続けるコウの手が止まる。コウははっきりと開いているとは言えない目の開き具合で水中で目を開けた時のように視線の先をぼんやりと見続ける。
視線の先にあるのは、幼女であった。自我を持ち歩き、人間としての意識が芽生えるような年頃であろう。そしてまた幼女の視線の先にあるのもコウの痩せこけた顔であった。
タバコの火を消すのにも、サンダルを履くのも、数十分前にカオリと一緒に入った家の扉を開けるときに彼女が女として呼ぶ声も、コウには全くとして耳に入っていなかった。
そして気がつくと、コウは幼女の手から土をはらっていた。幼女は、そのままコウに手をとられながらカオリの家まで階段を上がっていく。幼女の母親の様子や、家庭環境、今この時間に彼女が外にいるまでの事柄に思考が回ってしまう。全て雑念として入ってくるこの思考に、コウは苛立ちさえ覚えた。自分を捨てた母親を思い出す。
「おふろにはいろう」
彼女の身辺状況はどうでもよかった。彼女の「衣食住」を数時間だけでも確保せねばと考えたのだ。この年の子供からすぐ目を離すと、命に危険が及ぶことぐらいは学びの功がなかったコウでさえ察しがついた。少女は、一人でシャワーを浴びることを選んだ。
「明日、起きられる?」
少女の首が左右に動く。
「また明日、答え合わせしようか」
言葉の理解が日常会話程度に及んでいない彼女を鑑みて、その日まともな会話をすることはなかった。そして夜が明けたときには、夜の平穏は消失していた。静けさの中を生きていたいコウにとっては、耐えることのできない音が翌朝生まれていた。
「何よあんたいつからいるの」
寝ぼけているのか、視界がぼやける。子供が見える。昨日のことははっきりとは覚えていないが、夜更けに公園の前を子供の手を引いて歩いた記憶と手の感覚ははっきりと残っている。そして、今カオリが子供に怒声を浴びせているのもはっきりとわかる。カオリと子供の間だけ、まるで大雨が降っているようだ。幼女はまるで自我しかない生き物のように、カオリを非静物として見ている。さっきまで寝ていたカオリがこんなに動くものだから、この女に電源が入れられたとでも思っているのだろう。
「出よ」
コウは一言冷淡に言葉を放つと、幼女を抱きかかえて玄関を出た。カオリの怒声は、案の定コウに向いた。知らない誰かがいることへの恐怖を通り越した怒りをカオリはぶつけていた。
「吸ってろ」
容赦なくコウは、カオリにそう言い玄関を出た。幼女は、コウに小さな手を引かれながら、足のピッチをコウに追いつく。ゴミが散らばる朝10時の歓楽街に、通勤途中のサラリーマンや、子供を後ろに乗せて自転車で走る母親の様子が雑に混じる。レンタサイクルに乗って走る派手髪の女もたまに横を通り過ぎる。時々未処理の嘔吐もある。
厚い雲の下。人の流れに逆らいながら二人は前に前に進んでいく。野良猫を起こさないようにしているのだろうか。コウは2,3の裏路地を忍び足で通る。
「ここ、コウのいえ」
「喋れるのか」
幼女は玄関に突っ立ってコウを見続ける。コウはその日幼女に飯を作り、風呂に入れた。着替えはなかったため、コウのTシャツを着せた。
「おやすみ」
幼女はその日1日の体力の消費期限を迎えたように、ぐっすりと寝た。
あさが来た。
「これコウの顔」
幼女の手には、リモコンがある。コウは幼女の指を差すテレビに目をやると、こめかみあたりがズキズキしてきた。
「歌手KO、薬物売買」
アナウンサーが使い慣れた言葉を一部則れば、今朝の新聞の一面が歌手のKOで埋め尽くされている。それからコウは、すぐにカオリに電話をかける。
「おい、お前だろ。情報漏らしたの」
コウは落ち着いていた。焦りと屈辱。
「えー何。言うわけないのに」
電話越しに聞こえるのは、干からびた笑い声だった。小雨がベランダの物干し竿に降りかかる。
遠くから何やら大音響がする。大音響は時間が経つにつれてよりより大音響となる。その変化と共に、部屋の中が冷え、幼女の目線をグッと感じる。こめかみのズキズキがさらに痛む。
それから5分もしないうちだっただろう。コウの家に入ってくる警察数人。
何も言えずつれていかれるコウ。幼女はひたすらコウが手を引かれる様子をじっと見る。
それから出所したのは、数年後だった。コウは街の中華屋で腹ごしらえをした後、ライブハウスに向かう。表には行列ができ、少女の顔が載ったポスターが貼られている。
「キラキラひかる...」
都会のハズレの、非行少年が集まるようなコンビニの近くにあった。一人の少女が声をかすらせて歌っている。
「ありがとうございました!またね、コウでした!」
自分のことをコウと連呼してギターを持って立ち続けるその少女。去り際に観客席の端を見ながら、口を動かした。あ、え、あと口を動かした。
「待ってた」
コウはコウが舞台から完全に消えるまで、目を離さなかった。



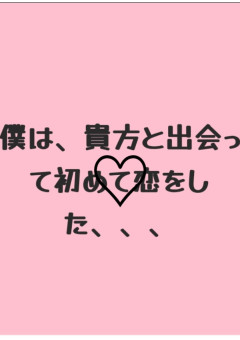












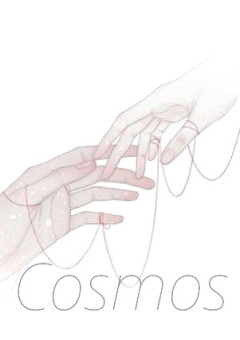

編集部コメント
引きこもりのおじさんと真面目な女子高生という組み合わせがユニーク。コンテストテーマである「タイムカプセル」が、世代の違う二人をつなぎ、物語を進めるアイテムとして存在感を発揮しています。<br />登場人物が自分の過去と向き合い、未来に向かって成長していく過程が丁寧な構成で描かれていました。