カラスの鳴き声が聞こえる。イルミネーションが輝く。遠くに夕陽が見える。
12月のはじめ、俺は一人街を歩く。
「僕の話を聞いてください」
クリスマスシーズン真っ只中の街は様々な装飾のおかげで無駄にキラキラしている。それに加え周りにはカップル、カップル、またカップル……鬱陶しい。俺には眩しすぎる景色に目眩までする。俺はこの季節が嫌いだ。
「聞いてくださいってば!!」
騒がしいしうるさいし迷惑だし……
「ねぇぇぇもぉぉぉ無視しないでくださいよぉぉぉぉ」
いや、
「さっきから何なんだよお前!!」
ずっと俺の後ろから大声で呼びかけてくる不審者。髪も眼も服装も、彼の体の大部分は黒で構成されている。故に、不審だ。
「お、やっと気付いてくれましたね」
「いや、前から気付いてたから……ほんと何なの?」
こんなに付き纏ってきたんだから、何か大事な話なんだろう。俺こいつのこと知らないし、何を話されるのか検討もつかないけど。
「サンタクロースって、信じてますか?」
「は?」
「え、サンタクロース、知らないです?」
「いや、それは知ってるけど」
「知っていますよね、じゃあ大丈夫です」
「え、何が」
「助けて頂きたいのです」
「はい?」
「サンタクロースが、消えてしまいそうなんです」
「さようなら」
最近、子どもたちがサンタクロースの存在を信じなくなっています。このままでは本当に、サンタクロースは消えてしまいます。サンタクロースは子どもたちが信じるから存在できる。だから、子どもたちにサンタクロースを信じてもらえるようにしないといけません。それを、あなたに手伝っていただきたいのです。
突然変なことを頼んできたそいつはコルネイユという名前で、フランス語でカラスという意味らしい。お洒落でしょう?と笑う顔は不審な見た目に反して無邪気だった。よく見ると顔立ちも整っている。服装も、綺麗なスーツ、燕尾服だろうか。後ろが長い。そして真ん丸な眼鏡をしている。何というか、執事、というような見た目だ。
「手伝っていただけますか?」
俺の顔を真っ黒で、そして、キラキラとした瞳で見つめてくる。あまりにも純粋な瞳で見つめられ、
「少し」
俺は、
「少しだけだからな」
嫌とは言えなかった。
クリスマス当日まで、そいつ、コルネイユとの同居生活が始まった。どうせなら、女が良かったな、なんて思っていると、コルネイユは俺の顔を覗き込みながら、
「男じゃダメだったんですか?」
なんて問いかけてくる。コルネイユは不思議だ。その真っ黒い瞳で心の中を見透かしているみたいな、そんな感じ。悪魔みたいだ。
「あながち間違ってないですよ」
「え?」
「僕は夢とかを守ってる、守り神?みたいなものなんですけど」
サンタクロースに続き、信じられないような話を当たり前のように話す。
「人の夢の中に入れちゃったりもしますし、コントロールも、しようと思えば出来るんで、まぁ、悪魔みたいなものですよね」
そう言い、困ったように笑う。
「あ、サンタクロースに子どもたちの欲しいものを伝えるのも僕の仕事なんですよ!」
「はいはい、そーですか」
「あー!信じてないですねその顔は!」
「信じてる、信じてるよー」
「嘘ですね、僕にはわかるんですよ!」
「あーもう!そんなことはいい!それより、どーするんだよ、サンタ」
「あ」
「あ、じゃねぇよ……まったく」
「大丈夫です、僕の力を使えばサンタは助かります」
「それ、俺必要か?」
「まあまあ、そんなこと言わないでくださいよ」
僕なら、子どもたちの夢の中に入り込み、夢をコントロール出来ます。そして、サンタクロースは本当にいると信じてもらうんです。
クリスマスがどんどん近付いてくる。同居生活にも慣れてきた頃。俺とコルネイユは真夜中二人、他愛も無い話をしていた。それはクリスマスの事なんて忘れて、ただ、笑い合えた時間。
「ほら、寒いだろ、これ飲め」
「ん、なんですか?これ」
「ホットミルクだよ、あったまるから」
「わあ、ありがとうございます、ん、甘い」
「お前、甘いもん好きだよな」
「はい、甘いものって、なんか、心が温まりますから」
「ふぅん、まあ、なんかわかる気がする」
「僕、このホットミルクが一番好きです」
「んえ?なんでだよ」
「これ、他のどんな食べ物や飲み物よりも、あったかいから」
「…………そうか」
暗い部屋の中、橙色の光が二人を照らした。マグカップからふわりと立ち上る湯気もまた、輝いていた。
クリスマスがもうすぐそこまで迫っている。作戦決行だ。
「作戦決行中は、僕眠っちゃうので、その間は静かにしててくださいね」
「ふ、静かになんて、お前に言われたくないな」
「どういうことですか!」
「なんでもない、ん、はよ寝ろ」
「結構時間かかりますから、自然に起きるまで放っておいてくれて構わないですからね」
「はいはい」
とか言って、ずっと見守ってたりしそうですね、なんて笑い、コルネイユは、眠りについた。
それが、最後だった。
クリスマスが過ぎ、大晦日も過ぎ、あけましておめでとう、という挨拶が飛び交っても、コルネイユは目を覚まさなかった。
「いつまで、寝てるつもりだよ……」
ベッドの横に座り、コルネイユの顔を覗き込む。穏やかな表情だった。呼吸は、あるのかもわからない。そもそも元から生きていたのかもよく分からなかった。
目の前に、一羽のカラス。じっとこちらを真っ黒な瞳で見つめてくる。
「コルネイユ」
俺は自然とそのカラスをそう呼んだ。
「バレてましたか」
カラスはふわっと飛び立ち、そしてその直後にはいつもの、人の姿で俺の目の前に立った。やっぱり、そのカラスの正体はコルネイユだった。否、あれが元の姿だろうか。
「なんで」
聞かずにはいられなかった。
「なんで目覚めないんだよ、帰ってこいよ」
「ごめんなさい」
「なんでだよ」
「ちょっと力を使い過ぎちゃいました」
「いつ帰ってくる」
「もう、帰れません」
「は?何言って」
「僕みたいなのは、人間の世界に来てはいけないと、掟があるんです」
「掟を破ったら、どうなる?」
「この世から消されます」
「な、そんな、意味が分からない」
「さようなら、楽しかったです」
「待て、駄目だ、行くな」
「ホットミルク、美味しかったです」
「まて、」
「二人で過ごした時間は、僕にとって最高のクリスマスプレゼントでした」
「いかないでくれ……!」
「僕のこと、忘れないでくださいね……」
「いやだ、いくな!」
「僕だって!……っ!僕だって、ほんとは消えたくない……ずっと一緒にいたいです……」
「なら……」
「でも無理なんです!……掟なので……だから、せめてちゃんとお別れしないと、って思って、最後に、ここに来ました」
「……」
「僕のこと、忘れないでいてくれますか?」
「……っ!あたりまえだ!お前みたいな変なやつ!忘れるわけがねぇだろ!お前が嫌だって言うほど覚えておいてやる!信じてやる!」
「……良かった、それならきっと、僕はあなたの夢の中で生き続けられますね」
安心したように笑い、瞬間、コルネイユは消えた。
窓から陽の光が差し込み、朝だと気付かされる。いつの間にか寝てしまっていたようだ。不思議な夢を見ていた気がする。ふと、ベッドの上に目をやると、それまでそこに眠っていたコルネイユがいなくなっていた。そしてその代わりに真っ黒な羽根が一枚、そこにあった。
それから何年か経った冬。またあの季節。
「ママー!サンタさんくるかなぁ!」
街の至る所からはサンタクロースを信じる子どもたちの明るい声が聞こえた。あいつが、サンタクロースを信じさせたのか。サンタクロースは助かったんだろうな。あいつは。あいつは消えてしまったけれど。でも、俺の中では今も生き続けているんだ。懐かしい無邪気な笑顔と、真っ黒な瞳は脳裏に今も焼き付いたままで。
「コントロールされてたり、なんてな」
カラスの鳴き声が聞こえる。イルミネーションが輝く。遠くに夕陽が見える。
12月のはじめ、俺は一人窓辺に座る。
今日も寒い。そうだ、ホットミルクを飲もう。あいつが好きだと言ったホットミルクを。甘くて温かい、ホットミルクを。






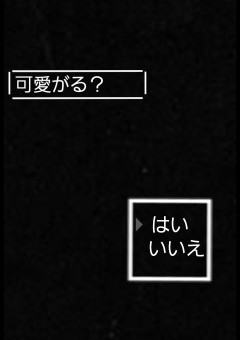














編集部コメント
主人公は鈍感で口下手ではあるものの『コミュ障』というほどではないので、キャラの作り込みに関しては一考の余地があるものの、楽曲テーマ、オーディオドラマ前提、登場人物の数などの制約が多いコンテストにおいて、条件内できちんと可愛らしくまとまっているお話でした!<br />転校生、幼馴染、親友といった王道ポジションのキャラたちがストーリーの中でそれぞれの役割を果たし、ハッピーな読後感に仕上がっています。