12)
「……亡くなった?」
「ええ、彼女は高校3年の冬に事故に遭って……。日生 椿。それが末吉の彼女の名前です」
と、写真をひっくり返して雛子へと差し出した。写真の裏側には、写真に写るメンバーの名前が刻まれていた。日生椿の名前が拓海の隣にある。
「日生椿さん……」
と雛子は拓海の彼女の名前を反芻する。
「末吉と日生さんは高校1年の時から同じクラスでした。高1の時から2人は付き合ってて、高校3年の末吉の受験日前日に事故に遭い、亡くなりました」
「そんな……」
「その後の拓海は凧の糸が切れたみたいに進学もせず、海外に行ってしまったんです」
「それで俳優になったんですか」
”日生海”という、日生椿の苗字をとった拓海の芸名は偶然じゃない。
拓海の意志で、その名を名乗ることを選んだのだろう。
「ええ、帰国するまでは精力的に仕事してたんじゃないんでしょうか。ただ、1年前に帰国してからというもの、ずっと家に篭りっきりになってしまって…」
「それって。どういうことですか? 日本に帰ってきたら、心が壊れたってことなんですか?」
雛子の疑問に加賀美は言葉を続けた。
「きっかけはタイムカプセルです。去年、湘栄祭の時期にタイムカプセルを開けるために同級生たちが学校に集まったんです。その同窓会に、帰国した末吉も参加したのですが。同級生の有志のメンバーが日生の追悼も兼ねて、学祭で吹いた日生のフルート演奏の映像をプロジェクターで流したんです。それで末吉が倒れて……」
雛子は突然、拓海が倒れた時を思い出した。雛子にとっては気にもとめないことが、拓海にとっては、辛い過去が襲ってくるトリガーだった。雛子は自分の無神経さに唇を噛み締める。
「過去の映像を見たことで、彼女を失った時の感情が戻ってきてしまったんでしょう。
ずっと抑え込んでいた感情が溢れてしまったせいで、末吉は再び彼女の死に向き合わなくてはならなくなってしまった。そんな不安定な心の状態で、タイムカプセルを開けることは難しいと思っていたのですが。受け取りたいと末吉が言い出して……。
それで黒川さん。あなたに末吉へタイムカプセルを渡すように頼んだんです」
過去と再会する。拓海にとって、それは時間をかけてようやく癒えた傷をもう一度抉るようなものなのだろう。苦しくて辛い日々を思い出して、心が壊れても、開いてしまった箱は、2度と閉じることはできない。あのタイムカプセルのように亀裂だらけになってバラバラになる拓海の心臓を想像してしまい、雛子は息が苦しくなった。
「……でも先生、どうして先生が渡さなかったんですか?」
と尋ねると、加賀美が悲しげに目を細めた。
「怖かったんです。恋人の死を引きずって苦しんでいる友人を見るのが……。タイムカプセルを開けたら、末吉が壊れるんだったら、私の手でタイムカプセルを壊したいぐらいでした……。日生椿との思い出が末吉を過去へと引き摺り込むなら、いっそ……」
「先生……」
「きっと私も末吉と同じなんです。10年前に大事なものを失ってしまったから」
「それは……」
と尋ねかけて、雛子はためらった。もし想像通りなら、苦しんでいるのは拓海だけじゃない。いつもにこやかな笑顔を浮かべる加賀美が胸の中にしまっているのは、拓海と同じ暗い世界の思い出だとしたら……。
ぎゅっと拳に力を込めた。
スカートのポケットの中で煩いほどに振動するスマホを取り出し、電源を切る。
「開けましょう」
力を込めて雛子は言った。
「え?」
と加賀美が疑問符を雛子へとぶつけた。
「タイムカプセルを開けましょう!」
「しかし、末吉は——」
「分かってます。彼女の写真を見るだけで倒れるぐらいやばい状況だって。だからって捨てるってないです。だって10年も待ってたんですよ。日生椿さんだって会いたいんです。過去の自分に触れて欲しいんです。だから笑顔でタイムカプセルを開けられるように、私がなんとかします」
バスのなかで流れたフルートの音色、閉じ込められた白い光の少女。
彼女は今もタイムカプセルの中にいて、拓海に再会する事を待っている。
”見て”
そう雛子へ訴えた彼女の想いを焼却炉に放り込むなんて、できるはずがない。
「タイムカプセルを開けましょう」
*
【拓海side】
フルートの音色が聞こえる。
瞼を閉じると鳴り響くメロディ。
その音色は消え薄れることなく、彼女を失った日から今もまだ鮮明に僕の耳を揺らし続けている。彼女が、あの丘で吹いていたあの曲が……ずっと……。
*
フルートの曲が不意に止まった。日生椿がフルートの先でコツンと僕の頭を叩く。
「拓海? 寝ちゃった?」
「寝てないよ?」
と僕は本をずらして顔を持ち上げた。春の陽気を吸った心地のいい風が流れている。
大きな夕陽が雲のない空に浮かんでいた。橙色の光を浴びた椿の髪が金糸のようにサラリと流れる。その柔らかな舞いに目を奪われる。椿は流れた髪の束を指先で直して耳にかけながら、僕を見て、ちょっと怒った様子で口角を引き上げた。
「嘘、絶対寝てた。ちゃんと録れてた?」
「うーん、待ってね……」
と、起き上がりながら停止ボタンを押す。スティール製のスティック型のボイスレコーダーを椿へと差し出した。椿はいつも自分の演奏をボイスレコーダーに録っている。毎日毎日、飽きもせず自分の演奏を録音しては消すを繰り返す。
「毎日録って、意味あるの?」
「あるの。日によって聴こえる音の色が違うんだよね、自分が奏でる音を客観的に知っておきたいじゃない?」
「だからってここじゃなくても、音楽室とかの方が良くない?」
「ここがいいの」
「ふーん」
ベンチから立ち上がり、制服のワイシャツについた木の葉や土を手ではたいた。砂が多いのは、すぐそばに砂場があるせいだ。昼間は子供達で賑わっていたのだろう。プラスティックのスコップやバケツがいくつも忘れられて砂場の中に残されている。
「それに音大合格したら、脱ガラケーするんだ。それまではボイレコで我慢かな」
「おおー、スマホデビューかよ」
「いーでしょ、羨ましい?」
「ドラクエがスマホで遊べるようになったら、ちくしょう! 羨ましい! って言ってやる」
「ふふっ。君はお子様だね」
ピピピとアラームが鳴り、椿は慌てて携帯を取り出した。その小さな画面を見るなり、握りしめていたフルートを持ったまま立ち上がる。慌ててケースに入れる彼女の様子をぼんやりと眺めた。
「もうこんな時間、ゆっくりしすぎた」
「レッスンだっけ?」
「うん。ごめん先に帰るね。あ、明日の予定覚えてる?」
「なんだっけ?」
「買い物付き合ってって言った。13時に駅前!」
「はい、はい」
「明日こそ、遅刻しないでね」
「わかった、わかった」
「約束だよ」
「はい、はい」
*
結局、僕はいつも通りに遅刻して、彼女を30分近く待たせた。
「君はいつも遅刻するね」
「ごめん、いやあ、何を着ようか迷っちゃって」
「本当?それで、その格好?」
「ごめん嘘ついた。適当に着てきた」
「やっぱり。これ後前逆だよ?」
と、トレーナーの首元を椿が引っ張った。
「後で直すわ」
「もうっ。普通は彼氏が待ちくたびれてるはずなんだけどなー」
と椿は頬を膨らませる。
「僕らの普通は、彼女が待ち人だね」
「君の普通は、みんなの特別なんだよ。この私を待たせる人なんて拓海だけだからね?」
「はいはい」
音楽ショップで新しい楽譜をゲットした後、帰り道を歩く。椿は新しい楽譜を手にして上機嫌でステップを踏む。ガヴォットみたいに明るい曲が彼女の頭の中で流れているのか、まるで鍵盤の上を跳ねるように横断歩道を渡り、音符を描くように腕を大きく躍らせる。
黒いパイプのガードレールは五線譜で、彼女のスニーカーが影を踏むたびに楽しげな音が鳴る。この曲にタイトルをつけるなら、どんなタイトルがふさわしいのだろう?
続いていくメロディの中、飛び跳ねる椿の背中を眺める。
それは永遠に続く曲で、僕はその曲をいつでも聴けると思っていた。
僕はいつだって彼女の観衆(オーディエンス)でいたから。
彼女が壇上から降りることはないと思っていたから。
——けれど突然、思いがけない形で椿が奏でる曲は止まった。























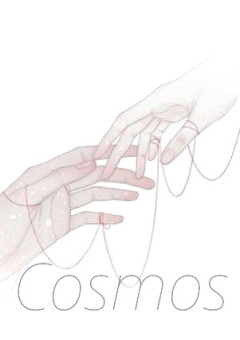
編集部コメント
主人公は鈍感で口下手ではあるものの『コミュ障』というほどではないので、キャラの作り込みに関しては一考の余地があるものの、楽曲テーマ、オーディオドラマ前提、登場人物の数などの制約が多いコンテストにおいて、条件内できちんと可愛らしくまとまっているお話でした!<br />転校生、幼馴染、親友といった王道ポジションのキャラたちがストーリーの中でそれぞれの役割を果たし、ハッピーな読後感に仕上がっています。