ふわふわとした空気感の二人に案内され、本部へと足を踏み入れる。すると金井さんがこそっと耳元に口を寄せて来た。内緒話かと耳を澄ませると、少し申し訳なさそうな声で、
「悪い、俺と薫はちょっと離脱するよ。仕事があってな」
「あ、はい、わかりました」
軽く頭を下げると、金井さんと神屋坂さんは一礼をして階段を駆け上がっていった。金井さんは別として、神屋坂さんは明らかに幹部の二人と俺、別々に頭下げてたな。本当に律儀な人だ。
三井戸くんに手をひかれ、入口正面にあるエレベーターに乗り込む。階を選ぶボタンが並んでいるのだが、ビルが高すぎて数字が凄いことになっている。
「……えっと、23階です」
三井戸くんが困ったように見上げてくる。そうか、三井戸くんでは届かないのか。昭原さんがクスリと笑ってボタンを押してくれた。三井戸くんは頬を少し膨らませて、その小さなイタズラに抗議の目を向けている。
「なんですぐ押してくれないんですか、ウメさんのいじわるー!」
「ごめんの、かわいぐって、ついな」
口元を手に当てて、上品に笑う。その仕草や言葉使いからは、この人がただの女性じゃないことを思い出させてくれる。いや、ただの人じゃないって言うか、若返りまくってると言うか。
増す増す頬を膨らませる三井戸くんに、こちらまで暖かな気持ちになる。思わずつつきたくなってしまったが、昭原さんに先を越された。
「あんれま、もちもちだこと」
「やめてくださいよ!ぼく、おこってるんですから!」
ぶんぶんと首を振って、昭原さんの手を払いのける。帽子が落ちそうになるのを、バレないようにそっと支えてあげた。
ポン、と目的の階に到着したことを伝える音がして、三人同時に顔を上げる。ドアが開いた先には、綺麗に掃除された廊下が広がっていた。
三井戸くんがいの一番に飛び出し、少し先に進んだところにあるドアの前でぴょんぴょんと飛び跳ねている。すっかりご機嫌のようだ。
「ここですよ!ここが、あなたさんのお部屋ですっ!」
と、大きな身振りでこちらを呼ぶので、自然と足が速くなってしまう。部屋の前に来ると、三井戸くんがぐっと力をこめて、ドアを開けてくれた。
決して広いとも言えないが、狭いわけでも無い一室。白いカーテンが取り付けられた大きな窓に、同じく白を基調とした家具の数々。独り暮らしをするには、いっそ贅沢と言えるほどの設備だった。
「おぉ、なんか凄いな」
素直な感想を吐露する。異常なほどの急展開にも、特に肩ひじを張らずにいられるのは、なんだかんだ優しい職員さんのおかげなのだろう。一通り部屋を見終わると、三井戸くんが袖を引っ張って来る。
「あの、そういえば、つたえわすれていたんですけど」
今まですっかり忘れていました、というような顔をして、少ししょんぼりとした顔つきで見上げてくる。忘れていたことに引け目を感じているのだろう。安心させてあげたくて、目線を合わせつつ、なるべく柔らかな笑顔を浮かべる。
「うん、何かな?」
「あの、あなたさんのご家族なんですけど、ねんのために、スクードのしょくいんさんが、見ていてくれているそうです!」
少し舌足らずな話し方に、内容とは裏腹にどこかほんわかとした気持ちになる。つまり、俺の家族は安全だということらしい。心の隅で気にかけていたことでもあったので、すっと気持ちが楽になった。
「そっか、ありがとう」
「えと、あとは、えっと……」
まだ伝えなければいけないことがあるらしく、帽子をいじくりながらしどろもどろとしている。しばらく考えても思い出せなかったらしく、助けを求めるように昭原さんの方を見た。
昭原さんもその視線の意図を察したらしく、三井戸くんに変わって説明してくれる。
「あのねぇ、ちょっと行かなきゃいけない施設があるだ。能力の研究をしてるとこだべ。忙しくて申し訳ねぇが、来てくれるかの?」
なるほど、と思って頷くと、二人はふんわりと笑った。守ってもらう立場な上、恐らく二人のほうが俺よりも強いのだろうが、守りたいと思わせる笑顔だった。
部屋を出て、研究室があるという階に行くためエレベーターを待つ。軽い雑談をしていると、エレベーターのドアが開いた。
「……あ、何階ですか?」
先に乗っていた女性が、気を利かせて聞いてくれる。『15階、お願い出来るかの』と言う昭原さんの言葉に従って、女の人はボタンを押してくれた。
よく見るとかなりの美人さんで、失礼を承知で少し見とれてしまった。ただ綺麗なだけでなく、はかないような、どこか寂しそうな表情に。
すると、女性は視線に気が付いたのか、ふっ、とこちらを見る。ドキリと心臓が跳ね、何と言い訳したものかと考えていると、女性は驚いたように口を開いた。
「もしかして、相上、くん?」

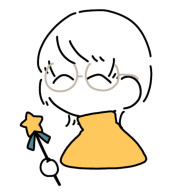


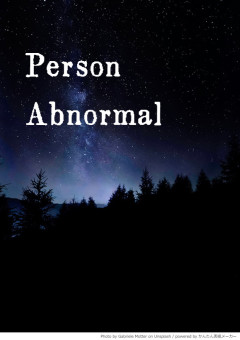























編集部コメント
依頼人の悩みや不安に向き合うカウンセラーという立場の主人公が見せる慈愛にも似た優しい共感と、その裏にひそむほの暗い闇。いわゆる正義ではないものの、譲れない己の信念のために動く彼の姿は一本筋が通っていて、抗いがたい魅力がありました!