「クソッタレ!!何でや、何で勃起(た)たんのや!!」
チュパチュパ。麗子がスケベったらしくワシの逸物を尺八(フェラ)してくれとるのに。
何度目になるやろか、久し振りにワシは麗子の部屋を訪れたのや。うん、確かに呑んだ帰りやが、ワシも歳かも知れんなぁ…。けどや、気持ちがええのや。
「あ、あう…」
麗子がワシの愛撫に顔をしかめているのを見やり、突起した乳首に舌を転がしながら、これでもかと言わんばかりに、麗子の蜜壺に中指で捏ね回したのや。
「うう…、ああうん、パパ、嫌々」
眉を寄せながらよがる麗子の甘味な漏れ伝う声に
「ええのか麗子、ええのか」
「ああ~ん。ハァハァ、パパ、イク。あん、あ…イクイク」
ワシの脳はドーパミンが放物しているのにや、一向に勃起(た)たんのや。挿入(い)れたいのや。ワシは麗子の蜜壺に精液を放ちたいのや。
「いや~っ」
麗子の躰が痙攣を起こしたかのようにブルブルと震え、「シャーッ」と潮を噴いたのや。
なのにや、ワシは麗子の蜜壺に逸物を挿入れることも出来ずに焦れていたのや。
まさかこの男が…、蜜壺にシャワーをあてがい入念に洗いながら、忌々しさを感じていた。
「麗子、ちょっとアッチに行っていてくれ」
黒蝶(店)で最後に飲み交わしたエンジェルスウィング、西岡はアル・カポネに唇を濡らした。
エンジェル・ウイング(Angel's Wing)とは、リキュールをベースとした、ロングドリンクに分類される、カクテルの1種である。
標準的なレシピ
クレーム・ド・カカオ(酒を焙煎したカカオ豆と共に蒸留し、バニラの香りを付けたリキュール) - 1/2
プルネル・ブランデー(スモモを主原料とする醸造酒を、蒸留して作ったブランデー) - 1/2生クリーム - 適量
作り方
いわゆるプース・カフェ・スタイルで作られる。
リキュールグラスにクレーム・ド・カカオを注ぐ。
混ざり合わないようにプルネル・ブランデーを注ぐ。
生クリームを少量浮かべる。
レシピのうち、クレーム・ド・カカオの上のプルネル・ブランデー、生クリームを別々に使うとエンジェル・フェイスになる。
●アル・カポネl Capone
1919年、アメリカで禁酒法が議会で成立。
飲酒を禁止することによって犯罪を抑止しようとする法律である。
1年後の1月17日から法律は施行さたが、その副作用として密売に関わるギャング達が膨大な利益を得るという、皮肉な結果を招いてしまった。
シカゴのギャング達の中で特に権力を握ったのがイタリア移民の子「アル・カポネ」である。
自称家具販売業のカポネは、密造酒製造・販売、売春業、賭博業を統括する犯罪組織のトップになり実質的にシカゴを支配するまでにいたる。
酒の密売についてのカポネのコメント、「俺は人々が望むものを与えてきた。なのに俺に返ってくるのは悪口だけだ」。
世の中についてのコメント、「他人が汗水たらして稼いだ金を価値のない株に変える悪徳銀行家は、家族を養うために盗みを働く気の毒な奴より、よっぽど刑務所行きの資格がある。この家業に入るまでは悪徳政治家など世の中には高価な服を着て偉そうな話し方をする悪党がこんなに多いとは知らなかった」。
やがて脱税容疑で投獄され、出所後には病気で48歳の生涯を終える。
後には選りすぐりの禁酒取締チームを描いた映画「アンタッチャブル」や、「スカーフェイス(彼の愛称)」などのモデルにもなる。
1月17日は禁酒法が始まった日であり、皮肉なことにアルカポネの誕生日でもあります。
レシピ
ジャックダニエル ブラック Jack Daniel's Black30ml
モニカ Monica15m
ディサローノ アマレット disaronno Amaretto15ml
フレッシュ ライムジュース Frech Lime Juice1tsp
シェークしてカクテルグラスに注ぐ。
作者:佐藤 章喜氏/Dining & Bar Beso勤務/大阪市/サントリーカクテルオブザイヤー2001受賞作品
また、禁酒法によって職を失ったバーテンダー達は豪華客船のバーやヨーロッパの酒場に職を求めて移住したりして、カクテル文化を世界に広めるという良い副作用も産み出した。
ククク、動き出しやがった。クク、ククク、ドイツもコイツも。済まないな、麗子。つまらないゲームにお前まで引き込んでしまった。
「いいえ。こうして日本国籍を手にいれ、ましてや」何も言わなくていい。奴は既に狂い始めた。そう、毒に呑まれてな。
数日前。
「どうしたのですか、西岡(にし)さん?」
「村田(むら)さんよ、飛びっきりの情報や。せやから200用意して欲しいのや。いつもの場所で5時やな頼んだで」
グフフ、麗子があれだけ悶えるとは思わなんだわ。しかしや…何故勃起(た)たんのやろか。しかもや、躯にシャブ(覚醒剤)を流し込んだのにや、さっぱり言うことが効かんがな。それにしてもや、どうもおかしいと思っていたんや。ワシもアホやあらへん。何故ヒネ(刑事)が松山ごときチンピラの情報欲しさにカネを出すのか。グフフ、ヤクザはズル賢く生きんとあかんのや。
「ハアハア、パパ~、誰に電話してたの?ああん」
「スポンサー様や。ええか麗子、そのスポンサーがワシ等の半目(敵対者)やとしたらどうや?」
吸い付くような麗子の密壺に指でまさぐりながらワシは言葉をはぐらしたのや。
あの日…、夢だったのだろうか…。私は深い眠りから覚めたように自分の部屋のベッドから身を起こした。
「夢…」
そっと自分の下着を見つめながら蜜壺に指をあてがった。ドクリ――。夢ではない。奴の痕跡があるかのように蜜壺が疼いた。間違いない。だから今まで以上に奴を求めている自分を自覚した。
「お早うございます」
加島誠之(のぶゆき)主席検事室。この部屋に足を運ぶことは2度とないと思っていたのに。
「松崎君か。確か辞職するんじゃなかったのかね」
「はい。しかし考え直すことにしました。加島主席検事、誠に申し訳御座いませんが撤回願いたいのですが」
まるで疑念を抱いたかのように主席検事が私を擬視するかのように冷たく応えた。
「しかしだね松崎君」
「何か不都合がおありなのでしょうか」
視光が絡みつくように交差した。
「何を言いたいのですか、君は?」
「では、ハッキリ言わせて戴きます。つまり」
私は一呼吸を於いてあだとらしく瞳に笑みを含み、言葉を差し向けた。
「Blood。加島主席検事、奥行きがまだ見えませんが、ウフフ、そのゲームとやらに私も参加させて戴きます」
「君!!自分で何を言っているのか判っているのか!!」
「あら、何か気に障ることでも言いましたか?」
緊張じみた空気が押し包む。やはり加島誠之は知っている。いや、参加しているのかも知れない。憤りを抑えているかのように、主席検事は私の目を直視しながらワナワナと肩を震わせていた。
「まさか君は、そうだな!?」
「仰(おっしゃ)りたい意味が判りませんが?」
いや、本当は判っている。貴方の目が語っているのですもの。
「加島主席検事、正義とは何足るかを教わりました。見かけ倒しの正義などは政治に於ける戯れでしかありませんわ。それと、私を辞職させることは」
「出来ないと言いたいのか」
「はい」
「な、何があった!?いや、お前は何を知ったと言うのか!!」
あの威厳ありき加島主席検事の目に、明らかに浮かぶ動揺。
「運命とは何である。時計の針の進行が即ち運命である。確か幸田露伴の座右の銘でしたでしょうか?主席検事が私に勧めた『努力論』からだったでしょうか?」
「何を知ったかしらんが、松崎君、この先は何があっても知らんぞ!!」
「アハハハハ。加島主席検事、それは脅しでしょうか?ご忠告有り難うございます。では、失礼します」
「君!!」
卓上を叩き上げる音が背に響いた。それは新たな過酷を強いるかのように。しかし、それはお互い様なのよ。闇に光が射し込む時――――、其処に浮かび上がるものが真実であるのかも知れない。
幸田 露伴(こうだ ろはん)
誕生 1867年7月23日
江戸下谷
死没 1947年7月30日(満80歳没)
墓地 池上本門寺
職業 小説家
言語 日本語
国籍 日本
教育 文学博士(京都帝国大学)
最終学歴 電信修技学校
活動期間 1889年-1947年
ジャンル 小説
主題 理想主義
文学活動 写実主義
代表作 『露団々』(1889年)
『風流仏』(1889年)
『五重塔』(1891年)
『風流微塵蔵』(1895年)
『天うつ浪』(1905年)
主な受賞歴 文化勲章(1937年)
ウィキポータル 文学
テンプレートを表示
幸田 露伴(こうだ ろはん、1867年8月22日(慶応3年7月23日) -1947年(昭和22年)7月30日)は、日本の小説家。本名は成行(しげゆき)。別号には、蝸牛庵(かぎゅうあん)、笹のつゆ、雷音洞主、脱天子など多数。江戸(現東京都)下谷生れ。帝国学士院会員。帝国芸術院会員。第1回文化勲章受章。娘の幸田文も随筆家・小説家。 『風流仏』で評価され、『五重塔』『運命』などの文語体作品で文壇での地位を確立。尾崎紅葉とともに紅露時代と呼ばれる時代を築いた。擬古典主義の代表的作家で、また漢文学・日本古典や諸宗教にも通じ、多くの随筆や史伝のほか、『芭蕉七部集評釈』などの古典研究などを残した。
「片瀬!?」
扉を開けた時、漠然と佇む片瀬に、鮮明に浮かんだアノ忌々しさに歯痒さを覚えた。
「あ、松崎検事、お早うございます」
私は無愛想に椅子に腰をかけた。この変態男!!自分が私に何をなそうとしたのか、忘れたとは言わせない!!
「どうしたのですか?朝から機嫌が悪いですよね」
何をしらばっくれているのよ。
「コーヒーを容れましょうか?」
コーヒー…?何を言っているのよ。私がコーヒーを飲まないことは知っているではないの。
「ちょっと片瀬君、私はジャスミンティーしか飲まないこと知っているでしょ」
「えっ、そうでしたか…。すみません…」
何なの……。本当に忘れてしまったのかしら?いや、私を判っているではないか。
「あのぅ…、貴方、本当に片瀬君なの?」
「嫌だなぁ、藪から棒に。松崎検事こそ、どうかしたんじゃないですか」
「覚えてないの?貴方が私に何をしようとしたのかを?」
「いい加減にして下さいよ。僕が松崎検事に何をしようとしたのですか?あ痛…」
片瀬は後頭部に手をあてがい顔をしかめた。まさか…
「ねえ片瀬君、1つ質問するわよ。貴方、松山慎吾を知っているわね」
「誰なんですか?その松山という人は……」
本当に片瀬は覚えていないのだろうか?そう言えば確かに困り果てた顔をしているようだ。その時卓上の電話が鳴った。
「はい、松山ですが」
「ククク松崎検事。やはり復帰をしたようだな。ククク」
松山慎吾?まさか…、声が全く出鱈目じゃないの。まるでアニメキャラの声だわ。
「いいか松崎検事。其処にいる片瀬の記憶は飛ばしてある。あとはクク、期待しているよ」
「ちょっ…」
ダメだ。電話が途切れてしまっている。じゃ、あの日のことは何だったの?夢……?いや違う。確かに今私に期待していると言った。目眩がしそうな気がしている私がいた。

















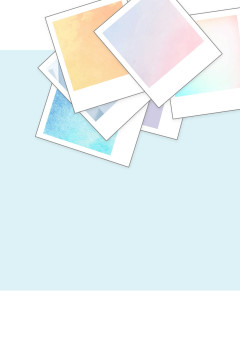


編集部コメント
引きこもりのおじさんと真面目な女子高生という組み合わせがユニーク。コンテストテーマである「タイムカプセル」が、世代の違う二人をつなぎ、物語を進めるアイテムとして存在感を発揮しています。<br />登場人物が自分の過去と向き合い、未来に向かって成長していく過程が丁寧な構成で描かれていました。