パーク内に入るやいなや、紙袋からカチューシャを取り出し、俺に渡してくる先生。
🐰 「 先生も付けてくださいよ?」
🐯 「 わかってるわかってる 」
相槌をしながら、そう適当に返事をする。本当にわかってるんだか、という風に横目で先生を見れば、ふんわりとした笑顔で俺がカチューシャを手にするのを待っていた。
テーマパークというものは、唯一無二の場所だと思う。まるで理想の世界が具象化されたようで、なんとも不思議な気分になる。パーク内の雰囲気をより醸し出すような音響には心躍らされ、夢がつまった様な建物の造りには想像力が掻き立てられる。何度来たって初めて目にしたような気持ちになるし、飽きるだなんて以ての外だ。それは本当に、一種の魔法のようなものなのかもしれないと錯覚する。
だからなのだろうか。何度か来たことのあるこのテーマパークも、一緒に来る人が違うだけでこんなにも新鮮に感じるだなんて。そう思いながら隣を歩く先生を見る。
🐰 「 ふふ、似合ってますね、先生 」
すると一瞬照れ臭そうにして鼻を触り
🐯 「 うっせ、それに… 」
🐯 「 似合ってる、はこっちのセリフだ 」
なんて言ってきた。似合ってるというストレートな褒め言葉に嬉しさを感じる一方、よりによってこのカチューシャを付けている時に言われるとは、という複雑さも感じた。嬉しさを隠すフリをして、少しふくれっ面をするようにこう言った。
🐰 「 …もう、どういう意味ですかそれ。これ女の人用なんですけど 」
しかし、その行為も虚しいようで。
🐯 「 ふふ、いいじゃねぇか。可愛いぞ、ジョングガ 」
🐰 「 …っ 」
その言葉を目を合わせながら言われれば、余計に脳を刺激する。瞬く間に心臓の鼓動が早まった。望んでもいないのに、じわじわと顔に熱が帯びていくのがわかる。そんな状態がバレたくないという思いから、反射的に顔を背けてしまう。相変わらず分かりやすい一連の動作にまたもや呆れてしまった。仕方ないと言えばそれまでだろうが、まったく厄介なことに、"かわいい" という言葉には未だに耐性がつかない。
🐰 「 …う、うるせ、っ 」
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
先生とゆっくりパーク内を歩いていると、周りの女性たちから
「 見て、あの子可愛い 」
やら
「 あんなん付けちゃってさぁ、もう可愛すぎ! 」
という声が聞こえてくる。近くにマスコットでも居るのだろうか。と疑問に思っていると、先生がため息混じりの声で話しかけてきた。
🐯 「 お前それ外しとけ 」
そう言えば、こちらの返事も待たずにカチューシャを外してくる。
🐰 「 え、あちょっと 」
🐰 「 なんですか急に 」
するとどこかバツが悪そうに
🐯 「 …ったく、だからお前は隙だらけなんだよ 」
と言ってきた。この人はいきなり何を言い出すのか、と意図不明なその言葉に思わず声が出てしまう。
🐰 「 はい?」
しかし理解が遅れただけであったのか、周りの声も相まって何となくその言葉の意味が察せられた。
🐰 「 あ、…わかった、先生 」
先程から耳に届く "可愛い" という言葉が向けられている先にあるのはマスコットなどではない。いや、カチューシャも元を辿ればマスコットがモチーフとなっているグッズなのだから、ある意味マスコットに向けられているとも捉えられるが、今はそちらの意味まで考える必要は無さそうだ。そう、気づくのが遅すぎたが、 "可愛い" の対象は俺なのである。
ただ勘違いしてはいけない。周りの女性陣から注目されていたのは、あくまでも、俺が女物のカチューシャを付けていたからだということ。それを証拠に、今はあの黄色い声は一切聞こえない。カチューシャを外されたただの男子高校生には、希少価値はつかないのだ。外された瞬間の周囲の残念そうな声が脳内で再生される。
にしても不思議だった。先生から言われた "可愛い" と、見ず知らずの人間から口にされる "可愛い" とでは、自分に向けてだと理解した時の感情が全く違った。あまり事細かく伝えると照れ臭いため、詳細に言うのは控えるが、1つ言いきれるのは、俺の弱点は先生なのだという事だ。それがまた小っ恥ずかしい。そしてそんな思いを悟られないようにと強がった気持ちが言葉となって、俺の口から飛び出した。
🐰 「 嫉妬してんだ 」
そう冗談交じりに言ったくだらない戯言に、まさか反応にされるだなんて。
🐯 「 …ああ 」
🐰 「 …え?」
🐯 「 え、って…ああもう、ほら、やっぱ付けとけ 」
誤魔化すように再びカチューシャが手渡される。
🐰 「 …隙だらけなんじゃないんですか?俺 」
🐯 「 ああ、無自覚も加えとけ 」
🐰 「 …そんな奴が、こんなん付けて大丈夫なんですかね?」
先生の反応にすっかり味を占めて、つい調子に乗ってしまう。元から結果は決まっていたというのに。
🐯 「 ま、別にいいんじゃね 」
🐰 「 …ふーん、」
🐯 「 もしお前がボケっとして、知らねぇやつになんかされる事があるとしても 」
🐯 「 俺が指一本触れさせなきゃいいわけだし 」
🐰 「 …っ 」
目に見えた展開。
🐰 「 …じ、自分の身ぐらい自分で守ります!」
🐯 「 はいはい、精々頑張れよ 」
🐰 「 んもう、先生!」
やはり俺の弱点は
先生だ
next ⇒ ♡ × 80









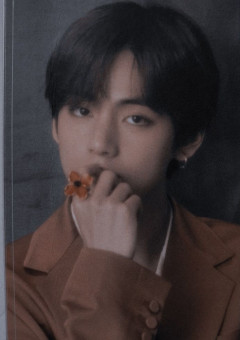














編集部コメント
依頼人の悩みや不安に向き合うカウンセラーという立場の主人公が見せる慈愛にも似た優しい共感と、その裏にひそむほの暗い闇。いわゆる正義ではないものの、譲れない己の信念のために動く彼の姿は一本筋が通っていて、抗いがたい魅力がありました!