「かぐや」
「何?」
眠そうな声で俺のそばにくっついてきた。俺のことは抱き枕と勘違いしてるのだろうか。
「何故、俺の隣で寝てる?ちゃんと二段ベッドを用意しただろう!」
「だって寒いのよ!」
そう言ってまた俺にしがみついてきた。外では紅葉が色づき、秋が深まっていた。朝と昼との寒暖差が激しかった。
時間は朝の6時。
寒い、寒いというかぐやのために、部屋の暖房をつけた。かぐやは素早くベッドから隣の部屋のコタツにもぐった。後頭部だけがちょこんと見えた。
俺はキッチンに行きお湯を沸かして、二人分のインスタントコーヒーを淹れた。かぐやにはミルクを多めにして渡した。かぐやはコタツから起き上がり、ふぅふぅと息を吹きかけて冷ましている。
アパートで二人暮らしをしていた。間取りは2K。家賃は6万円。二人とも仕事に就いていない。しかし、家賃は滞納することなく払えている。
村から追放されてすぐにかぐやと合流した。待ち合わせ場所を決めていたからだ。
洞窟の檻から逃げられたのは良かったが、かぐやは外の世界がよくわからないみたいで途方に暮れていた。助けたことに責務を感じた俺は一緒に暮らすことを提案した。
当時の俺は十歳だったので、かぐやは俺のことを子供のように慕っていた。
かぐやは年をとらない。不老不死だ。顔つきや肌などといった若さも十年前と変わりがない。 張りがある。
その間に俺は二十歳になり大人の体格になった。
「朝ごはん、私が作るわ」
かぐやはそう言って、冷蔵庫から卵を取り出し。フライパンで焼いた。 ジュウと食欲を誘う音。目玉焼きだった。他にもウインナーやキャベツや味噌汁を用意をしていた。
今日は和風なのかと思った。日によって白ご飯だったり食パンだったりする。
ご飯は一緒に作ることもある。
「彦」
俺は窓のシャッターを開け、新聞を取りに行き、コタツの天板を拭いていた。
かぐやが用意した朝食をコタツの上に二人分置いた。
いただきますと言ってから一緒に食べた。
味噌汁が体を温めた。パンもうまいが、朝食に白ご飯と味噌汁があれば文句はなかった。
「学校に行きたい」
それはかぐやから何度も言われていることだった。
「それは難しいと思う。あまり目立つことはしたくないんだ」
村の人間やかぐやを欲しがる連中から狙われている。
かぐやを守ることが俺の使命だった。十年前、暗い檻から助けた時から。
「私の力よりも、彦の力の方が十分目立つよ!」
「俺はそんなに力を使わない。かぐやは力を制御できないから困るんだよ」
「ひどい……学校に行きたいのよ」
かぐやがポロポロと涙を流した。みるみるうちに宝石に変わった。
言わんこっちゃない。こんなことが学校で起きればさぞや驚かれることだろう。
まぁ、これのおかげで家賃が払えている。
「それじゃぁ、大学に行くか。近くの大学でいいな」
「ありがとっ!……ナニコレ?」
部屋の押し入れの中から数冊の本を手渡した。
「参考書一式。大学に入学するなら試験を受ける必要があるからな」
かぐやのために、用意はしておいたのだった。
「えー、そこは彦の力で」
「ダメだ!他の受験生に失礼です。フェアにいきましょう」
かぐやは俺としか会話をしていない。
外に出るといっても買い物くらいだった。おそらく寂しいのだろう。
かぐやには外の世界を楽しんで貰いたい。それは以前から思っていた。
「彦、英語って何?」
「俺にもわからん」
前途多難だった。俺は教育を受けていない。文字の読み書きができる程度だった。
一方かぐやは違っていた。字を書くのは読めないほど達筆だ。教養もある。
かぐやは俺が生まれた村で百年くらい軟禁されていたので、外との繋がりがなかった。
それ以前は自由な時もあり、誰かしらの教養を受けたことさえあったという。
二人で勉強するなら俺が足を引っ張りそうな気がする。
「やっぱり彦の力を使おうよ」
「確かに俺は人の願いを叶える力を持つけど、自分の願いは叶えられないんだよ」
「それじゃぁ、彦はお家でお留守番しててよ!」
「かぐやを一人にさせるわけにはいかないだろう」
いつもの会話になる。 堂々巡り。
しかし、今度は覚悟を決めていた。二人で受験生になる。
彼女は『古典は任せてよ』と意気揚々だった。
「何も大学に入学する必要はないんじゃないか?見学で十分だと思うぞ」
「ダメよ!私は講義も受けたいし、サークルにも入りたいし、学食も食べたいわ!」
俺たちは何も就職をするわけではない。
でも、俺はともかく、かぐやは大学に通うことで何か生かせるかもしれないと思った。
「それに……お友達も作りたい」
その一言はとても重要な言葉に思えた。
「そうだな、頑張るか!」
そうして、二人で受験勉強に励んだ。二人とも独学だ。
塾に通うことで素性を知られるのはまずい。できるだけ、人との交流は避けたかった。
あれよあれよと、一年が経ち、二人で近くの大学の試験を受けた。
結果は二人とも合格だった。
この春からめでたく大学に入学することになる。
かぐやが俺を抱きしめて『やればできる子』なんて言われた。俺は必死で頭がオーバーヒートしていた。
かぐやは余裕そうだった。『やればすごい子』そう言い返した。






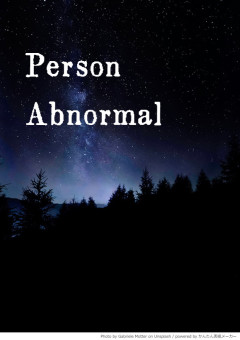
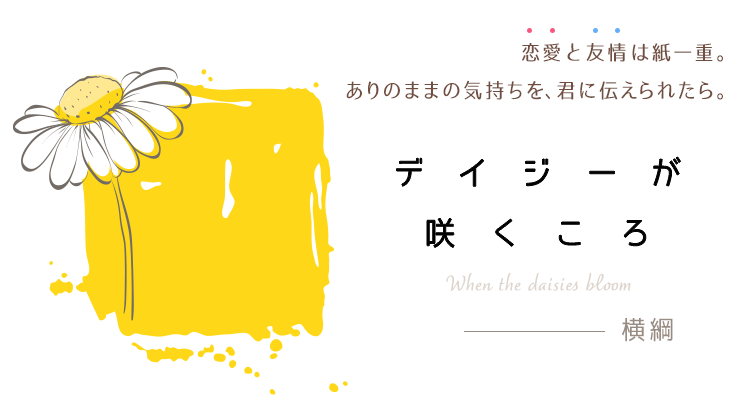












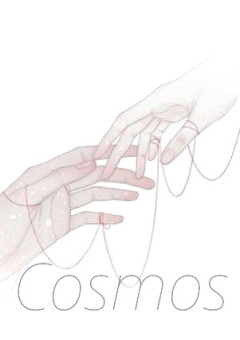
編集部コメント
主人公は鈍感で口下手ではあるものの『コミュ障』というほどではないので、キャラの作り込みに関しては一考の余地があるものの、楽曲テーマ、オーディオドラマ前提、登場人物の数などの制約が多いコンテストにおいて、条件内できちんと可愛らしくまとまっているお話でした!<br />転校生、幼馴染、親友といった王道ポジションのキャラたちがストーリーの中でそれぞれの役割を果たし、ハッピーな読後感に仕上がっています。