夏はいつも、切ないくらいに鮮やかだ。
7月に入ると、夏も本番だとでも言うように、暑い日が何日も続いた。
バレーボール部で活躍する琴と教室で別れて、帰宅部の私はそそくさと家路につく。
青い空の中、憎たらしいほど堂々と浮かぶ太陽が、私の皮膚を突き刺すように容赦なく照りつける。
その奥に潜む積乱雲が、太陽の光を大きな体に浴びて、白く輝いていた。
生温い風が吹いて、その中に湿った匂いを見つける。降られる前に帰らなきゃな、と私は歩くスピードを速めた。
最近、夏川先輩の姿は見かけない。
夏に入り、高3生である先輩たちは忙しい。
朝早くから学校に来て自習する人もいれば、遅くまで自習室にこもって勉強する人もいる。
毎日のように行われている校内模試や全国模試の様子を見る限り、私たちの学校も一応進学校なんだなぁなんて思った。
高2生である私だって、そんなにうかうかしていられないのだが。
夏休みに入るまで、あと半月ほど。
それまでに1回ぐらいは会えるかな。
こないだ、塾の授業中。授業の隙をついて、男子生徒が「三島先生って、彼女いるの?」とどこか馬鹿にしたような口ぶりで聞いた。教室中の誰もが、予想していない質問だった。
必死に板書を追ってノートをとる手に、少し力が入る。不意打ちに声をかけられた時のように、私の心臓が小さく跳ねた。
質問を投げかけられた先生は、小さくて丸い目を数回瞬かす。それから、へらりと笑った。男子のくだらない質問をとても一喝できそうにない、気の抜けた優しい笑顔だった。
そして一言、いるよ、と答えた。
質問した男子生徒が、えっ、と短く声を上げる。他の生徒たちも、内心驚いたのだろう。誰も気づかない程度に、教室の空気が揺れた。
途端に、ポップコーンが一気に弾け出すかのように、「どんな人?」だの「いつから付き合ってるの?」だの、芸能リポーターのような質問の嵐が巻き起こった。
私は、そんな様子を驚きながら見ていた。だけどなぜか、さほどショックではなかった。
ただぼんやりと、困ったな、なんて顔をしながら質問に答える三島先生を眺めていた。
私は、三島先生のどこが好きだったんだっけ、と思い返そうとしても、到底出てきそうにはなかった。
すぐさま学校で琴に話すと、「最初から、好きじゃなかったってことでしょ。」となんとも素っ気ない返事が返って来て、思わず言葉に詰まった。
つまらない古文の授業が終わって、休憩時間に入ったところだった。琴は、次の数学の授業に合わせて、教科書に目を落としていた。私の話を聞き終えると、ゆっくりと顔を上げる。
ビューラーで丁寧にあげられたまつ毛が、琴の瞳をより大きく誇張している。柔らかな焦げ茶の瞳は、私の戸惑うように揺れる瞳を真っ直ぐに捉える。すべてを見透かされているように注がれる視線に、そんなことないよ、と答えるのが精一杯だった。
好きじゃなかった、ではだめなのだ。
好き、ではないと。
三島先生を好きだと思う私がいたから、私は何にも臆することなく、普通に話すことができるのだ。
誰と?
静かに、密やかに、心の中で誰でもない声が私に問いかける。
私は、そんな声聞こえまいと首を振る。
誰も触れたことのないガラスのような水面を、間違えて指先で弾いてしまったかのように、私の心が穏やかに激しく波打った。















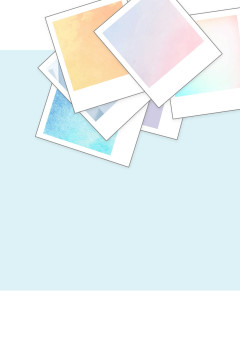


編集部コメント
主人公は鈍感で口下手ではあるものの『コミュ障』というほどではないので、キャラの作り込みに関しては一考の余地があるものの、楽曲テーマ、オーディオドラマ前提、登場人物の数などの制約が多いコンテストにおいて、条件内できちんと可愛らしくまとまっているお話でした!<br />転校生、幼馴染、親友といった王道ポジションのキャラたちがストーリーの中でそれぞれの役割を果たし、ハッピーな読後感に仕上がっています。