何気ない友人の提案から全てがはじまった。
八月。大学生の夏休みというものは想像以上に長い。高校のように追われる課題もなければ、どこにいってなにをするのも自由だ。
幾らバイトに明け暮れていても暇を持て余すのは必然だった。
ゆづるがメッセージに気付いたときには既にグループチャットは心霊スポットの話題で持ちきりになっていた。
ゆづるの反対を押し切り、友人たちはすっかり肝試しにいく気満々になっている。
流れていくトークを見ながらゆづるはスマホを握りしめ、ため息をついたのだった。
*
三日後の深夜二十三時。
ゆづるを含めた大学生の男女四名は某県山中のトンネル前に立っていた。
街灯一つない山道。ナビ上はいき止まりになっているが、目の前にはおどろおどろしいトンネルが佇んでいた。
軽自動車が一台やっと通れそうなほどの狭いトンネルの入り口は申し訳程度に錆びた一本のチェーンで塞がれている。車のライトでトンネルの奥を照らしてもなにも見えない。
じっとりとした夜の熱気と、蛙や虫のうるさい鳴き声が不気味さをさらに駆り立てていた。
入り口で立ち竦んでいるゆづるを置いて、三人はさっさとトンネルの中に入ろうとしていた。
ゆづるの制止を振り切り、三人はスマホのライトを頼りにトンネルの奥へと進んでいく。
最初は中から彼らの楽しそうな声が反響して聞こえてきたが、そのうちなにも聞こえなくなった。
一人残されたゆづるは不安を滲ませながらトンネルの奥をじっと見つめていた。
鼓動が速まる。背後から気配を感じて振り向いたが気のせいだった。
底知れぬ不気味な気配と恐怖感に襲われるのは、こんな真夜中に人気のない山奥にある最恐の心霊スポットの前に立っているせいだろう。
子供の頃、一度だけ探検と称してこのトンネルに来たことがあった。
なにも知らずに中に入ろうとしたら止めてくれた少年がいたことを、ゆづるはぼんやりと思い出した。
少し年上の頼れるお兄ちゃん的存在だった。
物知りな彼は、手を繋ぎながら色々なことを教えてくれたっけ。
とても優しくて、幼心に憧れを抱いていた。
でも、今はもう彼の名前も顔もよく思い出せない。
その時、トンネルの奥から友人の悲鳴が聞こえた。
トンネルに向かって名前を叫んでも返事はない。
いつの間にかうるさかったはずの虫たちの声が消え、辺りはしんと静まりかえっていた。
もう一度叫ぶが返事はない。
鳥肌が立ち、冷や汗が噴き出す。不安と恐怖で心臓はうるさいくらいに音を立てた。
警察に連絡するべき? でもここに来るまでかなり時間が必要だ。
それに、肝試しに来たなんていったら迷惑がられるに決まっている。
スマホを握りしめ一分、二分過ぎていく。だが待てど暮らせど友人たちは戻ってこない。
こうなったら助けを呼ぶよりも、自分がいったほうが早いはずだ。
手が震えていた。
外は暑いはずなのに、歯がガチガチと音を立てる。
頭の中に蘇るいつかの少年の声を振り払い、ゆづるは思い切ってトンネルの中に駆け出した。
トンネルの奥はいき止まりのはず。だからこうして走れば絶対に友人たちに追い付くはずだ。
ゆづるは極力周りは見ないようにして、足元だけを見つめていた。
自分の足音だけが反響している。しばらく走ったけれど、友人たちはまだ見つからない。
ゆづるは泣きたくなった。
肝試しなんて碌なことがないんだから、絶対にいきたくなかったのに。
友人たちのせいでもあるが、押しに弱く彼らを止めきれず、ついて来ることしかできなかった自分を悔いた。
恐怖を怒りに変え、ゆづるは走った。
その時、正面からぶわりと強風が吹き付けた。土埃に一瞬目を閉じる。
あれ、なんで正面から風が? このトンネルは片側が塞がれているはずなのに――。
ゆづるは目を疑った。
見えないはずのトンネルの出口が見えたからだ。
その向こうには真っ赤な夕焼け空が見え、風が吹き付けている。
まるでなにかに導かれるようにゆづるが足を動かすと、出口はどんどん近づいてくる。
そして彼女は友人とすれ違うことなく、とうとうトンネルをくぐり抜けてしまった。
片側が閉じられているはずのトンネルの向こう――そこには夕焼けに染まる不思議な世界が広がっていた。




















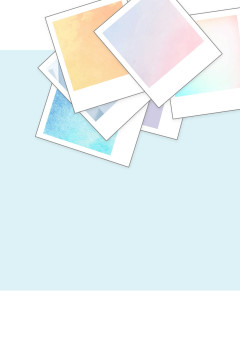


編集部コメント
主人公は鈍感で口下手ではあるものの『コミュ障』というほどではないので、キャラの作り込みに関しては一考の余地があるものの、楽曲テーマ、オーディオドラマ前提、登場人物の数などの制約が多いコンテストにおいて、条件内できちんと可愛らしくまとまっているお話でした!<br />転校生、幼馴染、親友といった王道ポジションのキャラたちがストーリーの中でそれぞれの役割を果たし、ハッピーな読後感に仕上がっています。