人魚は涙を持たない。
だから、余計に哀しかった。
どれだけ怒られても次の瞬間には空気を変えるように笑ってみせる。どんな理不尽な言葉を投げつけられても、なんでもないような顔で受け流してしまう。そんな彼をみて、ふと思い浮かべた寓話の一説。いい大人なんだから上手いこと自分で対処するだろうし。どうしてもダメなら相談してくれるだろうし。踏み込む怖さに二の足を踏んで、心に引っかかった暗い“ナニカ”に名前をつけないまま放置してしまったことへの罰がこの結果なのだと、目の前の景色を前に思い当たった。
「めめ、おれどうしよ、…」
「っ、」
「こんなんじゃ、アイドルなんて出来ないよね。SnowManでいちゃ、ダメだよね」
「そんなこと、」
「良いよ、俺が1番分かってる」
「佐久間くん、」
彼の笑顔は魔法だと言う、その言葉にその通りだと思った。周りの誰も彼もを巻き込んで笑うその顔は、魔法だと。明らかに引き攣った頬の筋肉に、必死で笑おうと努めて、却って泣き顔に近い雰囲気を纏ってしまう瞳。優しく弧を描く唇が震えて、限界を迎えたようにぽろりと雫が溢れた。
佐久間くんからLINEが届いたのは、彼の出演している映画のプロモーションが落ち着いてしばらく経った頃だった。
“めめ、たすけて”
散々迷って送信取消しを何度も重ねた後に送られて来たらしいLINEを見た瞬間、嫌な予感に胸が騒いだ。荷物を引っ掴んで向かった彼の自宅、不用心なことに鍵のかかっていない玄関に驚き、電気が消えた部屋で呆然と座り込んでいる佐久間くんの姿に心臓が竦む。慌てて駆け寄った先、彼はひとこと「笑えなくなっちゃった」と呟いた。
SnowManでいられない。
もう辞めなきゃダメかな。
震える声でそう口にした佐久間くんを前に、気付けば「大丈夫だから」と口走っていた。
「大丈夫。佐久間くん、大丈夫だから」
「でも、おれ…」
「疲れたんだよ、きっと。佐久間くんがまた笑えるようになるまで、俺が一緒にいるから」
「めめが…?」
「佐久間くんが変なことを言わないように、俺が見てるよ」
我ながら、思い切ったことを言ったなと思う。
その日から、俺と佐久間くんの同居生活が始まった。彼の凄いところは、仕事で笑えと言われたら笑えてしまえたところ。もともとお芝居に対する適性は高い方だったと思う。アイドル・佐久間大介を演じている時はいつもと変わらないように笑ってみせて、仕事が終わるとスイッチが切れたように表情が欠落する。
「めめが居てくれて助かったわ…」
「ふは、別に。俺も佐久間くんとのんびり過ごせて嬉しいよ。こうやって一緒に風呂入るのとか久し振りだし」
「ん、……そうね。でも笑ってる雰囲気だけで色々誤魔化して来たことあるんだろうなって、今回思ったかも」
「今はゆっくりすることだけ考えなって。佐久間くんの熱いとこ、俺は大好きだけど。でも反省会は元気になってから」
最初は見ていて苦しくなるような悲壮さが滲んでいた無表情が徐々に穏やかに変化して、せめてマイナスからゼロに近づけてるのかな、と思ってきたこの頃。メンバーのスケジュールの兼ね合いで歌番組とバラエティーをまとめて収録して、その後に俺と佐久間くんは4日のお休みが取れることになった。
踊って、歌って、笑って、わらって、…
多分、俺が来てから少しずつ緩めていた心の糸が一気に張り詰めて。それで、ぷつん、と切れてしまったんだと思う。
「「おつかれさまでしたー!」」
この後どうする?飲みに行く?とスタッフチームと盛り上がるメンバーの輪から少し離れたところ、“いつも通り”の仮面を必死で保ったまま、たたらを踏むように蹌踉めく佐久間くんが見えた。
「っ、俺と佐久間くんは雑誌の取材あるらしいから、今日は皆んなだけで楽しんでおいでよ」
残念そうな声と次を約束する声、その向こうで佐久間くんの瞳が安堵に染まる。メンバーの前ならいざ知らず、スタッフの前で仮面が剥がれたら根が真面目な彼のことだから、きっとSnowManでは居られないと嫌な方向に腹を括ってしまう。それだけは、止めたかった。
「じゃ、そういうことなんで。佐久間くん、あとひと頑張りしよ」
「ごめんね皆んな〜。また絶対誘ってよ?!」
最後の気力を振り絞るようなハイテンション。楽屋を離れて人気が完全に無くなるまで、佐久間くんはあくまで“アイドル・佐久間大介”を保ち続けていた。
「めめ、ごめん、……もうむり、」
「うん、分かってる。凄い熱だよ」
「撮影中からぞくぞくしてて、」
「頑張ったよ。もう我慢しなくて良い」
崩れ落ちそうな身体を抱き上げて、そのままタクシーで自宅に直行。隣から聞こえる呼吸は荒く上擦っていて、代われるものなら代わってやりたいとさえ思った。
「っ、はあッ、……くるしい、」
「解熱剤、確か飲めなかったっけ」
「きもちわるくなっちゃう、から」
「了解。あ、もう着くよ」
「めめ、」
「うん?」
「ごめんなさい」
それが何に対するごめんなのかは分からなかったけど、何故か胸の奥がギュッとなって、気付いた時には佐久間くんの身体を抱き締めていた。
「謝らなくて良いから。……帰ろう」
今度は涙を拭える距離にいる。そのことに安堵している自分には、気付かないふりをして。
「マジで高いな…」
「ぅ、……っ、は、ぁッ、」
部屋に入って楽な服に着替えさせて、直ぐに測った体温は39度近いものだった。
「佐久間くん、今って寒い?熱い?」
「っ、さむ、?あ、つ…?」
「うん。…わかる?」
「わから、な、…っ、ごめ、なさ」
「ううん、大丈夫。佐久間くんは何も悪くないよ。ちょっと頭冷やすから、寒かったら教えて。何かして欲しいことがあれば、何でもするから」
冷えピタを額に張り付けて、冷凍庫に仕舞われていた氷枕にタオルを巻く。熱った肌に冷たいものが触れた瞬間に少しだけ表情が和らいで、せめて心地いいと思ってくれていたらいいなと思った。
「めめ、……」
「うん、ここにいるよ」
緩く伸ばされた手をぎゅっと握り返して、熱を帯びた頬を優しく撫でる。低体温気味な指先がこんなところで役に立つとは思ってもみなかった。
「……、っ、て、ほしい、」
「佐久間くん?」
「おれ、のこと、」
呼吸の合間に掠れた声がほろりと零れ落ちる。強い風の前に晒された蝋燭みたいな頼りなさで、それでも何かを必死に訴えかける声。
「っ、おれ、っ…っ、げほ、げほげほッ」
「焦んなくていいから。ゆっくりでいい」
「き、きらい、に」
「…?」
「きらいに、ならないで…」
呼吸が乱れて咳き込み始めてしまった佐久間くんを抱き起こして、背中を撫でながら耳を澄ませる。聞き間違いじゃなければ、今、彼は。
「嫌いになんて、なるわけないって…」
何かに怯えるように謝ってみせたり、今の言葉だったり。点と点が繋がるように佐久間くんの傷の形が浮かび上がってきて、そういうことか、と腑に落ちる。最近、やけに笑い声が響く頻度が高かったこと。ハイテンションに振る舞うことで、悲しい気持ちをやり過ごそうとする癖なら、知ってたはずなのに。確かに彼の笑顔は魔法だ。俺をいつだって幸せな気持ちにしてくれて、周りの人を照らし出す太陽みたいな笑顔。だけど。
ねえ、聞いて。
「俺は佐久間くんの泣き顔も好きだよ。真剣に怒ってる時の熱さも好きだし、見てると武者震いしそうになる緊張感も好き。……笑ってる時の佐久間くんだけが、全てじゃないでしょ。そんなの、俺はやだ」
両手で頬を挟み込んで、丁寧に視線を重ね合わせる。全部本当の気持ちだって伝わるように。俺はどんな佐久間くんでも大好きだって、今だけは照れよりも恥ずかしさよりも、伝えるべきことがあるって分かるから。
「……っ、めめ、」
強張った身体から徐々に力が抜けて、俺の肩に佐久間くんの体温がダイレクトに伝わってくる。とすん、と肩に額を預けた彼は、ここまでの緊張が一気に解けたような顔で、ふわりと微笑んだ。
「……今の」
「ん、…ぅ」
体力の限界に達したのか、そのまま子どもみたいにすてんと寝入ってしまった佐久間くん。安心しきった寝顔と穏やかな寝息に、根拠なんてないはずなのに、もう大丈夫だと信じられた。
- 後日談 -
「ねえ、何であのとき俺に連絡してくれたの?」
「んえ?あー…それ、は」
「何?適当?」
「違うってー!めめなら、俺の弱いところ見せても引かないかなって、無意識に思ってた、かも、……ってこれ、恥ずかしいな。にゃはは」
あの時受け取った部屋の合鍵を未だに返していないのは、多分、俺のせいだけじゃない。









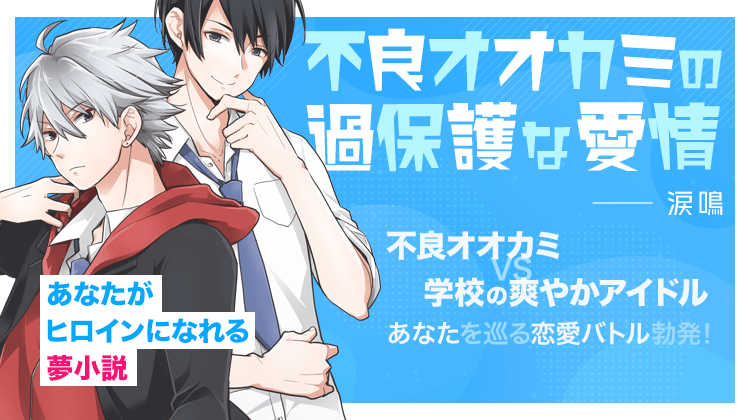












編集部コメント
主人公は鈍感で口下手ではあるものの『コミュ障』というほどではないので、キャラの作り込みに関しては一考の余地があるものの、楽曲テーマ、オーディオドラマ前提、登場人物の数などの制約が多いコンテストにおいて、条件内できちんと可愛らしくまとまっているお話でした!<br />転校生、幼馴染、親友といった王道ポジションのキャラたちがストーリーの中でそれぞれの役割を果たし、ハッピーな読後感に仕上がっています。