電車を乗り継ぎ、萎びた古い病院へ。
受け付けの看護師さんは、もはや軽く会釈をするだけで通してくれた。
頬を伝う汗を、みっともなく手で拭い、私は彼の部屋を開けた。
室内もまた、茹だるような暑さなのだが、ベッドで半身を起こし、静かに外を眺める彼を目にすると、その暑さすらも忘れた。
「もう、入るときはノックでしょ?」
その儚げな容姿とは対称的に、軽く掠れた、青年らしい声が私を迎えた。
「あら、ごめんなさいね。一秒でも早く、貴方の顔が見たくて。」
「そんな見え見えの嘘、面白くないし。」
前田は口は随分と達者だったが、表情は柔らかく、楽しそうだった。
「それにしても、よくもまあこんなクソ暑い日に病院なんて来たね。僕が君だったら絶対来なかった。」
「だって、それが私の仕事だもの。」
「へぇ~。生き辛そうだねぇ。」
のんびりと、彼はそんな冷えきった言葉を発した。生きづらいだなんて、今まで考えたこともなくて、この部屋だけが冷えきっていくように感じた。
「何よ...」
「そうやって一個一個本気になって捕らえてさぁ。君は、肩の力の抜き方を知らないよね。」
「...私は私。貴方が口出ししていいような事じゃないわ。」
そういって、何でもないような素振りをしてみたけど、心の冷えは収まらなくて、目の前の少年が心底怖くなった。
「そうだね!君は君だ。
それに、僕みたいなのに口出しされてもムカつくだけかぁ。」
前田はニコニコしながら、勝手にレジ袋をあさりだした。
「おっ、今日も美味しそうなの持ってきてくれたね~。味しない飯よりずっといいよ。」
二人でくだらないことを話ながらゼリーを食べる。先程あんなに冷たいことを言っておきながら、彼は悪びれもせずゼリーを頬張る。
...こうして、一つ一つ深刻に捕らえてしまうのも、生きづらいなんて言われる原因だろうか。
口に含んだゼリーは、私の悶々とする鼠色の気持ちを押し流すように喉を伝い、ゼリーに沈んだ白桃が弾けた。
「あ~美味しかったよ!いつもありがとうね!」
食後、彼は喜色を顔いっぱいに広げていた。
「じゃあ、私そろそろ帰るから。」
「あれ?もう帰るの?またおいでね~!」
小学生のような幼さで私に手をブンブンふる彼を見ると、やっぱり彼は、そこまで物事を深刻に考えていないのだと思った。
「こんなに美味しいもの食べれるなんて、生きてて良かったなぁ~。」
私が病室を出るその瞬間、彼のいとおしそうな声が聞こえた。
この言葉だけ聞けば、何も無かったのかもしれない。でも、私には、彼にとっての「生きる」がもう少しで終わる事実がちらつき、素直には喜べなかった。








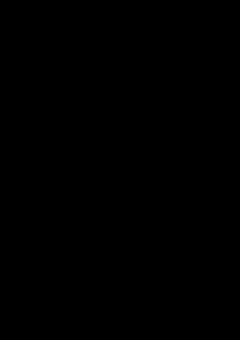














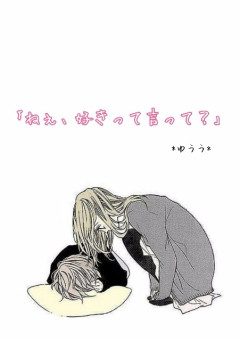


編集部コメント
主人公は鈍感で口下手ではあるものの『コミュ障』というほどではないので、キャラの作り込みに関しては一考の余地があるものの、楽曲テーマ、オーディオドラマ前提、登場人物の数などの制約が多いコンテストにおいて、条件内できちんと可愛らしくまとまっているお話でした!<br />転校生、幼馴染、親友といった王道ポジションのキャラたちがストーリーの中でそれぞれの役割を果たし、ハッピーな読後感に仕上がっています。