「煙草、買ってきて」
姐さんにそう言われて、少し前に通り過ぎた煙草の自動販売機へと走って戻る、そんな昼下がり。
どうせなら前を通った時に言って欲しかったと思いながらぐっと堪え、受け取ったお金で煙草を買う。
文句を言えないのは僕が下っ端だからで、それも、とある不良軍団の下っ端だからである。
僕をパシリにするのは、博麗霊夢という女で、姐さんと呼ばれている。
そこそこ高い身長に、抜群なスタイル、それからストレートの黒髪が特徴的だ。
そんでもってとびきり強い。
姐さんの隣にはいつも、霧雨魔理沙という女がいた。
霧雨さんやら魔理沙さんやら魔理ちゃんやら色んな呼び名で呼ばれているが、僕は霧雨さんと呼んでいる。
霧雨さんは、ふわふわの金髪で、小柄な可愛い子だが、僕よりずっと強い。
ぶっちゃけ、姐さんといい勝負だと思う。
さて、僕は買った煙草を握って、来た道を戻っていた。
あんまり遅いと怒られるので、全力疾走で。
「ね、姐さん…煙草…買ってきま…した…」
息を切らしながら差し出すと、姐さんは涼しい顔で受け取った。
「あぁ、ありがとね。魔理沙、ライターある?」
「あるけど…吸うのか?」
姐さんの横にいた霧雨さんは、持っていた鞄から渋々といった様子でライターを取りだし、姐さんに渡した。
「なに、駄目なの?」
「いや…だって体に悪いじゃん?」
「大丈夫よ、死なないから」
「んー…そう、かもだけど…」
霧雨さんは、姐さんが煙草を吸うのをいつもこんな風に止めようとする。
先輩に聞いた話だと、霧雨さんは姐さんの体を心配してるかららしい。
「あ、魔理沙も吸う?」
「いや、遠慮しとく」
姐さんは、そう?と言いながら煙草に火をつけた。
霧雨さんはちょっと嫌そうな顔をしながら、諦めたように溜息を吐いている。
「ふー…」
煙草を吹かしながら、なにか思いついたように姐さんが霧雨さんの腕を引っ張った。
と同時に、僕も先輩に引っ張られた。
「な、何するんですかっ」
「しっ、殺されたいのか?」
殺され…?
なんの事か分からず首を傾げていると、黙ってればいい、と言われて目を塞がれた。
驚きつつも言われた通りに大人しくしていると、激しくむせる音が聞こえてきた。
「げほっごほっ、ば、ばかっ!何すんだよ、煙直接吸わせるとか…」
「え、シガーキスってこうじゃないの?」
「ぜ、絶対に違う…ごほっ」
どうやら激しくむせていたのは霧雨さんだったらしい。
「というか、みんながいる前でこういうことやるなって!みんなどっか行っちゃったじゃん…」
「あらほんと、2人っきりになっちゃったわ。ホテルでも行く?」
「行かない」
耳に入ってくるそんな会話に、僕は驚きが隠せずにいた。
いや、まぁ全くそんな気がしなかった訳では無い。
やけに距離が近いし、2人でいる時は急用でない限り話しかけない方がいいと教わってからそんな気はしていた。
していたが、いざそれを目の当たりにしてしまうとやっぱり驚く。
「そう、まぁいいわ、みんな戻ってきて良いわよ」
姐さんがこちらに向かってそう声を掛けると、みんな一斉に姿を現した。
僕も先輩に引っ張られるようにして姐さんの元へ行った。
「な、なんでみんながいる所でそういうこと言うの」
「さっきはいなかったわよ」
「いたじゃんっ」
霧雨さんは顔を真っ赤にして、弱い力で姐さんをぽかぽかと殴っている。
先輩方はその様子を微笑ましそうに眺めていた。
「可愛いわねほんと…あんたらこいつに手出したら殺すからね」
突然向けられた殺意に背筋が凍った。
先輩方は慣れているのか、そんなことしませんよ、なんて笑いながら言っていた。
僕はほんとに最近入ったから知らないけど、これが日常なのだろうか。
「霊夢、殺すとか言っちゃ駄目だ。みんな仲間なんだぞ?」
霧雨さんが姐さんに向かってそう言うので、霧雨さんは割とまともな人なんだろうなと思った。
「分かったわよ、半殺しくらいなら良いわよね」
「だから…」
霧雨さんが、はぁ、と溜息を吐きながら、いつの間にか歩き始めていた姐さんの後を追う。
僕も先輩方に続いて歩き出そうとしたら、何を思ったのか霧雨さんが戻ってきた。
「分かってると思うけど、霊夢に手出したら殺すからな」
霧雨さんはこそっと囁くようにそう言って、何事も無かったかのように姐さんの横にぴったりくっついた。
「ひ、久々の魔理沙さんの殺気…ひぇ…」
「最近魔理ちゃんご機嫌だったから、油断してたな…」
先輩方がそんな風に萎縮してて、まともな人では無かったんだな、と思った。
姐さんには言っちゃ駄目とか言ってた癖に、自分は言うらしい。
「新人も、御二方の気に触るようなことしたら結構ガチで殺られるから気をつけろよ」
先輩方の警告にとりあえず頷いておいた。
後で分かったことだが、姐さんは霧雨さんの耳にも入るように言うけど、霧雨さんは姐さんにバレないようにこっそり言ってくるらしい。
そんな状況を先輩方は、お似合いカップルだ、と笑っていたので僕もそう思うことにした。
現に2人はお似合いカップルだし、多分ほんとにデキてる。
「霊夢〜、次どこボコすんだ?」
「こら、ボコすとか言わないの。隣町の奴らよ」
「あそこ前にボコした…よな?」
なんだか物騒な会話が聞こえてくる。
それでも本人たちは楽しそうだから、会話の内容を除けば、女子ふたりが仲睦まじく歩いているように見える。
「この間あそこの組の男がナンパしてきたじゃない、だからボコさなきゃね」
「ナンパされたの私じゃん…しなくていいよ…」
「私の女に手出したらどうなるか分からせなきゃじゃない?」
私の女、と言われて霧雨さんは突然上機嫌になった。
さっきまで呆れたような顔をしていたのに、今は喜びが隠しきれないような顔でニヤついている。
「し、仕方ないな〜、大事にしないならしてもいいぜ」
「あ、ほんと?じゃ、行きましょ」
姐さんに、着いて来い、と言うように手招きされたので先輩達に続いて着いていく。
相変わらずあの2人は先頭で仲睦まじい姿を見せていた。
「ま、待ってくださいよ、姐さん。隣町の組って強い奴らじゃないですか」
「怖いなら着いて来なくていいわよ?」
「いや…着いていきますけど…」
先輩はそう言いながらも、ちょっと怯えていた。
そんなに強い奴らなのだろうか。
「強いって言っても霊夢が1人で勝てる程度だろ?大丈夫だって、私もいるし、な?」
霧雨さんはそう言って、怯えているみんなを励ましているようだった。
やがて到着したのは、半壊状態のアジト。
今から全壊にされるのかと思うと胸が痛む。
その時、アジトから人が出てきた。
すかさず姐さんがそいつの腕を掴む。
「ひっ、な、何するんですか」
「ちょっと聞きたいことがあるのよ、正直に答えてくれたら貴方は見逃してあげるわ」
アジトから出てきたそいつは、どうやら新人のようだった。
パシリにされているところだったらしい。
「聞きたいことって…?」
「ここの組に、私の女に手出した奴がいるはずなのよ。心当たりは?」
「え、ちょっとわかんな」
「あ?」
ひっ、と新人が声を上げる。
「せ、先輩方に聞いてきますのでお、おお待ちを…!」
そう言ってそいつはアジトの中へと入っていった。
「霊夢…脅しちゃ可哀想じゃん...」
「脅してなんか無いわよ?聞いただけじゃない」
明らかに脅してましたけどね〜…と先輩方が小さい声で呟く。
その声は姐さんの耳には入らなかったらしい。
しばらくして、相手の組の新人が戻ってきた。
「今、買い出しに行ってるみたいで…」
「そうなの、じゃあここで待たせてもらうわね」
「あ、はい」
新人はそう言うと、こちらをチラチラと伺いながらアジトの中へ戻って行った。
それからほんの少しして、例のナンパ男が帰ってきた。
手にはたくさんの荷物が抱えられている。
「あんたね?私の女に手出したクソ野郎は」
そう言いながら、姐さんがそいつの肩をがっと掴む。
「なんだいなんだい、誰かと思えば隣町の可愛い子じゃないか。何の用だい?」
「あんたの頭をかち割りに来たのよ、私の女に手出すなんて度胸のある奴ね」
「金髪のお嬢ちゃんのことかい?いやぁ、可愛いよなぁ」
男は姐さんの殺気染みた言葉に怯みもせず、悠々と言葉を返していた。
「…ちょっと声掛けただけじゃないか。そんなに怒ることでもないだろ」
「怒ってなんか無いわ。ただちょっと、分からせなきゃって思っただけよ」
そう言って、どこから取り出したのか、金属バットを男目掛けて振り下ろした。
男はそれをひょいと躱した。
「こわ〜…大事にすんなって言ってんのに、当たったらどうすんだよ」
霧雨さんはちょっとだけ怯えながら、僕たちと一緒に姐さんを見守っていた。
「あれ当たったらひとたまりもないっすよね…」
「いやほんとだよ、何考えてんだか…」
霧雨さんはそう言いながらも、ちょっと上機嫌そうに見える。
きっと、私の女呼びが嬉しいのだろう。
「はぁ、面倒臭い…避けるんじゃないわよ」
姐さんはそう呟くと、再び金属バットを振り下ろした。
「いやいやっ、避けないとこれ当たったら痛いじゃんっ」
「痛くしてるんだから当然でしょ」
ふー、と息を吐きながら、苛立った様子でそう言い放つ。
「次は避けないでね」
思い切り振り下ろされた金属バットは、男の肩を掠めた。
「ひぃ、当たるとこだった…」
「…次は外さないわよ」
「れ、霊夢っ、やめて!!」
霧雨さんがそう叫んで飛び出すと、姐さんに抱き着いた。
「ちょっと、なんで邪魔するのよ」
「もう、いいから、その人だってもうちゃんと分かってくれたと思うし…」
からん、と金属バットが姐さんの手から離され、金属バットを握っていた手は霧雨さんを抱き締めるのに使われた。
「霊夢…!」
「…あんたがあの男のこと許すって言うんなら、もうしないわ」
「許す、許すから早く帰って昨日買ったアイス食べたい」
霧雨さんの言葉に、姐さんの顔が少し綻んだように思えた。
「と、言うことで、今回はこのくらいにしとくわ。次手出したらどうなるかは分かってるでしょうけど」
「あぁ、分かってるさ。もうしないよ」
男は反省したみたいで、ぺこぺこ頭を下げながら、買い物袋を引っ提げてアジトに帰って行った。
「さーて、私達も帰りましょうか」
「アイス、アイスっ」
「はいはいアイスね」
霧雨さんは姐さんと手を繋いで、ご機嫌そうにその手をぶんぶん振り回していた。
なんとも微笑ましい光景。
先輩方の顔も、心做しか優しく見える。
「そういえば、あんたらの分あったかしら…」
「え!?俺らにもくれるんすか!?」
「そりゃあ...ね...私らだけ食べるのも変でしょ」
何言ってんの、と言うように姐さんはそう言うと、くるりと方向を変えた。
「無かったら困るから、スーパー寄って帰りましょ」
「私、ケーキ食べたい」
「...アイスは?」
「アイスも食べる」
姐さんは、もー、と呆れつつも優しい顔をしていた。
ほんと、お似合いカップルだと思う。
そんな光景に思わず顔を緩んでしまう。
先輩方もその様子を優しい目をして眺めていた。
〈おまけ〉
とある手下と霧雨さんのお話
いつかの休憩中、俺はずっと気になっていたことを霧雨さんに聞いた。
「あの、霧雨さんって姐さんがいるところでは戦いませんよね。あれなんでなんすか?」
「...なんだよ、いきなり。なんでもいいだろ」
霧雨さんは迷惑そうにそう言うと、席を立とうとした。
こうなってしまうことは想定済みだ。
でも俺には秘密兵器がある。
「...あ、そういえば俺、姐さんの写真持ってるんですけど」
そう言って、すぐさま懐から秘密兵器こと数枚の写真を取り出す。
「えっ」
慌てた様子でこちらを向く霧雨さんを見て、俺はしたり顔をした。
やっぱり姐さんの事となると反応が違う。
少し前は、霧雨さんは姐さんのことが好きなんだろうと思っていたが、どうやらもうデキてたらしい。
そんな霧雨さんは俺から写真を奪い取ると、それをじっと見つめた。
寝顔だとか、横顔だとか、後ろ姿だとか、そんな写真。
「勝手に取らないでくださいよ」
俺がそう言うと、霧雨さんは渋々といった様子で写真を俺に返した。
「…なんでお前がこんなの持ってんだよ」
なぜ持ってるかというと、普通に隠し撮りしたから。
なんて事を素直に言ってしまうと怒られるので、企業秘密ですよ、なんて言ってはぐらかした。
「寝顔、とか...私でも持ってないのに...」
「欲しいですか?」
俺のその言葉に、霧雨さんはきらりと目を輝かせた。
「ほ、欲しい!」
食いついた。計算通り。
あまりにも事が上手く運ぶので、にやけ顔を隠せない。
顔を戻すために、軽く咳払いをした。
「俺が聞いたこと答えてくれたら、差し上げますよ」
「ぐ...そういう事か...」
霧雨さんは何かを理解したように頷くと、少し悩んでから覚悟を決めたように口を開いた。
「...わかった。でも、誰にも言うなよ?」
「言いませんって」
霧雨さんは俺の言葉を疑いながらも、欲しいという気持ちには勝てなかったみたいで、耳に顔を寄せてきた。
「ほ、ほんとに誰にも言わないんだよな?」
「言いませんってば...」
じゃあ、と言うように、霧雨さんはもう少し顔を寄せた。
近すぎて、かなりドキドキする。
「れ、霊夢に守ってもらうのが…すき…だから…」
霧雨さんはそこまで言うと、突然ぱっと離れた。
「ほ、ほら!言ったから、それ寄越せ!」
「はいはい、分かりましたって」
俺がそう返事をして例の写真を渡すと、霧雨さんは嬉しそうに写真をまじまじと眺めていた。
「それにしても、霧雨さんも可愛いところあるんすね」
「だ、誰にも言うんじゃないぞ…?」
「だから言いませんって」
霧雨さんは俺の言葉を聞いて、ちょっとだけ疑いながらも一応は大丈夫だと判断したようだった。
後日、霧雨さんと俺が2人きりで居たというのが姐さんにバレて、半殺しにされたというのはまた別の話。
〈あとがき〉
ぼんやりと設定を放置してたので書いてみたやつでした
あほっぽいおはなし
たのしいね
めちゃくちゃサボってすみませんでした!
なんか色々…色々…うわーとなっていた…
進捗もあんまりよくない!
来週出るといいね
がんばろー!
みてくれてありがと!またね!
※実際の団体、組織等とは一切関係ありません










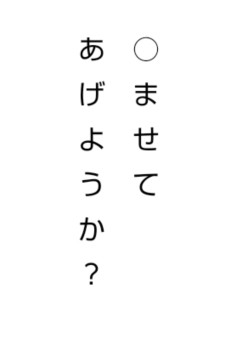

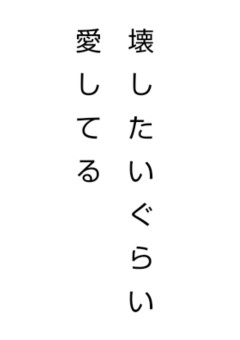
















編集部コメント
主人公は鈍感で口下手ではあるものの『コミュ障』というほどではないので、キャラの作り込みに関しては一考の余地があるものの、楽曲テーマ、オーディオドラマ前提、登場人物の数などの制約が多いコンテストにおいて、条件内できちんと可愛らしくまとまっているお話でした!<br />転校生、幼馴染、親友といった王道ポジションのキャラたちがストーリーの中でそれぞれの役割を果たし、ハッピーな読後感に仕上がっています。