西の国、山茶花家の当主は水仙と呼ばれている。
水仙と野薔薇妃の間に産まれたのが、霞の君である。彼は幼い頃から母譲りの端麗な顔立ちをしていて、西の貴公子と呼ばれ、民衆から愛されていた。
朝顔姫がぼーっと惚けている間に、てきぱきと菊乃が着付けや化粧を施した。
昨日、厠から帰ってきた時から朝顔姫は何か様子がおかしかった。
体調が悪いのかと聞くが、どうやらそうではないらしい。
何かにうっとりと、夢を見ているようだった。
「お嬢様、しっかりなさってください。今日が霞の君様とのお見合いなのですよ」
菊乃に言われ、朝顔姫はぼそっと呟く。
「霞の君…」
鏡を見る。
朝顔姫は、昔から色んな人に母譲りの美しい顔だと言われてきた。
自分でも、美しいことは自覚していたし、その美しさを疑ったことは無かった。自信過剰と思われるかもしれないが、確かに彼女は自分の容姿に自信を持っていた。
別に自信を喪失した訳では無い。でも。
霞の君が、男性とも思えないほどに美しかったこと。しかも、そんな人が自分のお見合い相手であったこと。
もっとしっかり、勉強してくればよかった。
「菊乃…」
「どうかしましたか?」
朝顔姫はじっと真っ直ぐに菊乃を見つめる。
「このお見合いが失敗したら、どうなるの?」
「最悪の場合ですが、東西戦争が勃発して国が滅びます」
朝顔姫ははあっとため息をつく。どうともなく、形容しがたい不安感が拭えない。
そんな様子を察したのか、後ろで剣を研いでいた椿が朝顔姫の肩をポンっと触る。
「お嬢様、気に病む必要はありません。最悪の場合というのは、大体起こらないものです」
朝顔姫は目を丸くした。
なんだかこの男は不思議なことを言っている。それが少しだけ、面白かった。
「ふふ…ありがとう、椿」
椿は笑われた意味がわかっていない様子だった。だが、朝顔姫は少しだけ緊張が解けたようだった。
「それじゃあ行きましょう。お嬢様」
見合いが行われるのは山茶花の者たちが住む、後宮最上級に神聖な場所である。
そこでは時たま宴が行われたりするが、今回はほぼお忍びであるため、最低限人を少なくして執り行われることになっている。
西洋風のシャンデリアが佇んだ大きな間だった。階段を上ると、水仙と野薔薇妃、その間に挟まれた霞の君がいた。
目の前にして、息を呑んだ。
緊張と、少しの好奇心。
菊乃に腰を押され、朝顔姫は三人の前に立った。
「この度お見合いさせていただく、朝顔と申します」
朝顔姫とともに、両脇の菊乃と椿が礼をした。
「顔を上げてください。どうぞ、お座りになって」
朗らかな口調で言ったのは野薔薇妃だった。
温かみがあるが、朱色の着物には、豪勢な橘の文様がされている。野薔薇妃は想定される年齢とは打って変わってとても若く、美しい女性だ。
木製の椅子に座ると、目の前には大きな伊勢海老などの刺身がたくさんある。
普段の朝顔姫なら飛びついてしまうが、手をつねって我慢した。
「遠路はるばるお越しくださりありがとう。お父さんとも話を通してるけど、今回は自己紹介程度のお話が出来たら良いなと思っているよ」
西洋に渡って薬学を学んだりと言う噂を聞いていて、何となく強欲そうな貴族かと思っていたが、水仙もとても朗らかな様子だった。
体格もどことなくふくよかで、優しそうだ。
朝顔姫はほっと胸を撫で下ろす。
「ありがとうございます、水仙様。父からも水仙様のお話は聞いております」
「本当かい?何て言っているかな」
「話している時は、いつも楽しそうですよ。今日は共に釣りをした、今日は競馬をしたと、土産話をたくさんしてくれています」
「そうかい。ふふ、君はお父さんととても仲が良いんだね」
水仙に言われ、朝顔姫はぎこちない笑みを返した。
両脇の夫婦は温かい雰囲気だが、真ん中にいる霞の君だけはずっと無表情だった。昨日は結っていなかった長い髪を、今日は組紐で一つに結っている。昨日、庭園でお転婆していた娘が朝顔姫であるとは思っていないのだろうか。忘れてくれているなら幸いだが。
今のところ、朝顔姫と話しているのは水仙だけである。
(どうしよう…霞の君様に話を振るべきだろうか)
そんな朝顔姫の思惑を察したのか、水仙が突然立ち上がった。
「さてと、早速だけど私たちは去ろうか。後はお若い二人でね」
野薔薇妃に次いで、無言で成すすべがなかった菊乃たちも慌てて立ち上がる。
「それじゃあごゆっくり」
水仙にそう言われ、本当に二人きりになってしまった。
(確かに話せたら良いとは思ったけど、何も話の種がない…どうしたもんかな…)
霞の君は一点を見つめるだけで、ぴくりとも動こうとしない。
美しいが、その姿は人形のようだ。
「霞の君様…今日は、とても良い天気でございますね」
自分でも下手すぎる話の始め方に笑えてしまう。
「ああ」
霞の君はそう言うだけで、自分から話を始めようとはしない。この政略結婚に協力的ではないのだろうか。
だって、顔を上げてくれない。
今日ここに来てから、霞の君は一度も朝顔姫のことを見ようとしてくれなかった。
わかっていたけれど、少し悲しい。
(ここでめげたら…折角、父上様が…)
わかっている。被害妄想だ。
なのに、どうしようも出来ない自分に腹が立って仕方なかった。
「…顔を」
霞の君が呟いた。
昨日も聞いた、麗しい玲瓏な声だった。
「見ても良いか」
朝顔姫はハッと顔を上げる。
ああ気が付いたら、顔を下げていたのは自分のようだった。
真っ直ぐな、霞の君の視線が突き刺さる。
「私は、人の顔と名前が覚えられない」
霞の君の口から出た言葉は、信じ難いものだった。
だが、歪な理由だが自分から話を始めてくれたのが嬉しくて、朝顔姫はじっと霞の君を話を聞く。
「国の主になる者として、有るまじきことだと思う。だが幼い頃から、他人に興味を持つことが普通の子よりも出来なかった。感情の起伏も少ないし、侍女たちの中にはそんな私を不気味に思って嫌う者も多かった。私は冷たい人間だ。君に、とても迷惑をかけると思う」
霞の君は表情は変わらないが、なぜだろう、とても寂しそうな風に朝顔姫は感じた。
朝顔姫はふうっと息を吐き、真っ直ぐに霞の君を見つめる。
「霞の君様、私には父がおります」
突然始まった朝顔姫の話に、霞の君はじっと耳を傾ける。
ああやっぱり、朝顔姫は確信をした。
「父の両親、つまり私の祖父母ですが。祖父母は流行病で父を産んですぐ亡くなりました。兄弟もいなかったものです。落葉松の血を受け継いだのは父だけだったため、父にはたくさんの妃がもうけられました。ですが、父は生涯愛しているのは撫子、私の母だけだと言います。母も身体が弱かったため、私を産んで死にました。父はとても私を大事に思っていて、私が成長すればそれを喜ぶし、私が体調を崩せば何よりも心配してくれる。とても優しい父です。ですがある日、私は気づいてしまいました。父は私に、母の幻想を重ねているのだと。私は母とそっくりだとよく言われます。父にとって、私は母の生まれ変わりだと思われてしまっているのだと感じてからは、素直に愛を受け取れなくなりました。その上、私は人の愛し方すらも忘れてしまったのです」
突然された重たい話に、霞の君は何と言っていいか分からない様子だった。最大限、こちらのことを気遣っているのがよくわかった。
朝顔姫は慌てて話を付け足す。
「つまり、私も貴方も“不器用”というだけなのです!」
朝顔姫は勢い余って、声を大きくしてしまった。
「あの…身の上を話したから同情してほしいという訳では全くありません。つまりその…霞の君様が人に興味を持てないというように、私も人の愛し方が分からないのです。だから…その、私たち不器用な者同士、少しずつ寄り添い合ってみませんか?という意味です…」
朝顔姫の声はどんどん弱まっていった。
自分の言いたいことが十分に伝えきれていない気がして、もどかしかった。
おかしなことを言っていると思われないか少し不安だったが、霞の君は優しい表情でふっと笑った。
「なるほど…」
霞の君はそう言って、立ち上がった。
窓に向かい、大きな西の国を見渡す。
「君は僕の欠点も、愛す努力をしてくれるということかな?」
霞の君は顔だけ振り向かせて、意地悪な、男の人には有るまじき、可愛らしい表情を浮かべた。
この人は自分の顔を理解しすぎている、と朝顔姫は思う。
「…はい」
「君は普段、もっと雄々しい口調をしていたりしないか?」
「何故それをっ…?」
やってしまった、と朝顔姫は口を手で覆った。
何故と言ってしまう前に適当に誤魔化しておけばよかったのに、驚きすぎて思わず言葉に出てしまった。
霞の君は顔を綻ばせる。その雰囲気は、どことなく水仙や野薔薇妃に似ていた。
「僕は君を見たことがある。いつかはわからないが、思い出せたら良いな」
霞の君が抱く寂しさが、何となくわかった気がした。
彼は人に興味が無いわけでは、きっとない。
きっととても優しくて、人との関わり方がいつしかわからなくなってしまったのだろうと、推測だが、朝顔姫は思った。
朝顔姫も立ち上がり、霞の君の隣に立って西国を見渡す。
「霞の君様、私には夢があるのです」





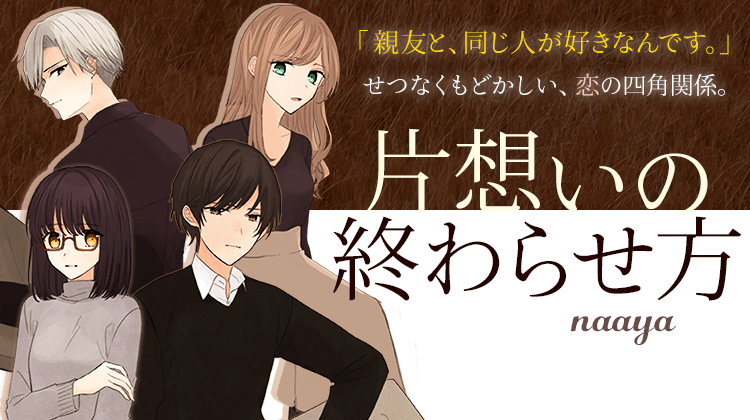












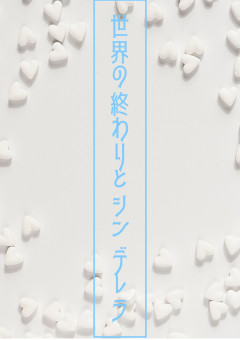
編集部コメント
引きこもりのおじさんと真面目な女子高生という組み合わせがユニーク。コンテストテーマである「タイムカプセル」が、世代の違う二人をつなぎ、物語を進めるアイテムとして存在感を発揮しています。<br />登場人物が自分の過去と向き合い、未来に向かって成長していく過程が丁寧な構成で描かれていました。