好きになっちゃいけないってずっと思ってた。
勝手にブレーキをかけて、バーテンダーだからろくなやつじゃないとか勝手に思ってて。
でも、彼と一緒にいる時間が自然に長くなって、本当の彼はとっても繊細で臆病なんだと思ったから。
そんな部分も知ってしまったら、好きの気持ちに対するブレーキなんてなくなった。
だって、私と変わらないんだもの。
傷つくことが怖くて、誰かを想うことも怖くて。
辛い思いなんてしたくなくて、恋をする気持ちにそっと蓋をしようとした。
誰かに裏切られたくなくて、逃げていた私に優しく寄り添ってくれたのは彼だった。
『マスター、彼にXYZを。』
「かしこまりました。」
「意味…知ってるの?」
『調べたって前に言ったでしょ?
別に健太郎のためだけじゃないけど。』
ちょうど偶然、とあるバーの企業広告を頼まれて、至高の一杯を提供するバーにしたいということだったので、カクテル言葉を調べて、黒の背景に逆三角のカクテルグラスで、このカクテルを作ってもらった。
バーテンダーが、カウンターの向こうから差し出すような構図で取られた写真は、高級感にあふれていて、まさに至高の一杯という雰囲気になっていて。
広告として採用されるのはまだまだ後の話だけれど、いい仕事をしたと思った。
その時に見たのが、このカクテル言葉だった。
彼と結ばれたときには、このカクテルをプレゼントしよう…そう思っていたけれど、こんな緊張する空間になるなんて思ってなかったな。
「お待たせしました。XYZです。」
「ありがとう。」
『ねえ、健太郎。』
「ん?」
出されたカクテルを飲んでいる彼を呼ぶと、グラスを片手にこちらを向いてくれる。
夜景と彼とカクテル…なんてどこの恋愛ドラマよっていうようなシチュエーションだけれど、そんな王道のシチュエーションも、彼にはまってしまう…と思う。
『これから、たくさんぶつかることもあると思う。
でも、健太郎の隣にずっといたい。』
「うん。」
ばちんとぶつかった健太郎の視線が甘くて、引き寄せられるようにキスをした。
恋人になって初めてのキスはレモンの味がした。
後日、会社で健太郎と付き合うことになったと村上くんに報告したところ、ワンナイトなのは気に食わないけどおめでとうございますって言われた。
付き合うまでの間にワンナイトどころかツーナイトもスリーナイトもあったなんて口が裂けても言えなくて、ひやひやしたけれど。
『村上くんも、幸せになってね。』
「それ、あなた先輩が言うんですか?」
『間違いなく、後輩としては一番好きだよ。』
「ずるいなぁ…、そんなこと言われたら
何も言えなくなっちゃうじゃないですか。」
優しい目をして、おめでとうございますと言ってくれた彼は、きっとこれからもいい後輩で、素敵な相棒でいてくれるはず。
「あなた先輩!営業連れて行ってください。」
『はいはい、いい加減免許取ったら?』
「そりゃあ先々は取りますけど。
もう少しだけ、先輩の助手席は俺のもので!」
『そういつまでも面倒見てあげないよ~?』
「それは困ります!!」
笑顔で行ってくるあたり本当に抜け目がないけど。
仕方がないからもうしばらくは、助手席は彼の特等席にしておこう。
「あなた。」
営業車から降りて、ビルのほうに歩いて行く間、聞きなれた声に呼び止められて振り返ると、そこには、まだ切った髪に見慣れない健太郎がいた。
「あー!ワンナイトバーテンダー!」
『ちょっと、村上くん!』
「まだ俺、ワンナイトって言われてるの?」
『彼氏だとは言ったから、ごめんね健太郎…。』
気にしてないよ、って笑ってる彼は本当に笑ってるだけらしい。
それだけでもホッとする。
「今日は?終わった後。」
『行くよ。』
「わかった、待ってるね。」
『うん。』
頭をポンポンとして去っていく彼。
昼間に会えたことも奇跡みたいなのに夜の約束もできてうれしくなる。
「彼氏みたーい…」
『彼氏なのよ。』
「ちぇー…」
仕事を終えて、バーの入り口をくぐるといらっしゃいといういつもの彼の声。
違うのは、髪型と私たちの関係。
いつもの席に座って、ふと気づいたことを口にした。
『そういえば表の看板クローズになってた。
早かった?』
「んーん?今日は貸し切り。」
『なんで?』
「俺が、あなたと二人で話がしたいから。」
『職権乱用。』
そういうとかわいくないなあって笑った。
なにも注文していないのに彼は手慣れた手つきでお酒をシェイカーに入れ、蓋をする。
「何ができると思う?」
『材料は?』
「ラムとコアントロー、レモンジュース。」
『…、もしかして。』
にやっと笑った彼はシェイカーを下ろして、中の液体をカクテルグラスに注ぐ。
氷のカランという音が私たち以外誰もいないバーの空間に響いた。
「お待たせしました。XYZです。」
『…これがしたかった?』
「だって、先越されたから!」
『ふふ、ありがと。嬉しい。』
「これからもずっと、一緒にいよう?」
そう言った彼と私の間には、バーカウンターという一つの境界線。
永遠に超えられないと思っていたこの線を、今の私たちは簡単に超えられる。
彼の作る美味しいお酒がくれた最高の贈り物。
Fin
XYZ
カクテル言葉:永遠にあなたのもの






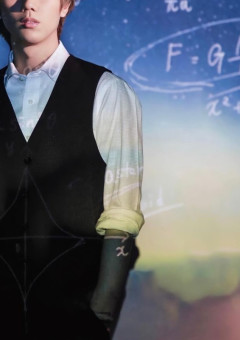
























編集部コメント
引きこもりのおじさんと真面目な女子高生という組み合わせがユニーク。コンテストテーマである「タイムカプセル」が、世代の違う二人をつなぎ、物語を進めるアイテムとして存在感を発揮しています。<br />登場人物が自分の過去と向き合い、未来に向かって成長していく過程が丁寧な構成で描かれていました。