私が仕事に行く際に通勤しているいつも通る道に、いつもなら梅原さんが通るはずなのに最近見かけなくなった。
一週間前までは、通る度会釈したり、口でがんばって下さいと言ってくれた。
私はがっかりしながら、歯を磨いていた。
その時、一通のメールが届いていた。
それは梅原さんだった。
私は歯磨きしながら携帯を弄っていたので口から吐きだしそうになった。
ゴホゴホと咳こみながら、メールを見た。
すると、内容は明日、会えませんかというお誘いだった。
私は異性からの誘いは初めてだったので学生みたいに胸をときめかせていた。
本当に恋をしたことないのかと考えると、今思えば恋っぽいことをしたことだってあることはある。
私に好意を持って接してくる異性はいた。
私がその気持ちに薄々気づいて、一方的に冷たく接したりしたからだ。
その男性は、私は嫌いではなかった。
でも、あの時の私はよく分かっていなかったのだ、恋を。
その時の私は自意識過剰だったかもしれないが、大体私は人の気持ちが分かるから恋が出来ない。
でも、今回の恋は違う。
私が初めて好きになった人。
それは一番違う所。
私は、明日は仕事が休みなので、メールに明日、大丈夫ですと返信をした。
すると、すぐ返ってきて。
では明日、俺達がいつも通る所でと書いてあった。
いつも通る所。
それは、紛れもなく私が告白した所である。
翌日
私は珍しく早起きをした。
母親に、休日だっていうのに早いわね、どうしたのと言われたくらいだ。
休日は、友達に会うか、用事がなきゃ行かないから。
インドアの私にとっては、外に出かけるのは一大事なのだ。
今から私は梅原さんに会う。
プライベートで会うのはこれが初めて。
私はドキドキがとまらなかった。
いつもの通る道を歩くけど、今日は何か気分が違う。
私はウキウキしながらいつもの通る道を踵を地面につけ、歩いた。
私は待ち時間より早く着いてしまった。
待ち合わせ時間は、11時。
今は、10時30分。
早い。まだ、着いている訳がない。
楽しみだとはいえ、早く着きすぎではないか。
周りを見渡した。
休日なので、人が沢山いた。
今日は近くでイベントがあるのか、観光客や近所の人達が私が待っている真正面の公園で賑わっていた。
賑わう声が聞こえる中、やはり梅原さんの姿はなかった。
私は空を見て、目を瞑り梅原さんのことを考えていた。
その時
「何、目瞑ってるんですか?」
男性の声が聞こえた。
「え?梅原さん?」
梅原さんは、私の肩にポンと手をのせて言った。
待ち合わせ時間は、11時なはずなのに、なんで!
ってか、私の肩に梅原さんの手が…
もう会って数秒も経ってないのにドキドキが止まらないよ。
「う、梅原さん。待ち合わせ時間まだまだですよ。早くないですか?」
私はこの感情を隠しながら梅原さんに言った。
「いや、分かってましたよ。でも、ここ散策したいなと思って」
梅原さんは、私に向けた本当の笑顔か分からないがニコと笑った。
「そうでしたか……では、早いですけど一緒に散策しますか?」
「そうですね、早く来たことだし。後、花守さんともきちんと話をしなくてはならないと思うので……」
梅原さんは、眼鏡をクイとあげてから俯きながら私に言った。
「それなら、私の勤務先の近くでお勧めな所を連れてきたいんですけどいいですか?」
私は梅原さんに提案した。
「いいですけど…あれ見なくていいですか?」
梅原さんが指をさした先は、私達の目の前にあった公園で何かのイベントが行われていた。
「私は、見なくていいですよ。人たくさんいるの苦手なんで」
梅原さんは、安心したような顔で
「良かったです。俺も苦手なんですよ」
梅原さんは、自分の髪を右手で掻きながら言った。
私に気を遣ってくれたんだ。
優しいな
私はそんなことを思っていたら、
「花守さん」
梅原さんが私のことを初めて名前で呼んでくれた。
「名前……覚えてくれたんですね?」
私は梅原さんに笑顔で話しかける。
もう私の胸の中は嬉しくてしょうがないのだ。
「……それは覚えてますよ」
梅原さんは、ちょっと照れ臭そうに言った。
やはり、仕事とプライベートでは違うなと思えた。
いつもはスーツを着ているのに、長袖に長ズボンというラフな格好だった。
スーツ姿もいいけど、本当の梅原さんを見れた気がして何か嬉しい。
ウフフと私はにやけた。
それを気づいたのか梅原さんは
「どうかしましたか?」
「い、いえ」
私は首を振った。
「それでは、行きますか?」
梅原さんは私の前を歩き始めた。
意外にも、引っ張ってくれるんだと思えた。
朝見る度、しっかりしているという印象を受けていた。
だから、本当に私の理想の人だ再確認した。
本当に変な感じ
いつも通る道で、気になった人を好きになった。
その人が目の前にいる。
考えられないことだ、私にとって
私の前に出ていた梅原さんは、私の隣に来て、私に話しかけてきた。
「花守さんはいつも休日に何してるんですか?」
急に質問きたー!
まさか予想していなかったが、私は答えた。
「えーと、まあゲームしたり、友達と遊んだりしたりしてますよ」
梅原さんが意外そうな顔をしていた。
「へえー、意外ですね。可愛いのが好きそうなイメージでした」
私達は、真っ直ぐな道から右の角を曲がった。
「……そうですか?」
梅原さんは、頷く。
「今日の服も可愛い系統でしたから……」
可愛い系統……
可愛い……
私のことが可愛いと言っている訳じゃないもんね。
調子のらない、のらない。
私は頭を抱えて、そう自分に言い聞かせた。
「だ、大丈夫ですか?」
梅原さんは、心配そうに私に話しかけてきた。
「大丈夫ですよ。あ、あともう少しで私のお勧め場所ですから。喫茶店「星」なんですけど…いいですか?お昼食べたら、近くでブラブラしませんか?」
梅原さんは、聞いたことあるなというような顔をしていた。
「そこで大丈夫ですか?」
「……あのもしかして、美容院の隣のあの喫茶店「星」ですか?」
「……はい、そうです。何で知ってるんですか⁈」
私は梅原さんを見て驚いた。
「俺そこの近くに住んでいるんですよ」
「えーー!そ、そうだったんですか。じゃあ、私の職場にも近かったりしますかかね……?」
梅原さんの横に歩きながら、私は話しかけた。
「……そうかもしれません。よく周り見ないんで……分かりませんけど」
「そうだったんですね……ではそこでいいですか?」
「はい、そうですね」
梅原さんは、私の提案にのってくれた。
喫茶店「星」に着くと
「い、いらっしゃいませ」
マスターの声がした。
「真白ちゃーん、暇してた所だったの。ちょうどよか……」
店長は、ちょうどよかった、飲んでいきなと言いたかったのだろう。
私の後ろを見た、マスターは
「え?何?真白ちゃん。今度こそ彼氏?」
「……ち、違うって。マスター」
マスターは、怪しいねという顔で私を見てくる。
私はマスターに言われる前に梅原さんとテーブルに座った。
この前、犬飼さんと座った所と同じだった。
客がいない喫茶店で暇なマスターを呼び、メニューと水を持ってきてと指示した。
私達は、メニューを見た。
「どうしますか?」
私は梅原さんに話しかける。
梅原さんは、眼鏡をかけているのにメニューと眼鏡を近づけて、真剣に悩んでいる様子でメニューとにらめっこしている。
私はその様子を見て、なんか可愛いと思えて心の中でにやけていた。
「………では、オムライスで」
私は笑ってしまった。
「何笑ってるんですか?」
梅原さんは、私を見て言った。
「だって、犬飼さんと同じメニュー頼むんですもん」
梅原さんは、眼鏡をクイとあげて、私に向けた本当の笑顔ではない笑顔をニコと笑って言った。
私はその時に彼が心底で笑ってないと気づいた。眼鏡をかけていたけど、目は笑ってなかった。
「あー、陽介が……花守さん。陽介からなんか聞きましたか?」
梅原さんは、思い出したかのように聞いてきた。
多分、犬飼さんが来たことについて聞いているのだろう。
「……はい」
「そうですか…その前に花守さん食べたいの選んで下さい」
私は梅原さんの話を聞き入っていて
選んでいなかった。
いつもならすぐ決められるのに……
「えーと私は、スパゲティで」
「マスター、オムライス一つとスパゲティ一つ下さい」
マスターはめんどくさそうに立ち上がり、はい、はいと作り始めた。
私達しかお客がいない為、やけに静かだった。
私は口に水を含ませた。
緊張していることをバレないように
「…花守さん。多分陽介から聞いてると思いますが…」
私は梅原さんが話をする前に私は言った。
「女性が苦手なんですよね?」
水が入っているコップを両手で持ち、私は言った。
「……はい。本当は、俺が花守さんに直接そのことを話をすべきでした。しかし……」
「しかし?」
梅原さんは、下を向き、私からは見えないが多分ズボンで両手の拳を強く握っていた。
「………俺は、母親から幼い頃暴力を受けられていました」
私は驚いた。
梅原さんは、かっこ良くて、背も高くて私にとって完璧な人に見えていた。
「早くに父親を亡くしてしまって、母親一人で俺と弟を育てていました」
弟、いたんだ
知らなかった
梅原さんは、私を見て、ハッと思い出したかのように
「……すいません、こんな話」
梅原さんは、私を見て言った。
「いえ、大丈夫ですよ」
私は笑顔で答えた。
「……友達として、花守さんには俺のこと知っていてほしいんです」
梅原さんは、俯きながら言った。
「……はい、私も梅原さんの事知りたいです」
友達としてか……と私は思いながら、水をまた口に含み言った。
「ありがとう…ございます。…父親が亡くなった後、母親は、俺に暴力するようになり、俺がおもちゃだから叩いても壊れないんだからと言って…毎日……俺のことを叩いては蹴っていました」
私は、梅原さんの話をまばたきしないで聞いていた。
梅原さんは、苦しそうに胸を掴んで話してくれた。
「弟は、俺とは正反対に優しく接していました。しかし、俺をストレスを軽減する道具として、弟は、きちんとした子供として…」
梅原さんは、私を見て言った。
「……そんなの……梅原さんが?」
「……大丈夫ですよ」
梅原さんは、ズボンのポケットからハンカチを取り出して額の汗をふき取った。
汗を拭き取り、梅原さんは眼鏡を外してハンカチで拭いていた。
真面目な話をしているのに、私は目の前の梅原さんが眼鏡を外している姿に見入ってしまった。
梅原さんの眼鏡を外した姿。
初めて見た。眼鏡なくても、かっこいい、芸能人になれるのではないかと私は思った。
だが、梅原さんが眼鏡をつけた瞬間、私は何かのスイッチが切れたのか大きい声で梅原さんに言った。
「梅原さんが大丈夫な訳ないじゃないですか?」
私は立ち上がりテーブルを叩いて言った。
その時、マスターが出来たよと言って、
オムライスとスパゲティを持ってきてくれた。
マスターは、気を遣ってくれたのか、なにも言わないで立ち去っていた。
「……座って下さい」
「すいません」
私は梅原さんに謝った。
「食べながら話しをしましょう」
「はい……」
「花守さん、俺は今日花守さんとこうして話しをしてきましたが、本当の俺じゃないんです。いつも見ている俺はきちんとしているように見えますが、本当の俺は臆病なんです。母親から受けられた暴力で女性の顔を見ると、母親を思い出すんです」
「では、私といるとお母さんを思い出しますんですか?」
私は今焦ってる。
私はこの人を逃したら、いい人を見つける気配すらないからだ。
「……分からないんです。花守さんとは……でも、付き合う自信がないんです」
梅原さんは、スプーンを右手で持ち、一口だけ食べて言った。
私はまた振られたのか
梅原さんは、私のことが好きなのかよく分からない。
でも、本当の彼が見れないということは私には好意がなかったのか
「……分かりました。でも、たまにメールしてもいいですよね?」
私はスパゲティをクルクル回しながら言った。
「……それは勿論」
「あ、そうだ。ここの席、犬飼さんも座ったんですよ」
私達は、この前来た犬飼さんの話を少しして喫茶店「星」を出た。
私の勤め先に連れて行って、この辺りをブラブラ散策して別れた。
私は、別れ際に何かあったら相談にのりますよと言った。
その時の梅原さんの顔が満面の笑みであったが、やはり目は笑っていなかった。
私はその表情を見て、梅原さんははいと答えてくれた。
私は、その顔を忘れられない。
笑顔の裏に本当の彼はいるのだろうか
私は思った。


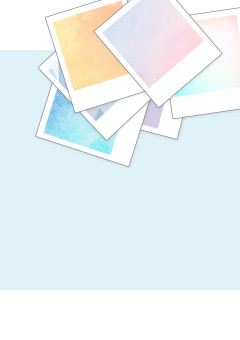
















編集部コメント
主人公は鈍感で口下手ではあるものの『コミュ障』というほどではないので、キャラの作り込みに関しては一考の余地があるものの、楽曲テーマ、オーディオドラマ前提、登場人物の数などの制約が多いコンテストにおいて、条件内できちんと可愛らしくまとまっているお話でした!<br />転校生、幼馴染、親友といった王道ポジションのキャラたちがストーリーの中でそれぞれの役割を果たし、ハッピーな読後感に仕上がっています。