辛さって実は味覚じゃなくて痛覚だ。
それは知っていたし、甘党の私にとって辛いものは苦手なものだから納得のいく事実。
けれどまさか。
辛さ以外にもあんなにも暴力的な味があるなんて──。
「おや、ルティアさん。またここにいるのですか。私の秘密の場所だったんですが」
「ここって大学の敷地内だったと思いますけどぉ。いつからヴァイス先輩の所有物になったんです?」
セントミラ魔法大学へ入学して一年が経った。
私こと、ルティア・ミスティックは魔法の世界にずぶずぶとのめり込み…授業と食事と睡眠の時間以外のほとんどを本にかじりつくようにして過ごしていた。
最初は苦手だった魔法理論も少しずつ攻略し始め、一年生の最終試験ではついに総合成績学年一位になることができた。
それによって、最初はただ魔力が強いだけの脳筋庶民扱いして来ていた周りの同級生たちも遠目からこちらを睨んでくるだけになり、とっても学園生活が楽になったのである。
「大したものですよ。ルティアさん、貴女は今まで全く勉学としての魔法には触れてこなかったわけでしょう?直感だけで魔法を使っていたということですね」
ヴァイス・ランドシーカーのどこか嫌味っぽい言い回しにモヤる。週一くらいで出会う度に思うのだけれど、どうしてこの男は毎回こういう言い方しかしてこないのだろう。
「まぁ、自分がどれだけ効率の悪い魔力運用をしていたかはよく分かりましたねぇ。今までの数倍は魔力がもつようになりましたよぉ」
「…恐ろしいことを言いますね。それ、本気ですか?入学試験であんなバカみたいな火力のインフェルノを放っておいて?」
「嘘言ってどうするんですー?あれ、全魔力突っ込んでたんですからねぇ」
ムカついていたから、にやりと笑ってそのまま私は手元の分厚い本に視線を戻した。
魔法の勉強は、すごく楽しかった。
理論も分からないまま覚えた炎の魔法も面白かったけれど、「知識」というものはそれ以上に沼だった。生まれつきの魔力量に恵まれていたらしい私は、効率的な魔法理論を取り入れれば取り入れるだけできることが増えていったのだ。
「……フフ」
「……なんです?」
「いえ、ずいぶん楽しそうだと思いまして」
まさにその通り。
けれど彼に見透かされてそれをそのまま認めるのが気に入らなくて、アイスブルーの瞳を睨み返す。しかしヴァイス先輩はにこにこと涼やかに笑うだけで、凄んだ私なんて怖くもなんともないらしかった。
それも気に入らなくて視線を逸らす。読み途中の本に戻るけれど、もう既に集中できなくなってしまっていた。
「さて、そんな将来有望な後輩に優秀な先輩から学年一位のお祝いをさしあげましょう」
「……自分で優秀って、ナルシストー」
「何か言いましたか?」
「べつにぃ」
笑いながら持っていた袋から何かを取り出すヴァイス先輩。……黒い、ゼリー?
「なんですか、それ?」
「フフフ、これは知る人ぞ知るセントミラの名物スイーツ。その名もカフジェレーと言います」
「へえぇ……」
知る人ぞ知る、すいーつ。
スイーツ好きの私からしたら絶対に聞き逃してはいけない情報だ。
「あなた、いつも図書館にこもってばかりでセントミラの観光をしていないでしょう。少しでもいい所を知ってもらえればと思いましてね」
「ヴァイス先輩……」
そう言ってスプーンとカフジェレーの入った器を私へ差し出してくる。……いつも顔を合わせれば皮肉や嫌味の応酬で「ああ言えばこう言う」って感じのやり取りしかしてこなかった私たち。こんなのってはじめてじゃないだろうか。
「……じゃあ、ありがたく、いただきます」
「どうぞ」
ヴァイス先輩の手から器を受け取る。触れたその手は、少し冷たかった。
「……た、食べにくいんですけどぉ……」
「フフ、お気にならさず」
頬杖をついて、にこにこにこにこ笑いながらこちらを眺めているヴァイス先輩。不満に思いながらも、せっかく気を利かせてプレゼントをくれたんだからとスプーンを香ばしい香りの中に沈めこんだ。……嗅いだことのないにおい。
左側から熱い視線が突き刺さるのを感じながら、ぎこちなく口元へそれを運ぶ。近くなればなるほど、独特の爽やかでビターな香りが強まった。
色も黒いし、香りもこの系統だと甘さ控えめの大人向けスイーツと言ったところだろうか?少し苦いのかもしれないな──、
と。
口を開けてそう思ったところで、一瞬私の記憶は飛んでいる。次の瞬間、私の視界に星が飛んだからだ。ほんとうに一瞬視界が違うもので埋め尽くされた。
もちろん、先輩が私に毒物を盛ったわけではない。このカフジェレーというものは正真正銘食べられるものだ。実際ヴァイス先輩はこれを好んで食べ、売っているお店のお得意さんなのだと言う。
──いや、「毒物」ではないだけで、「劇物」ではあるのだけれど──、
「…………う゛えぇ……」
「ルティアさん!?どうしたんですか、涙が…!」
なんとかして口の中のものを飲み下した瞬間、私の口から出たのは苦悶を表すうめき声だった。……なんだ。なんなんだこれは。この強烈な不快感は。
「……に、」
「に……?」
「にがーーーーいっっ…………!!」
……こんなに苦いものが名物だなんて、セントミラの人たちは苦味を感じることが出来ないの!?
そう思ってしまうのも仕方がないくらい、その苦味は暴力的だった。
こんなのがスイーツなわけない。
私が知っているスイーツはもっとこう。あまくてふわふわしたものだ。
「わ、わ、私になんの恨みがあるんですかぁ……!」
「どうして!?」
くしゃくしゃになった私の顔を見て、ヴァイス先輩があわてている。
……いやがらせだ、いやがらせだこんなの……!!
「ヴァイス先輩が私をどう思ってるのか、はっきりわかりましたよぉ……」
「……ル、ルティアさん……?」
「上等です。受けてたちますよ……!」
「何の話ですか!?」
口元をおさえて目に涙をためたまま、ヴァイス先輩を睨みつける。未だ口の中で暴虐の限りを尽くすカフジェレーに必死に抵抗する。
……この空に誓う。
絶対、この男より上の成績をとって鼻をあかしてやる。
──これが、この先ヴァイス・ランドシーカーとルティア・ミスティックの間で長きに渡り繰り返されるカフジェレー戦争の幕開けであった。








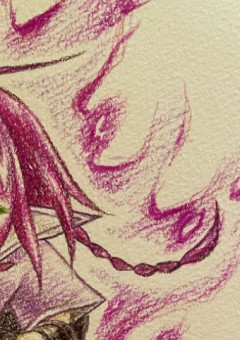



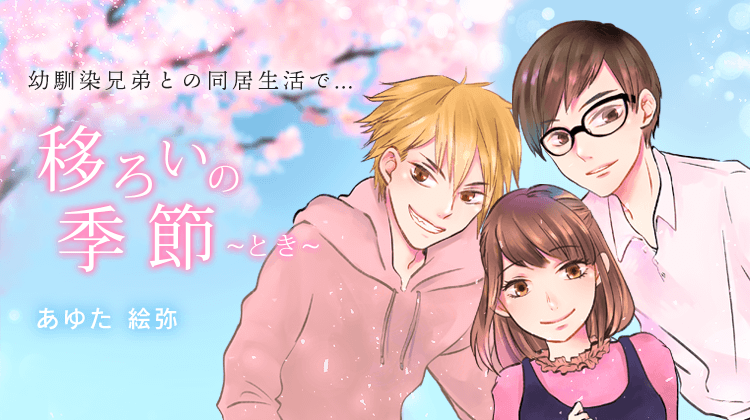













編集部コメント
引きこもりのおじさんと真面目な女子高生という組み合わせがユニーク。コンテストテーマである「タイムカプセル」が、世代の違う二人をつなぎ、物語を進めるアイテムとして存在感を発揮しています。<br />登場人物が自分の過去と向き合い、未来に向かって成長していく過程が丁寧な構成で描かれていました。